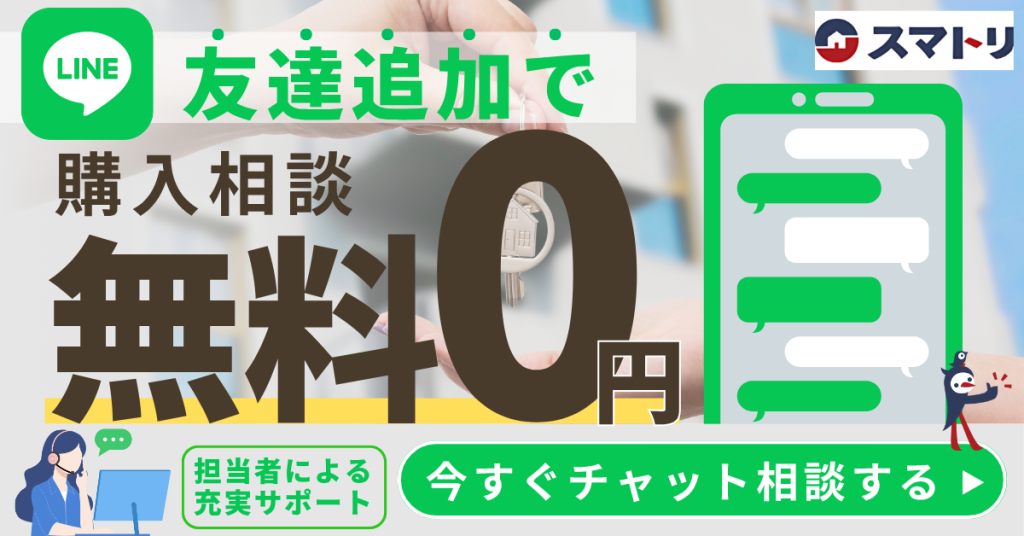不動産購入時にかかる税金は4つ!種類や知っておきたい控除も解説
「今度不動産を購入するけど税金はいくらくらいかかるのだろう?」
「不動産購入時にかかる税金って何があるの?」など、不動産購入時にどんな税金を支払う必要があるかを知らない人も多いでしょう。
不動産を売却して利益を得た場合に税金を支払うのはわかるけど、購入するだけでなぜ税金を支払わないといけないの?と驚かれる方も少なくありません。
不動産購入時には、仲介手数料や登記費用などの経費に加えて、不動産の購入をする際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税の4つの税金がかかります。

不動産の購入は大きな金額が動きますから、購入時にかかる税金の全体像を把握し、どの程度費用が必要かをイメージすることが重要です。
今回の記事では、不動産購入時、購入後に必要な税金と控除などの活用できる特例について解説していきます。徴収される税金について税の種類や計算方法、軽減措置などをわかりやすくお話していきますので一緒に理解を深めていきましょう。
これから不動産の購入を検討しているのでどんな税金が必要なのかを知りたいという方は、最後までこの記事を読んでください!
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
目次
印紙税

印紙税は、不動産売買契約書などの課税文書にかかる税金です。
不動産の購入にあたっては、他にも住宅ローンの金銭消費貸借契約書や建築請負契約書にも印紙税が課税されます。税額は不動産の売買金額など契約書に記載された金額によって異なることを覚えておきましょう。
納税の方法は、貼付した印紙に印鑑で割印を押すと納税完了です。
一般的には、売主、買主が契約書に押した印鑑で割印をしますが、片方の印鑑だけでも特に問題はありません。
記載金額が10万円を超える売買契約書は軽減税率が適応される
印紙税の納税額については、契約書に記載される金額によって以下の表のようになります。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までは、記載金額が10万円を超える売買契約書については右側の軽減税率が適用されています。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円以下を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
印紙税がかからないケースもある
一方で、印紙税がかからないケースもあります。下記をご覧ください。
①記載金額が1万円未満の場合
契約書に記載する金額が1万円未満の場合は印紙税が必要ありません。
②契約書を1通のみ作成する場合
不動産売買契約書は、売主、買主のそれぞれ1通ずつ計2通作成するのが一般的です。
この場合は、それぞれの契約書に印紙を貼ることになるので印紙が2枚必要になります。
②の場合、契約書を1通のみ作成して一方は写し(コピー)を保管することで印紙税を節約する方法もあります。
この場合は、印紙代は1枚で済みますが、写しであっても当事者直筆の署名押印等がある場合は本契約書と同等とみなされて印紙税を請求されることもあるので注意しておきましょう。
第1号文書から第4号文書までの印紙税の一覧表や印紙税額については、国税庁のNo.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書までをご確認ください。
登録免許税

登録免許税は、不動産を購入に関する様々な登記を行う際に必要となる税金です。
登記の種類には、所有権の移転や抵当権の設定などがあり、登記する内容によって税率が異なります。
登録免許税は国税ですが、登記する法務局に現金で納税を行います。
登記の種類は3種類ある
登録免許税が必要な登記は、①所有権保存、②所有権の移転、③抵当権の設定の3つです。
①所有権保存登記
所有権の保存登記とは、表題部しかない不動産に対してはじめてする所有権の登記のことを言います。
建築中の新築戸建を購入した場合などに行います。
▼不動産の所有権とは?
不動産における所有権とは、購入した物件を自由に使用・収益・処分ができる権利のことを言います。この権利があれば、法令の範囲内であればご自身で自由に他人に貸して収益を得たり、売ったりすることも可能です。
②所有権移転登記
所有権の移転登記とは、売買などによって所有者が変わった(移転した)場合に行う登記です。
不動産の購入前は売主の名義が登記されていますが、所有権移転登記することで買主の名義に書き換えを行います。
③抵当権設定登記
抵当権設定登記は、不動産の購入の際に住宅ローンで金融機関からお金を借りた場合に抵当権者である金融機関が対象の不動産に抵当権を設定するための登記です。
金融機関は抵当権を設定することで、万が一借主が返済できないときには対象不動産を競売するなどして資金を回収することができます。
登録免許税の計算方法と軽減税率が適応されるケース
登録免許税は、「税額=課税標準×税率」で計算します。
登録免許税は、土地、建物のそれぞれにかかりますが、いずれも軽減税率が適応されるケースがあります。
土地、建物の税率と軽減税率については以下のとおりです。
①土地の場合
令和8年3月31日までの間に所有権の移転登記を行う場合は1.5%の軽減税率が適応されます。
| 税率 | 軽減税率 | |
| 所有権の保存 | 0.4% | |
| 所有権の移転 | 2.0% | 1.5% |
| 抵当権の設定 | 0.4% |
②建物の場合
令和6年3月31日までの間に所有権の保存、移転、抵当権の設定を行う際には一定の要件を満たすことで軽減税率が適用されます。
要件には、各行政庁が認定する長期優良住宅、認定低炭素住宅の購入などがあります。
登記申請に当たって、その家屋の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意しましょう。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
| 税率 | 軽減税率(一般住宅) | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | |
| 所有権の保存 | 0.4% | 0.15% | 0.15% | 0.1% |
| 所有権の移転 | 2.0% | 0.3% | マンション0.1% 戸建0.2% | 0.1% |
| 抵当権の設定 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
不動産取得税

不動産取得税は、不動産を購入した際に物件所在地の自治体支払う税金のことで購入してから数か月後に納付書が届きます。
ある程度まとまった資金が必要になるので、不動産取得税の支払いがあることを忘れないように注意しましょう。
不動産取得税の計算方法と受けられる軽減税率
不動産取得税の税額は、以下の方法で計算できます。
不動産取得税=課税標準額×税率
①課税標準額
課税標準額は、購入価格ではなく、固定資産税評価額で計算します。
▼固定資産税評価額確認のポイント
固定資産税評価額は、購入時に売主からもらえる購入年度の固定資産税評価証明書や固定資産税支払通知書などで確認することができます。
手元にない場合は、各市町村で固定資産税評価証明書を取得するか、閲覧するなどして自分で確認しましょう。
②税率と軽減税率
| 税率 | 軽減税率 | |
| 土地 | 4% | 3% |
| 家屋(住宅) | 4% | 3% |
| 家屋(住宅以外) | 4% |
不動産取得税の税率については、土地・家屋とも一律4%ですが、令和6年3月31日までは上記の軽減税率が適用されます。
他にも、家屋(住宅)に関しては住宅が一定の条件を満たすと評価額から一定額の控除が可能です。
▼軽減措置が受けられる建物の要件のポイント
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの
※要件の詳しい内容については所轄の自治体にご確認ください。
控除金額に関しては以下のとおりです。
| 新築日 | 控除額※ |
| 1997年4月1日以降 | 1200万円 |
| 1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
| 1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
| 1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
| 1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
| 1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
| 1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
不動産取得税がかからないケース
土地や家屋の課税標準額が低い場合は不動産取得税が課税されません。
不動産取得税が課税されないケースは以下のとおりです。
| 区分 | 課税標準となるべき額 |
| 土地 | 10万円未満の場合 |
| 家屋(新築、増築、改築によるもの) | 1戸につき23万円未満の場合 |
| 家屋(売買、交換、贈与等によるもの) | 1戸につき12万円未満の場合 |
又、一定の条件で取得した土地や家屋においても課税されないケースがあります。
・相続により不動産を取得した場合
・宗教法人が、その法人の本来の用に供するために不動産を取得した場合
・学校法人が、直接保育又は教育の用に供するために不動産を取得した場合
・公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 等
参考:大阪府「不動産取得税」
消費税

不動産の購入において、土地は非課税ですが建物は消費税の課税対象です。
消費税は提供される物やサービスに対して課せられる税金なので、不動産の場合は建物のみに消費税が適用されます。一方で、土地は消費される対象ではないということから非課税となっています。
不動産購入時の消費税
不動産購入時の消費税は、購入する不動産の土地と建物を案分して別々で計算します。
例えば、土地が1,000万円、建物2,000万円を購入する場合、建物は消費税10%加算されて2,200万円となり、合計で3,200万円を支払う必要があります。
ほとんどの販売資料は価格を税込みで記載していますが、税抜き価格を記載しているケースもあるので購入時には注意しましょう。
非課税になるケース
中古物件で個人が売主の場合は、消費税は非課税です。
ただし、売主が事業者である場合は中古物件でも消費税の課税対象となります。
他にも、個人において前々年の課税売上が1,000万円を超えている場合は課税業者となるので消費税が課せられます。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
不動産購入時に利用できる特例

不動産購入時には、住宅ローン控除や所得税控除などが利用できます。
所得税などの税負担を減らすことができるので有効に活用しましょう。
2022年には住宅ローンの控除率が1%から0.7%への変更や2024年、2025年に新築に入居する場合は省エネ基準を満たさないと住宅ローン控除が受けられないなどの改正も多いので、利用時には適用される条件について必ず確認しましょう。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、一定の条件を満たすと住宅ローン利用者の所得税を控除するための制度です。
住宅ローン残高の0.7%を原則として最大13年間所得税を控除することができます。
購入する物件の種類や住宅性能によって借入限度額や最大控除額が異なります。
購入前には、購入したい物件がどの条件に当てはまるのかを確認しておくことが重要です。
住宅ローンを受けるために必要な条件は以下の通りになります。
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・自身が居住していること
・床面積が50㎡以上あること
・居住用割合が1/2以上あること
・合計所得金額が2,000万円以下であること
※一部例外がありますので詳しくは国土交通省のHPでご確認ください。
①既存住宅の場合の控除
| 住宅性能 | 入居開始年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
| 1年間 | 合計 | |||||
| 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 2022年~ 2025年 | 3000万円 | 0.7% | 13年間 | 21万円 | 210万円 |
| その他の住宅 | 2000万円 | 14万円 | 140万円 | |||
| リフォーム(増改築等) | 2000万円 | 14万円 | 140万円 | |||
参考:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
②新築住宅・買取再販住宅の場合の控除
| 住宅性能 | 入居開始年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
| 1年間 | 合計 | |||||
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 2022年~ 2023年 | 5000万円 | 0.7% | 13年間 | 35万円 | 350万円 |
| 2024年~ 2025年 | 4500万円 | 31.5万円 | 315万円 | |||
| ZEH水準 省エネ住宅 | 2022年~ 2023年 | 4500万円 | 31.5万円 | 315万円 | ||
| 2024年~ 2025年 | 3500万円 | 24.8万円 | 248万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 2022年~ 2023年 | 4000万円 | 28万円 | 280万円 | ||
| 2024年~ 2025年 | 3000万円 | 21万円 | 210万円 | |||
| その他の住宅 | 2022年~ 2023年 | 3000万円 | 21万円 | 210万円 | ||
| 2024年~ 2025年 | 控除適用なし | |||||
参考:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
所得税の特別控除

認定住宅の購入や新築、居住用家屋のバリアフリー改修工事等を行った場合には、所得税の特別控除を受けることが可能です。認定住宅の条件や計算方法について見ていきましょう。
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅を購入、新築する場合は所得税の特別控除を受けることができます。>
認定長期優良住宅は、期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けた住宅、認定低炭素住宅は、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)の認定を受けた住宅のことです。
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に認定住宅の新築や購入をし、新築または購入の日から6ヶ月以内に住み始めた場合適応されます。
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に認定住宅の新築または購入をし、新築または購入の日から6カ月以内に住み始めた場合に適用されます。
参考:国税庁「No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」
控除額(65万円が限度) = 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(最大650万円が限度) × 10%
バリアフリー改修工事等
居住用家屋をバリアフリー改修工事大規模修繕および省エネ改修工事等をした場合にも所得税の特別控除を受けることができます。
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定の高齢者等がマイホームのバリアフリー改修工事を行い、改修工事等の日から6カ月以内にそのマイホームに住み始めた時に適用されます。
控除額(20万円が限度) = バリアフリー改修工事等の標準的な費用の額(補助金等の額はのぞく)(最大200万円が限度) × 10%
住宅特定改修特別税額控除における控除額は、バリアフリーリフォームの標準的な費用の額(最高200万円)の10%で、算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てられます。
ただし、限度額200万円は10%の消費税額などが含まれている場合なので、それ以外の場合は標準的な費用額である150万円が限度額となります。
参考:国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
不動産購入時の税金を軽減したいなら確定申告をしよう

不動産購入時の特例を使って税金を軽減するためには確定申告をする必要があります。
確定申告というと面倒だと感じる人も多いと思いますが、住宅ローン控除については、サラリーマンだと初年度だけ確定申告すれば2年目以降は会社の年末調整で対応可能です。
面倒な場合は税理士に依頼することもできますが、最寄りの税務署でも丁寧に教えてくれるのでまずは自分でトライしてみましょう。
さいごに
今回は、不動産購入時にかかる税金について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
人生において大きな買い物のひとつであるマイホームの購入においては、どの程度費用や税金がかかるかが心配な人も多いでしょう。
不動産購入時にかかる税金は購入資金とは別に準備する必要があるので、購入前にきちんと確認しておくことが重要だということがわかりました。
不動産の購入にかかる税金は、印紙税、不動産取得税、登録免許時、消費税と4つだけなのでそれほど難しくないと思います。
ただし、不動産取得税など忘れたころにまとまった資金が必要になるので忘れないように注意しましょう。
マイホームの購入の際には、住宅ローン控除や所得税の特別控除が活用できるので、自分が購入する物件がどの条件にあてはまるかをきちんと確認しておく必要があります。
購入前に費用や税金がどれくらい必要かをシミュレーションしておくと購入後の資金計画も安心です。
是非この記事を参考に不動産購入時の税金についての知識を身につけてください!
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。