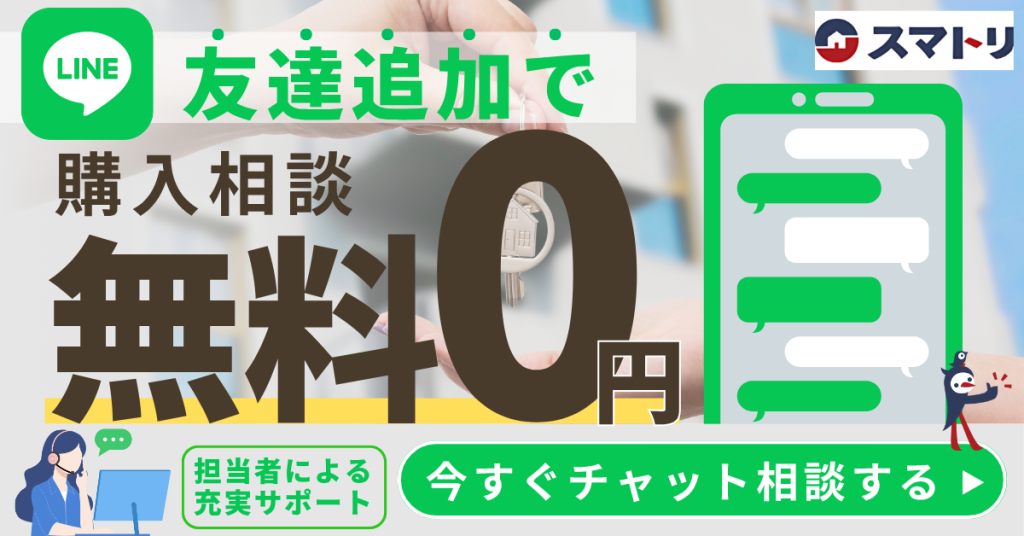不動産購入にかかる10の諸費用とは?安くするポイントや注意点を解説
仕事や生活環境の変化を機に不動産の購入を検討される方も多いのではないでしょうか。
しかし、現金をいつまでにいくら用意しなければいけないのか、全部でどのぐらいの費用がかかるのか、わからないと不安になるのではないでしょうか。
事前にどのタイミングで、どのぐらいの費用がかかるのかを把握しておくことで、思わぬ出費に慌ててお金を用意することもなくなるので、心にゆとりをもって安心して大きな買い物に挑むことができます。
この記事では、不動産を購入する際にかかる費用を段階ごとにまとめてご紹介しているので、不動産の購入の諸費用についての情報収集にお役立ていただければ幸いです。
目次
不動産購入の際にはあらかじめかかる費用を把握しておく

不動産を購入する時にかかるのは物件自体の費用だけではありません。仲介手数料や司法書士への依頼料、税金等様々な諸費用がかかります。
金銭が大きく動くタイミングは大きく「契約時」「決済時」「決済後」の3つに分けられます。
物件の代金が決まっていれば、事前にいくらぐらい現金を用意しておけばいいのかがわかりますので、しっかり計算しておくことで無用なトラブルを避けることにつながります。ここでは、何にどのくらいの金額がかかるのかの全容と金額のシミュレーションをしていきたいと思います。
株式会社不動産経済研究所が発表した首都圏 新築分譲マンション市場動向によると、発売は 1,006 戸、3.5%増と昨年 10 月以来の増加という結果になりました。
マンション購入を検討する方が増加するなか、諸費用について気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産購入の際に諸費用がかかる10の項目
この後、各項目で詳しく解説していきますが、まずは全体でどのような費用がかかるのかを一覧の表でご覧ください。
| 時期 | 諸費用 | 内容・特徴 |
| 契約時 | 仲介手数料半額 | 不動産会社へ仲介を依頼した場合に発生する費用です。 契約時にはまだ物件の引き渡しが終わっていないので多くの場合は半額を契約時に支払います。 |
| 印紙税 | 売買契約書や住宅ローン契約書に貼る印紙代金です。物件の価格によって印紙の価格は変動します。200円~60万円まで印紙の種類がありますが、大抵の場合は5,000円~2万円の間で収まります。 | |
| 手付金 | 手付金は物件の一部に充当する代金を支払うことで、売主買主に違約や解約が生じた際の保証を行うためにあります。 一般的に物件代金の5%~10%で、上限は20%です。 | |
| 決済時 | 頭金 | 頭金は住宅ローンで受ける融資以外の物件代金のことを差し、自己資金で準備する物件代金のことです。 |
| 登録免許税 | 不動産登記をする際に支払う税金です。物件代金が基になるのではなく固定資産税課税標準額がもとになります。 1月1日付けの所有者の元に固定資産税の納税通知書が送られているので、納税通知書から確認が可能です。 | |
| 司法書士への報酬 | 表題登記や所有権移転登記、抵当権の設定の登記を代行してくれる費用です。 相場は10万円~20万円ほど見ておくと良いです。 | |
| 住宅ローンの融資手数料 | 金融機関によって金額や方法は様々ですが、事務手数料や取引手数料の名目で金融機関に一括で支払う必要があります。 | |
| 住宅ローンの保証料 | 借入金額に応じて金融機関へ支払う保証料です。融資手数料がない場合は保証料として、金融機関への一括の支払いが必要です。 | |
| 火災保険・地震保険 | 購入物件にかける保険で、保険会社やプランによって金額が異なりますので調べておく必要があります。 | |
| 仲介手数料残額 | 決済時に仲介手数料の残額、通常の場合は半額を支払います。 | |
| 決済後 | 不動産取得税 | 不動産を取得した人が一度だけ支払う税金です。物件の売買代金ではなく、固定資産税課税標準額から算出され、通常は4%が税率になります。 |
| 管理費・修繕積立金 | マンション等の集合住宅を購入した際にマンションの管理会社に支払う諸費用です。 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 1月1日に固定資産を所有している人に課せられる地方税で一括か4期ごとに支払うか選ぶことができます。この地方税はマンションでも戸建てでも課せられます。 | |
| 引っ越し費用 | 購入物件に引っ越しをする為の諸費用です。 | |
| 水道加入負担金 | 水道局に支払う水道の新設や水道の口径を増やす為に使われる負担金です。自治体によって負担金額が異なりますので確認が必要です。 |
思っていたよりも項目が多かったと感じた方もいらっしゃる方もいるかもしれません。言葉だけで説明があっても具体的にどれくらいの金額がかかるか想像つかないという方は多いでしょう。そんな方のために、実際の数字を当てはめて諸費用を解説していきます。
費用の目安・シミュレーション
まずは例として数字を当てはめて、実際どれくらいの金額がかかるのか想定してみたいと思います。あくまでも想定なので、購入する物件や、使う金融機関等によって大幅に金額が変わってきます。
皆様がイメージしやすいようにこのような説明方式をとっていますが、同じ物件の料金でも必ずしも同じになるとは限らないので、参考程度にお考えください。
▼下記の表は【27,800,000円】の物件を購入する際の諸費用の目安金額になります。
| 条件 | |
| 物件代金 | 27,800,000円 |
| マンションファミリータイプ | |
| 鉄筋コンクリート造 | |
| 築年数 | 13年 |
| 固定資産税課税標準額 (土地・家屋合計) | 7,859,000円 |
| 都市計画税課税標準額 (土地・家屋合計) | 8,807,000円 |
| 融資金額 (頭金なし・返済期間35年) | 30,000,000円 |
| 司法書士利用 | |
| 不動産会社の仲介利用 | |
| 火災保険・地震保険加入 | |
| 諸費用 | |
| 仲介手数料(3%+6万円) | 983,400円(税込) |
| 収入印紙税 (売買契約書・金銭消費貸借契約書) | 40,000円 |
| 手付金 (10%/物件代金に充当) | 2,780,000円 |
| 登録免許税 | 157,180円 |
| 司法書士への報酬 | 200,000円(税込) |
| 住宅ローンの保証料 | 660,000円(税込) |
| 火災保険・地震保険加入 | 250,000円(税込) |
| 不動産取得税 (標準税率4%/軽減措置なし) | 314,360円 |
| 管理費・修繕積立金 | 32,0000円 |
| 固定資産税・都市計画税 | 136,400円 |
| 引っ越し費用 | 150,000円 |
| 水道加入負担金 | 150,000円 |
購入・契約時にかかる諸費用

金銭の動くタイミングの最初のフェーズに「契約時」があります。
購入する物件を決めて売買契約を交わす段階です。まだ、融資も通っていない状態なので、自己資金で用意しなくてはなりません。
大抵の場合は、売買契約に移る前にいくら必要なのかは事前に把握できますので、売買契約当日ではなく事前に準備しておくと無用なトラブルを避けることが可能です。
仲介手数料の半額
不動産会社へ仲介を依頼した場合に発生する費用です。
契約時にはまだ物件の引き渡しが終わっていないので多くの場合は半額を契約時に支払い、残額を決済時に支払います。
自己資金で準備する金額のうち、大部分を占めるのがこの仲介手数料です。
仲介手数料の上限金額は法律で決まっており、物件の代金によって変わります。
200万円以下 5%
200万円超400万円以下 4%+2万円
400万円超 3%+6万円
自身が購入検討している物件に照らし合わせて計算して仲介手数料を算出してみましょう。
印紙税
不動産の売買契約書や、住宅ローンの契約書である、金銭消費貸借契約書には印紙税が課されます。
物件の代金によって貼る印紙の金額が異なりますので注意が必要です。
| 金額 | 印紙税額 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
他にも建設工事請負契約書にも印紙がかかりますので、新築する場合には覚えておきましょう。
手付金
手付金は、一般的に物件代金の5%~10%で、上限は20%と決まっています。
よく頭金と勘違いされますが、頭金はあくまで住宅ローンを組む際の物であり、この手付金とは別の物です。
手付金は物件の一部に充当する代金を支払うことで、売主買主に違約や解約が生じた際の保証を行うためにあります。
通常売買契約書には、「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」という文言が入ります。
売買契約書を交わした後に、買主が買うのをやめた場合は手付金が違約金として返ってきません。逆に売主が売るのをやめた場合は、手付金を返したうえで、手付金と同じ額を違約金として買主に支払うことになるという内容です。
手付金の存在により解約をしにくくするという効果があります。手付金がゼロの契約も可能ですが、簡単に解約されてしまうリスクがある事は覚えておきましょう。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
不動産の購入の決済・引き渡しにかかる諸費用

次の金銭が大きく動くフェーズが「決済時」です。
決済時は物件代金を全額支払い、所有権を移転させる段階になります。物件代金を全額支払うだけではなく、金融機関へ手数料を支払ったり、司法書士に登記をお願いしたりと諸費用がかかってきますのでしっかりと把握しておきましょう。
頭金
手付金と混同しやすいですが、ここでいう頭金は住宅ローンで受ける融資以外の物件代金のことを差し、自己資金で準備する物件代金のことです。
金融機関によっては頭金を準備しなくても融資を組んでくれる場合もあります。
初期費用で自己資金を準備しなくて済むのは最大のメリットですが、デメリットもあります。
何らかの事情でローンの返済が難しくなった時に売却額よりも残債の方が多くなってしまい、競売や任意売却をしなければならなくなる可能性がある点は注意が必要です。
登録免許税
不動産登記をする際に支払う税金のことを指します。
物件代金が基になるのではなく固定資産税課税標準額がもとになります。
1月1日付けの所有者の基に固定資産税の納税通知書が送られているので、納税通知書から固定資産税課税標準額の確認が可能です。固定資産税課税標準額に決まった税率をかけることで登録免許税の金額が決まります。
| 登記の登録 | 税率 |
| 土地の所有権の移転(売買) | 2% |
| 土地の所有権の移転(相続) | 0.4% |
| 住宅の所有権の移転(新築) | 0.4% |
| 住宅の所有権の移転(中古) | 2% |
| 住宅の所有権の移転(相続) | 0.4% |
| 抵当権の設定(住宅ローンを組む場合) | 0.4% |
住宅ローンを組む場合に抵当権の設定の登記は融資額に税率をかけて計算します。
なので、住宅ローンを組んで土地付きの住宅を購入する場合は、「土地の登記」「建物の登記」「抵当権の登記」の3つの登録免許税と支払うことになります。
軽減税率の措置を受けられる場合がありますので、自分が当てはまるのか国税庁のHPを確認してみてください。
司法書士への報酬
登記に関して司法書士に支払う費用です。
依頼する司法書士事務所によって費用は変わりますが、一般的に相場は10万円~20万円ほど見ておくと良いです。
どこまでお願いするかによっても金額は変わりますが、主に所有権の移転登記、抵当権設定登記、決済の立会業務費用等があります。
不動産会社が仲介に入る場合には不動産会社指定の司法書士がいる場合があります。
売主買主双方で司法書士を準備すると費用も無駄にかかりますので、その場合は指定の司法書士に任せましょう。
住宅ローンの融資手数料
金融機関によって金額や方法は様々ですが、事務手数料や取引手数料の名目で金融機関に一括で支払う必要があります。
金融機関によって、融資手数料か住宅ローンの保証料のどちらかを支払います。
融資を受ける際に自己資金として準備しておくのが通常ですが、金融機関によっては、融資手数料を融資金額にまとめて組んでもらえる場合があります。
その場合は自己資金で準備をする必要がありませんが、手数料が高額な場合はローンの支払いが高くなるので、返済について負担になりますので、検討が必要です。
金融機関によっては一律で55,000円という所もありますので、まずは手数料や金利が低い金融機関に与信をお願いしてみるのがおすすめです。
住宅ローンの保証料
借入金額に応じて金融機関へ支払う保証料です。融資手数料がない場合は保証料として、金融機関への一括の支払いが必要です。
保証料は融資を受ける期間が長くなるほど率が上がります。
支払い方は大きく分けて2通りで、前払いとして一括で支払う場合と、金利に上乗せて毎月の返済額として支払う方法があります。
金利上乗せの場合は一般的に0.2%~0.7%となっていることが多いようです。
火災保険・地震保険料
購入物件にかける保険で、保険会社やプランによって金額が異なりますので調べておく必要があります。
火災保険は多くの場合、建物の構造でプランが変わり、強固であればあるほど保険料は安くなります。
地域によっても金額は変わります。乾燥しやすく火事が起きやすい場所は火災保険料が若干高くなる傾向にあるようです。
地震保険は、所在地、構造、耐震診断を受けているか等で金額は変わってきますが、国と民間の保険会社が共同で運営している保険なので、保険会社によって金額の設定が変わるということはありません。
地震による危険が多い地域なのか、構造が木造なのか鉄筋コンクリート造なのか、構造が強固であれば当然保険料も安くなりますし、耐震診断を受け問題がなければ安くなる場合もあります。
火災保険も地震保険も絶対に入らなければならないわけではありませんが、万が一のことを考えて、加入しておくことが無難でしょう。地震保険は各社同じ金額となっていますが、火災保険は各社様々なプランがあり、金額も異なりますので、比較検討しましょう。
仲介手数料の残額
決済のタイミングで、売買契約時に払った半額の仲介手数料の残額を支払います。
これは自己資金で準備しなくてはなりません。
他の諸費用がたくさんあるので忘れがちですが、金額の大きなものなのでしっかり準備しておきましょう。
不動産購入の決済後にかかる諸費用

金銭が動く最後のフェーズの「決済後」には、不動産取得税や固定資産税・都市計画税等の税金や、維持管理に必要な管理費・修繕積立金等がかかります。
物件の購入が終わった後で、自己資金を準備しなくてはならないのは意外と抜けてしまいがちです。どのぐらいの諸費用がかかってくるかをあらかじめ頭に入れておくことで慌てることもなくなるのでしっかり把握しておきましょう。
不動産取得税
不動産を取得した人が最初に一度だけ支払う税金で地方税に該当します。
課税されるのは物件の売買代金ではなく、固定資産税課税標準額から算出され、通常は4%が税率になります。
相続の場合以外の、贈与、購入、新築等が課税対象になります。
一定の条件を満たすと軽減措置の対象になりますので、都道府県のHPより「不動産取得税 軽減措置」で調べてご確認ください。
戸建て購入の場合にかかる諸費用
決済後に戸建ての場合にかかる費用として、固定資産税・都市計画税があります。1月1日に所有している人に納税通知書が送られてくるので納税の義務があります。
1月1日以外の日付で物件を購入した場合には売主と日割り清算するので、実質翌年から届く納税通知書での支払いが始まります。
一括で年間分を支払う方法と4期に分けて支払う方法があります。
計算の方法は、固定資産税課税標準額に税率をかけて算出します。
標準の税率は1.4%の地域が多いですが、中には1.5%や1.6%等、地方によって税率が変わりますので確認が必要です。
戸建ての場合は、マンションと違い管理費や修繕積立金はかかりませんが、建物は経年劣化していくものなので、突然の修繕が必要になった場合の為の積立金は自分で金額を決めて確保しておくのがおすすめです。
マンション購入の場合にかかる諸費用
戸建てで説明した固定資産税・都市計画税の他に管理会社に支払う管理費と修繕積立金が別途かかります。
集合住宅では複数の住人が住んでいる為、トラブル等を防ぐ目的や、物件の維持をする目的で建物管理会社に管理を依頼している場合が一般的です。
管理を委託している場合、管理会社の報酬として管理費を支払い、建物の大規模修繕の為の貯蓄として修繕積立金を住人全体で積み立てます。
管理費も修繕積立金も平米数に応じて決まることが多く、1階も10階も平米数が同じであれば同じ金額を納めるのが一般的です。
引っ越し費用
物件を購入する代金が大きいので忘れがちですが、引っ越しによる家具の移動費用も忘れてはならない諸費用の一つです。
なるべく費用を抑えるためにも、複数の引っ越し業者から相見積もりをすることをおすすめします。
自己資金になりますので、事前にどの程度の金額がかかるのかを把握しておきましょう。
水道加入負担金
水道局に支払う水道の新設や水道の口径を増やす為に使われる負担金です。
もうすでに水道が引いてある物件を購入しても支払わなくてはならないの?と不思議に思われる方もいるかもしれませんが、地域によって取り決めがあった場合にはたとえ引き込みが思っていたとしても支払う必要があります。
また、自治体によって負担金額が異なりますので確認が必要です。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
不動産購入の諸費用を安くするコツ
不動産購入にかかる諸費用は、物件価格の約6〜10%にのぼることもあり、家計への影響は大きなものです。
しかし、これらの費用には見直しや工夫の余地がある項目も含まれています。
適切な時期の選定や業者の選び方によって、数十万円単位でのコスト削減も可能です。
ここでは、実際に活用できる「諸費用を安くするための具体的なポイント」をご紹介します。
引っ越しの時期を工夫して費用を抑える
引っ越し費用は、同じ距離や荷物量でも時期によって大きく変動します。
特に3〜4月の繁忙期は、進学・転勤シーズンと重なるため料金が高騰しやすく、通常期の1.5〜2倍になることも想定しておくべきでしょう。
一方で、6月や11月などの閑散期は価格が下がりやすく、柔軟な日程調整ができればさらに安くなるケースもあります。
また、土日祝日や月末は混み合いやすいため、平日や月初を狙うのも効果的です。
引っ越し業者の一括見積もりサービスを活用し、複数社を比較することで、最適な料金とサービスを見極められます。
仲介手数料を割引できる会社を選ぶ
不動産会社への仲介手数料は「物件価格の3%+6万円」が一般的な上限ですが、必ずしもこの金額が固定ではありません。
現在では「仲介手数料無料」や「割引あり」を掲げる不動産会社も多く、特に自社で売主から直接依頼を受けている物件の場合、買主からの手数料を取らないケースもあります。
ただし、安さだけで業者を選ぶと対応の質にばらつきがあるため注意が必要です。
信頼性とコストパフォーマンスのバランスを見極めながら、複数社を比較して選ぶことが大切になるでしょう。
不要なオプションや火災保険を見直す
不動産購入時には、火災保険や住宅オプションなどの選択肢が提示されることが多くありますが、すべてをそのまま採用すると費用がかさみます。
たとえば、照明やエアコン、カーテンレールなどの設置オプションは、別途購入・設置した方が安く済む場合もあります。
また、火災保険も内容と保険会社によって大きく保険料が異なる点にも注意が必要です。
補償内容を過剰にしすぎず、自分の暮らしに本当に必要な内容だけを選ぶことで、無駄な支出をカットすることができます。
不動産購入にかかる諸費用に関してのQ&A
不動産購入にかかる諸費用について主だった質問に回答していきます。専門的な知識がないと疑問がたくさん出てきますし、不安に思う事も多いと思います。諸費用を抑えるコツも解説していきますので参考にしてみてください。
Q.新築・中古の物件購入で諸費用は変わってきますか?
A.新築と中古の物件購入でかかる諸費用は変わってきます。一般的に新築の方が、諸費用は抑えられる傾向にあります。
諸費用の差が出る一番の要因は、不動産取得税や登録免許税などの税金です。
新築の場合は軽減措置が使える場合が多いので活用することで諸費用を抑えることができます。
また、新築の場合は多くの場合、売主が不動産会社になっている場合が多いので仲介手数料がかからない点も新築の方が諸費用を抑えられる要因になっています。
ただし物件にもよりますが、そもそも物件代金の金額が新築と中古で大きく異なりますので、住宅ローンの返済額を考えて新築にするか中古にするか検討しましょう。
Q.諸費用を現金で用意できない場合はどうしたら良いですか?
A. 相談次第で対応可能な場合もあります。
自己資金の必要がある諸費用の中で大部分を占めているのが、主に4つで、①手付金、②仲介手数料、③頭金、④住宅ローンの手数料・保証料です。
①手付金は上限20%となっていますが、売主買主の同意があればゼロでの契約も可能です。売主からの一方的な解約のリスクがあるのであまりおすすめできませんが、手付金の割合を低くできないか相談することで自己資金を押さえられます。
②仲介手数料はかなり大きな金額になりますが、必ず自己資金で準備しなくてはなりません。不動産会社の収入になる部分なので、基本的に融通を利かせてくれることは少ないと考えておくほうが良いでしょう。
稀に相談次第で割賦での支払いも了承してくれる不動産会社もありますので、どうしても自己資金が準備できない場合は相談してみましょう。
③、④の金融機関に支払う頭金や手数料・保証料に関しては、利用する金融機関にもよりますが、頭金なしで手数料・保証料を融資金額に含めてくれるケースがあります。
その場合、利息が高くなるケースがあることと、物件代金全額+手数料・保証料の月々の返済額が高くなりますので、無理がないかどうかをしっかり検討しましょう。
万が一手放さなければならなくなった時に首が回らなくなる可能性があることは考慮しましょう。
Q.諸費用をなるべく節約したいです。節約することは可能ですか?
A. 物件価格を下げられれば、仲介手数料や融資の手数料・保証料も下げることができます。
諸費用を少しでも節約したいのであれば、①物件代金、②司法書士への報酬、③火災保険・地震保険、④仲介手数料をなくす、の4点があります。
意外と見落としがちなのが物件の購入代金の交渉です。
不動産の売買において売り出されている金額で購入しなくてはならないと考えている方も多いかもしれませんがそんなことはありません。
不動産は明確な金額が定まっているわけではなく、ある程度利益を考えて売り出されているものです。
そのままの金額ではなく、ある程度の交渉には乗ってくれる場合が多いので覚えておきましょう。
物件価格を下げられれば、仲介手数料や融資の手数料・保証料も下げることができますので、諸費用も抑えられます。
また、司法書士への報酬という点では、司法書士を使わなければならないという法的制限はありません。そのため費用を抑えるために自分でも登記申請を行うことはできます。
自分で行う場合はミスが大きなトラブルにつながりますので、事前にしっかりと登記に必要な知識は学んでおきましょう。
火災保険・地震保険については各社プランがありますので、必要なものだけにしておくことで、諸費用を抑えることができます。火災保険に関しては会社によって金額が異なりますので、しっかり相見積もりを取って見比べて金額を抑えましょう。
仲介手数料は自己資金で必ず用意しなくてはならない上に、購入に際しての諸費用で大部分を占めています。
仲介を利用しないと不安という方もいらっしゃると思いますが、弊社が運営する「スマトリ」は売り手と買い手を繋ぐ場所として、個人間売買をサポートするプラットフォームです。
スマトリの形式は個人間売買になるので、仲介手数料は一切かかりません。「個人でできるか不安」といった方には不動産取引の専門家と提携したオプションが様々用意されているので、自分の必要な分だけオプションを選択し利用することが可能です。
費用を抑えてスマートに取引できる新しい不動産の購入方法がスマトリです。是非この機会に視野に入れてみてください。
まとめ
不動産購入時にかかる諸費用について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
意外にも不動産の購入に際しての諸費用は高額な自己資金が必要な場合があります。不動産の物件価格と仲介手数料は理解していても、税金等は頭から抜けている方もいらっしゃったのではないでしょうか。
仲介手数料だけではなく、税金の諸費用や、金融機関を利用する際の諸費用をしっかり計算しておくことで後になって驚くような金額を支払わなければならないという事態を防ぐことができます。
どの程度の自己資金が準備できるのかを把握したうえで、購入後に無理のない物件の購入を検討しましょう。
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。