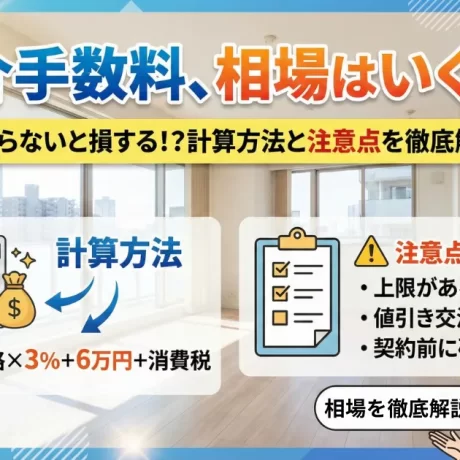契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや期間制限を解説
「契約不適合責任は瑕疵担保責任と何が変わったの?」「売主が買主に対して責任を負うケースを知りたい」など、契約不適合責任について詳しく知りたいという方もおられるのではないでしょうか。
契約不適合責任とは、「売主が引き渡した目的物の契約内容の不備を負担する責任」のことです。
改正前は、瑕疵担保責任として運用されていましたが、2020年4月の民法改正で契約不適合責任に名称が変わって新たに運用されています。
不動産の売買における契約不適合責任には、購入後の雨漏りや不動産沈下による建物の傾きなどがありますが、契約不適合責任には責任を追及できる期間に期限があるので引渡し後に契約不適合がないかを早めにチェックすることが重要です。
ほかにも、契約不適合責任で請求できる権利や免責事項と合わせて売買契約時に確認しましょう。
今回の記事では、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い、買主が請求できる権利や免責事項について解説します。
これから不動産の購入を予定している人は、是非最後までこの記事を読んでいただければと思います。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買契約などで引き渡された物が、契約で定められた内容と一致していない場合に、売主が買主に対して負う法的責任を指します。
具体的には、種類や品質、数量などが契約と異なるときに問題となるケースが多数です。
たとえば、注文した商品が破損していた、数量が足りなかった、あるいは契約で示された性能を満たしていない場合などが該当します。
この契約不適合責任は、主に売買契約に適用されますが、民法の規定により、請負契約などの他の有償契約にも準用される場合があります。契約に基づいた適切な履行が求められる現代の取引において欠かせない規定といえるでしょう。
参考:e-Gov
契約不適合責任の定義
契約不適合責任とは「売買契約の内容に適合しない目的物を引き渡した際に、売主が買主に負う責任」のことです。
民法の中でも1896年に制定されて以降改正されていなかった債権関係の規定を中心に、2020年に民法が改正の際に瑕疵担保責任の名称が廃止されて契約不適合責任に名称が変更されました。
契約不適合責任においては、契約後に引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主が売主に対して目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しなどの請求ができます。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
| 契約不適合責任 | 瑕疵担保責任 | |
| 対象物 | 特定物だけでなく不特定物も対象 | 特定物のみ |
| 基本的な考え方 | 契約責任説 | 法定責任説 |
| 救済手段 | 履行の追完 代金減額請求 解除 損害賠償請求 | 損害賠償請求 解除 |
| 買主の善意無過失 | 不要 | 必要 |
| 損害賠償における売主の故意過失 | 必要 | 不要 |
| 損害賠償の範囲 | 信頼利益だけではなく履行利益までが範囲 | 信頼利益のみが範囲 |
| 期間制限 | 契約不適合に気づいてから1年以内に通知 | 瑕疵に気づいてから1年以内に責任 |
契約不適合責任と瑕疵担保責任の一番の違いは、法定責任説から契約責任説に変更されたことです。
瑕疵担保責任は法定責任説が採用されており、売買契約後に売主から告知のなかった瑕疵(隠れた不備)が見つかった場合に、損害賠償請求権と解除権を行使できます。
しかし、一般の債務不履行において認められる追完請求権や代金減額請求権が含まれていませんでした。
そこで、契約不適合責任では契約責任説を採用することにより、不備のあるまま目的物が引き渡された場合は債務不履行の状態であるという考えのもとで「追完請求権」や「代金減額請求権」も認められるように変更されたというわけです。
また、瑕疵担保責任では売主から告知されていない雨漏りなどの隠れた瑕疵が主な適用対象でしたが、契約不適合責任では雨漏りはもちろんのこと、土地の面積が違う、物件の購入後に不同沈下(※1)で建物が傾いたといったケースも適応対象になるなど範囲が拡大しています。
※1:不同沈下…軟弱な地盤に建てられた建物が傾いて不ぞろいに沈下することを指す
契約不適合責任を買主が追及できる期間
契約不適合責任には、民法において買主が追及できる期間が設けられています。
追求できる期間については、宅建業者、一般消費者など売主と買主がどういった立場にあるかによって期間が
変わる点には注意が必要です。
一般的な取引の場合
契約不適合責任を買主が追求できる期間のことを排斥期間と言います。
契約適合責任の排斥期間は、「不具合を知ったときから1年以内」に不具合の内容を売主に通知する必要があります。
ただし、この期間はあくまで民法上の決まりなので契約の内容によって行使期間を長くすることも短くすることは可能です。
また、
契約不適合責任には消滅時効があり、買主が契約不適合を知ったときから5年以内、もしくは目的物の引渡しから10年以内に売主に通知しないと契約不適合を理由とする買主の権利は消滅します。
買主が一般消費者の場合
不動産の売買契約において、一般消費者同士の売買の場合は、契約不適合責任を買主が追及できる期間を3カ月としていることが多いです。
しかし、不動産の売買契約の場合は売主が宅建業者になることもあります。
売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合は、宅建業法第40条において、契約不適合が存在することを通知する期間を目的物の引渡しから2年以上でなければならず、2年未満に限定する特約は無効です。
買主が業者の場合
買主が個人ではなく業者の場合は、民法よりも効力のある商法が適用されます。
商法における契約不適合責任の排斥期間については、「不具合を知ったときから6ヵ月以内」に不具合の内容を売主に通知する必要があります。
ただし、不動産取引においては、商法が適用されると買主である業者が不利になるので、買主は不動産売買契約に際して、商法を適用しない旨の条項を売買契約に入れることを要請することが多いです。
契約不適合責任の追及・請求方法
契約不適合が発覚した場合、買主が売主に対して請求できる権利は4つです。
契約不適合責任に変わったことで、瑕疵担保責任のときには請求できなかった「追完請求権」や「代金減額請求権」が追加されています。
契約不適合責任に基づいて買主が請求できる権利は特に重要なポイントとなるので詳しく解説します。
履行の追完請求
履行の追完請求権とは、引渡し後に引き渡された目的物が種類、品質または数量において契約の内容に適合しない(契約不適合である)ときに、買主が売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しを求めることができる権利です。
瑕疵担保責任では、買主は損害賠償か解除しかできませんでしたが、売主に対して目的物の修補や代替物の引渡しによって対応してもらうことができるようになりました。
不動産売買における履行の追完請求の例としては以下のようなものがあります。
・天井や窓などから雨漏りがしていた場合に雨漏りの修補請求する
・建物の取り壊しを行ったところ大きな基礎杭が出てきたので排除を請求する
・土地を購入後に土壌汚染が発覚したので土壌改良を請求する
代金減額請求
代金減額請求権とは、引渡し後に引き渡された目的物が種類、品質または数量において契約の内容に適合しない(契約不適合である)ときに、買主が売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しができない場合に代金の減額を請求できる権利です。
不動産取引においては、雨漏りの修補を請求したが売主にお金がなく、修補ができないので代金の減額で対応するといったケースが考えられます。
債務不履行による損害賠償請求
債務不履行による侵害賠償請求権とは、引渡し後に引き渡された目的物が種類、品質または数量において契約の内容に適合しない( 契約不適合である)ときに、売主に過失がある場合において損害賠償の請求ができる権利です。
不動産取引では、建物付きの土地の売買において不動産会社が転売目的で購入したものの、土壌汚染や埋設物が発見されたことによって予定金額で転売できない場合に損害賠償を請求されるケースが考えらえます。
債務不履行による契約解除
債務不履行による契約の解除とは、引渡し後に引き渡された目的物が種類、品質または数量において契約の内容に適合しない(契約不適合である)ときに、履行の追完を催告しても売主が相当期間内に対応しない場合には買主が契約を解除できる権利です。
軽微な契約不適合であれば履行の追完で対応するので渋滞な契約不適合でないと解除は認められません。
不動産取引では、新築物件を購入した際に建物の基礎部分に重大な欠陥が発覚したが修補が難しく、今後も住むことができないケースが考えられます。
契約不適合責任が認められた3つの事例
みなさんは不動産売買の経験も少なく、契約不適合にはどういった事例があるのかについてイメージしにくいと思います。
では、実際に契約不適合責任が認められた事例にはどういったものがあるのでしょうか。
ここでは契約不適合責任が認められた3つの事例 についてご紹介します。
経年劣化による雨漏りが発生
戸建ての売買で多いのは、購入後に建物の雨漏りが発見されるケースです。
特に築年数が古い木造の物件は、建物の経年劣化により建物が歪むなど雨漏りが発生しやすいので注意する必要があります。
(東京高判 平性31年1月16日)取引の概要 : 鉄筋コンクリート造5階建て、築22年の共同住宅の売買
売主の瑕疵担保責任負担期間 : 建物引渡し後3カ月
雨漏りの状況 : 建物引渡し2カ月後に5階の1室の入居者が退去したところ、買主は天井に染みを発見し、壁紙を剥がすと天井のコンクリート部分の湿りが確認できた。
当該雨漏りに対して買主は売主に瑕疵担保責任による修繕を請求したが、売主は、5階の入居者から雨漏りの苦情を聞いていなかったことから瑕疵にあたらないとして修繕に応じないと反論があった。
裁判所の判断では、今回の雨漏りについては屋上防水層の経年劣化によってコンクリート躯体に雨水が到達したもので、一定の期間をかけて徐々に雨水が浸透することを考えると建物引渡し前から雨漏りは存在したことが認められるということで契約不適合責任(当時は瑕疵担保責任)にあたるとされています。
不動産の売買契約書の契約不適合責任の条項には、雨漏りとシロアリの害、給排水管の故障などは契約不適合責任にあたるということで具体的に明示されているケースが多いです。
参考:Vol.20 雨漏りと売主の契約不適合(瑕疵)担保責任に関するトラブル(公益社団法人 全日本不動産協会)
不同沈下で建物が傾いている
物件の購入後に不同沈下によって建物が傾いていることが発見されるケースも多いです。
不同沈下とは、建物の重みによって地盤や建物が不ぞろいに沈んだりずれたりすることを指します。
(大阪地判平成15年11月26日)取引の概要 : 築7年の建物の売買
不同沈下の状況 :買主が売主から物件を購入したところ、不等沈下によって建物に約70分の1の勾配傾斜があることが判明し、買主が売主に契約不適合責任(当時の瑕疵担保責任)を追及した。
裁判所の判断では、建物の傾斜は経年劣化ではなく、地盤の不等沈下によるもの、この傾斜は築後の経年劣化によって通常は生じうるものではない、本件では、買主が傾斜を承知して物件を購入したわけではなく、売買代金も傾斜を反映していなかったという3点から契約不適合責任(当時は瑕疵担保責任)にあたるとされています。
契約不適合責任を追及するにあっては、買主が物件を購入するにあたって事前に傾きがあることを知っていたか、傾いている場合は価格に反映されていたかが重要なポイントです。
消防法違反の指摘が発覚した
土地や建物などの、不動産の売買契約後に消防法などの法律違反が判明するケースも多いです。
消防法では、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
消防署から指摘があった場合は是正計画書を提出して改善する必要があります。
(大阪地判平成22年3月3日)取引の概要 : 土地建物を1億9千5百万円で売買
不同沈下の状況 :買主が売主から物件を購入し、引渡し後に内装工事のために消防署に問合せたところ、引渡し前に売主に消防法違反の指摘があったことが判明した。
買主は売主に対して、媒介契約の善管注意義務違反による損害賠償請求を行った。
裁判所の判断では、売主は違反事実を知りながら告げていなかったので、瑕疵担保免除特約の適用には該当せず、消防法違反については瑕疵にあたるとされています。
媒介業者については、点検結果報告書以外に売主からの情報提供はなく、消防法違反を疑うべき状況もなかったので調査義務違反ではないとの判断です。
ただし、売買契約において契約不適合責任の免責を条項に記載していても、売主が契約不適合の事実を知りながら告げていない場合は免責にはならないということを知っておく必要があります。
参考:契約不適合責任に係るトラブルについて(住宅政策本部民間住宅部不動産業課)
免責特約の注意点
契約不適合責任においては、契約内容によっては売主の契約不適合責任が免責となるケースもあります。
ただし、契約不適合責任について免責の特約を条項に記載していても売主が法人などそれぞれの立場や条件によっては免責にならないケースも多いので注意しましょう。
特約は買主に不利な契約
契約不適合責任の免責特約は、買主にとって不利な契約です。
そのため、売主は免責特約を入れておけば何でも免責になるわけではなく、条件によっては無効になるケースがあります。
民法においては、売主が引渡し前に契約不適合を知っていたのに告知しない場合や売主が自ら第三者のために権利を設定、または第三者へ権利を譲渡することによって生じた契約不適合責任については免責特約が適用されません。
また、宅建業法や消費者契約法に違反するような契約不適合責任の免責特約はすべて無効です。
免責特約は買主の同意が必要
契約不適合責任の免責特約は、売主と買主双方の同意がある場合のみ有効になります。
契約不適合責任は、任意規定なので法律よりも売主と買主が取り決めた事項が優先されます。
物件が古い場合や買主が値下げ交渉をしている場合に契約不適合責任の免責特約が適用されるケースが多いです。
契約書に記載されている免責事項については基本的には無効にできません。
売主と買主双方が契約不適合責任の免責特約の内容について問題ないかを十分に確認した上で契約するようにしましょう。
免責特約の条件は異なる
売主が「個人」「宅建業者」「宅建業者以外の法人」によっても免責特約の条件が異なります。
「個人」「宅建業者」「宅建業者以外の法人」の場合は以下の条件にあてはまる場合は免責特約が無効になります。
個人
・引渡し前に契約不適合を知っていたのに告知しない場合
・売主が自ら第三者のために権利を設定、または第三者へ権利を譲渡することによって生じた契約不適合責任の場合
宅建業者
・引渡し前に契約不適合を知っていたのに告知しない場合
・売主が自ら第三者のために権利を設定、または第三者へ権利を譲渡することによって生じた契約不適合責任の場合
・宅建業法により引渡しの日から2年以上となる特約以外
(例えば、契約不適合責任を一切負わない、引渡しの日から1年とする場合などは無効)
宅建業者以外の法人
・引渡し前に契約不適合を知っていたのに告知しない場合
・売主が自ら第三者のために権利を設定、または第三者へ権利を譲渡することによって生じた契約不適合責任の場合
・消費者契約法により契約不適合責任を一切負わない、引渡しの日からすぐの免責特約の場合
(3か月の免責特約は無効として判例があり、一般的には1年程度に設定することが多い)
契約不適合責任は民法ですが、宅建業者は宅建業法、宅建業者以外の法人は消費者契約法が適用される点に注意が必要です。
買主が個人の場合は、宅建業者や宅建業者以外の法人の立場が強いとされることから買主保護のために民法よりも厳しい宅建業法や消費者契約法が優先されます。
免許特約が無効になるケースは、物件の売主によって異なることを覚えておきましょう。
終わりに
今回は、不動産の売買における契約不適合責任の期限や免責、瑕疵担保責任との違いなどについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
【中古マンションをお探しの方へ】
スマトリのLINE相談では、仲介手数料無料の物件を数多く紹介しており、物件によっては数百万円の費用を節約することができます。
無理に購入を勧めることはありませんので、ご自身の状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えましょう。
「少しでも初期費用を抑えて住まいを手に入れたい」「賢く中古マンションを購入したい」という方は、スマトリのサービスをチェックしてみてください。
\LINE登録者限定無料特典あり/
スマトリ公式LINEで無料相談する
一般の人にとっては、不動産の売買は取引の回数も少なく、契約不適合責任について知らないという人も多いと思います。
契約不適合責任は、不動産を購入した後に使える買主にとって重要な権利です。
特に中古物件の場合は、契約不適合責任の免責特約が適用されていることが多く、「購入後に給水管から水漏れがあった」「シロアリで床が腐食して困った」といったトラブルをよく耳にします。
免責特約を受け入れる場合は、想定されるリスクを考えて価格面も含めて総合的に判断する必要があります。
また、契約不適合責任については、期限が設けられているので、契約不適合の有無を早めに確認し、発見したらすぐに売主に通知することも重要なポイントです。
契約不適合責任について勉強したい、これから物件を購入しようと考えている人は、今回の記事を参考にしていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。