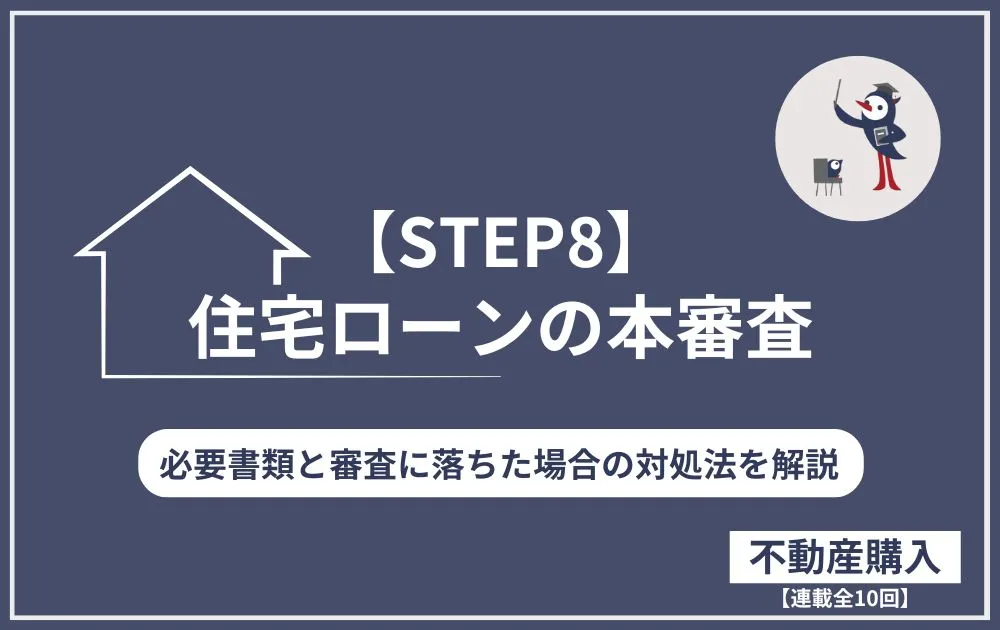ペアローンはやめた方が良い?夫婦におすすめの住宅ローンを解説
「ほしい物件がペアローンでないと買えない」「夫婦それぞれのローンで家を購入することを検討している」など、物件価格の高騰もあってペアローンを利用する人が増えています。
しかし、「一方が退職した場合にローンが残って返済の負担が増える」「夫婦が離ればなれになった際の対処が難しい」など、ペアローンはやめた方が良いという意見もあります。
ペアローンは、1つの物件に対して、夫婦や親子などの同一世帯の2人がそれぞれに個別でローンを組む方法です。
夫を主債務者として妻の収入を加える収入合算の場合、妻は連帯保証人となるだけですが、ペアローンの場合は、個別に返済を行い、お互いが連帯保証人となる必要があります。
収入合算と比べると借入金額が増える、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるのがペアローンのメリットです。
一方で収入合算よりも諸経費の負担が増える、贈与税が発生する場合があるといったデメリットがあります。
ペアローンで失敗しないためにも、メリットとデメリットを理解した上で利用することが重要です。
ペアローンでの物件購入を検討している人やペアローンのデメリットについて詳しく知りたいという人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。
目次
ペアローンはやめた方が良いといわれる理由

近年、共働きの世帯の増加、住宅価格の高騰、 正社員として働く女性の増加によって、ペアローンの利用者は増えています。
一方で、借入金の負担や離婚後の対応の難しさといった理由から、ペアローンにネガティブなイメージを持っている人もおられるでしょう。
まずは、ペアローンが敬遠されがちな理由について、リスクやデメリットを具体的に解説します。
どちらかが退職しても返済は続くから
ペアローンは、夫婦のそれぞれが主債務者として借入するのが特徴のローンです。
そのため、どちらかが退職して収入がなくなった場合でも住宅ローンの返済は続きます。
例えば、共働き世帯でペアローンを組む場合、子どもができて妻が働けなくなると一時的に返済額の負担が大きくなってしまいます。
ペアローンを組む場合は、一時的に返済額の負担が大きくなった場合に備えて、貯蓄などの余裕資金を持っておく、妻側の借入額を小さくしておくといった対策が必要です。
離婚した場合も返済義務が残るから
ペアローンは、夫婦が離婚した場合でも返済義務が継続します。
離婚した場合、自宅はどちらかが所有するか、売却して処分するかを検討する必要があります。
どちらかが所有する場合、所有する人がもう一人のローン残債を支払うか、借り換えをして新たにローンを組み直さないといけません。
しかし、実際にはローン残債を支払うほどの貯蓄を持っている人は少なく、借り換えもできないケースが多くあります。
また、売却して処分する場合、売却価格よりもローン残債が少なければ問題はありませんが、ローン残債が多いと売却してもローンの支払いが残ってしまいます。
ローンの返済義務が残ってしまうと、離婚後にどちらがローンを払うのかを解決できず、離婚協議が長引くケースも考えられるでしょう。
ペアローンの住宅控除のシミュレーション

では、実際にペアローンを組んだ場合、借入可能額や返済額はどれくらいになるのでしょうか。
事前にペアローンの借り入れをシミュレーションし、具体的な数字を把握しておくことが重要です。
ここでは、共働き世帯がペアローンを借り入れした場合に、住宅控除を受けた場合のシミュレーションしてみましょう。
【ペアローンの借り入れ条件】
ペアローン契約者:夫(年収600万円)、妻(年収500万円)
購入住宅の価格:5,000万円
住宅ローンの借入額:夫3,000万円、妻2,000万円
住宅ローン金利:年1%(全期間固定金利)
返済期間:35年間
住宅の環境性能など:長期優良住宅・低炭素住宅の場合
住宅ローン限度額:5,000万円
最大控除額:夫婦それぞれ上限35万円
控除期間:13年間
持ち分割合:夫5分の3妻5分の2
ペアローンでは、夫婦のそれぞれが住宅控除を受けられます。
夫婦共有名義での購入ですが、それぞれの借入額や持ち分割合に応じて条件は異なります。
今回のケースでは、借入額と持ち分の割合は同じでしたが、例えば持ち分が2分の1ずつの場合だと、5,000万円の2分の1です。
それぞれの借り入れの上限は2,500万円までとなるので、持ち分を決める場合には注意をしましょう。
ペアローンのメリット
ペアローンはやめたほうが良いと言われていますが、多くのメリットがあることから利用者は年々増えています。
リスクだけでなく、メリットを理解することで、ペアローンを有効に活用できます。
ここでは、ペアローンの3つのメリットについて解説します。
借入可能額が増加する
ペアローンを利用すれば、単独で住宅ローンを組むよりも多くの借り入れが可能です。
金融機関の審査では、年収に対して借入可能額が決まります。
ペアローンであれば、それぞれの年収に対して借入可能額が設定されるので、単独で借りるよりも借入可能額が増加するというわけです。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は、年収の約5倍~7倍と言われています。
例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円の場合、年収の7倍を借りられるとすると、夫の年収を基準とする単独の場合は3,500万円ですが、ペアローンであれば、5,600万円まで借り入れが可能です。
単独では住宅ローンを組むことが難しい場合でも、ペアローンにすることで購入できる物件の範囲が広がる点がメリットになるでしょう。
夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる
ペアローンを組む場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象です。
主債務者である夫だけしか住宅ローン控除を受けられない収入合算と比べると高い節税効果を得られます。
ただし、住宅ローン控除には、控除額に上限がある点には注意が必要です。
控除額については、夫婦それぞれが最大35万円、合計で70万円が限度額となっています。
金利や返済期間を分けて設定できる
ペアローンでは、生活様式やライフイベントに合わせて、金利や返済期間を夫婦それぞれが独自に設定できます。
例えば、夫のローンは、できるだけ低い金利で長期間に設定することで毎月の返済額を抑え、妻のローンは、期間を短くして早めに返済を完了させるといった設定が可能です。
ライフイベントの中でも、子どもの高校、大学進学の時期はお金がかかります。
長期で組んで返済を進めながら教育資金を貯める、一方を進学までに返済をしてその時期のキャッシュフローを増やすなど、自身のライフスタイルに合わせたローンを設定しましょう。
ペアローンのデメリット
ペアローンは諸費用などの資金面だけでなく、場合によっては贈与税がかかるなど、気になる点が多々あります。
住宅ローンを組んだ後で後悔しないためにも、デメリットを理解しておくことが重要です。
ここでは、ペアローンの3つのデメリットについて解説します。
単独のローンよりも諸費用がかかる
住宅ローンを組む際には、融資事務手数料や契約書に使う印紙代、団体信用生命保険の保険料などの諸費用がかかります。
ペアローンの場合は、夫婦それぞれが諸経費を負担することになるので、単独ローンよりも多くの諸経費が必要です。
金融機関によって融資事務手数料は異なるので、ペアローンを組む金融機関を選ぶ際には、融資事務手数料や保証料などを含めて比較する必要があります。
ライフイベントに伴う負担が増える
ペアローンを組むということは、夫婦それぞれが多額のローンを抱えるということです。
結婚、出産、進学など、結婚生活ではさまざまなライフイベントがあります。
特に、出産時には育児休暇などを使っても妻の収入が一時的に減少するので、返済の負担が増えることを想定した資金計画を組むことが重要です。
一方が退職した場合にも同様に返済の負担が増えるので、高齢の方はペアローンを組む際は注意しましょう。
贈与税が発生する場合がある
ペアローンを組む際には、住宅ローンの負担割合に応じて夫婦それぞれが不動産の登記をするのが一般的です。
しかし、中には住宅ローンの負担割合とは異なった所有割合で登記するケースもあります。
その場合、ペアローンを組んだ後に、一方が退職など何らかの理由で支払いができなくなり、一方のローンを支払うと贈与税が発生することがあります。
贈与税を回避する上でも、住宅ローンの負担割合と不動産の所有割合は合わせておくほうがよいでしょう。
夫婦で住宅ローンを借りる主な3つの方法
夫婦で住宅ローンを組むことを検討している場合は、事前にいくつかの方法を把握しておくことが大切です。
ここでは、夫婦で住宅ローンを借りる3つの方法について解説します。
ペアローン
ペアローンは、夫婦それぞれが別々に住宅ローンを借りる方法です。
単独では、ローンの希望金額に届かない場合や当初の予算よりも高い物件を購入する際に利用します。
ペアローンを借りる手順としては、まずは同じ金融機関に夫婦それぞれが希望金額で仮審査を申し込みます。
仮審査で問題なければ、不動産の売買契約を行って本審査へと進みます。
本審査の承認が取れれば、金銭消費貸借契約を行い、融資が実行されます。
必要書類は以下の通りです。
・ローン借入申込書
・個人情報の取扱いに関する同意書兼表明および確約書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバー、パスポートなど)
・住民票の写し
・健康保険証
【所得証明できる書類】
・源泉徴収票
・確定申告書など
【物件関係書類】
・売買契約書
・重要事項説明書など
金融機関によって上記以外でも書類が必要な場合もあるので、ペアローンを申し込む際には事前に金融機関に確認しましょう。
連帯債務型
連帯債務型は、収入合算の方法のひとつで、契約者と配偶者(親族など)が連帯債務者となって住宅ローンを借りる方法です。
ペアローンと同様に、単独ではローンの希望金額に満たない際に利用するケースが多くを占めます。
連帯債務型では、夫婦それぞれが住宅ローンの全額の債務を負うのが特徴です。
連帯債務型を借りる手順としては、まずは金融機関に主債務者と連帯債務者として希望金額で仮審査を申し込みます。
仮審査で問題なければ、不動産の売買契約を行って本審査へと進みます。
本審査の承認が取れれば、金銭消費貸借契約を行い、融資が実行されます。
連帯債務型は、ペアローンと同様に連帯債務者も住宅ローン控除を受けられ、契約も1本にできるのがメリットと言えます。
一方で、連帯債務者は団体信用生命保険に加入できない、取り扱っている金融機関が少ないのがデメリットです。
連帯保証型
連帯保証型は、収入合算の方法のひとつで、契約者は一人で配偶者(親族など)が連帯保証人となって住宅ローンを借りる方法です。
ペアローンや連帯債務型と同様に、単独ではローンの希望金額に満たない際に利用するケースが多くを占めます。
ペアローンや連帯債務型では、夫婦それぞれが債務を負うのに対して、連帯保証型では、一方は主債務者が支払えなくなった際に、連帯保証人として返済義務を負う点が大きな違いです。
連帯保証型を借りる手順としては、まずは金融機関に主債務者と連帯保証人として希望金額で仮審査を申し込みます。
仮審査で問題なければ、不動産の売買契約を行って本審査へと進み、本審査の承認が取れれば、金銭消費貸借契約を行い、融資が実行されます。
連帯保証型はペアローンや連帯債務型と比べると、錬太保証人は住宅ローン控除が受けられない、住宅ローンの借入可能額も低い点を抑えておきましょう。
また、住宅ローンの審査で落ちるリスクを下げておくために、本審査が通らない理由をあらかじめ確かめておくことをおすすめします。
ペアローンに関するQ&A
実際にペアローンを利用する前に、もう少しペアローンについて詳しく知りたいという人もおられるのではないでしょうか。
ここでは、ペアローンのよくある疑問や悩みについて、具体的な質問形式で解説します。
ペアローンの利用条件は何ですか?
ペアローンの利用条件として、最低限必要なのが夫婦それぞれに収入があることです。
諸条件については金融機関によって条件が異なります。
例えば、フラット35のペアローンの利用条件は以下のとおりです。
ペアローンを組める人は、収入合算できる人の(1)~(3)の要件にあてはまる必要があります。
(1)申込みご本人の親、子、配偶者など
(2)申込時の年齢が満70歳未満の方
(3)申込みご本人と同居する方
・それぞれが100万円~8,000万円(限度額は年収によって異なる)
・物件価格以下
【借入期間】
金利はフラット35と同じ
【担保】
借入対象となる物件に対して、2つの融資についていずれもそれぞれに住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位(同順位)の抵当権を設定が必要
【その他】
2つの融資それぞれが単独債務での申込みとなるため、親子リレー返済は利用できない
金融機関によっては、最低申込金額が500万円以上、ペアローンを申し込む相手との関係性など、細かい条件が設定されているケースもあります。
まずは、利用する金融機関のホームページや店舗で、ペアローンの利用条件を確認しましょう。
ペアローンを途中で一本化できますか?
ペアローンは、免責的債務引受といって第三者が債務を引き受けることで解消できます。
例えば、離婚をして妻が住む場合、妻は債務を引きうけて住宅ローンを一本化するといった方法があります。
しかし、残債が多い場合は、引き受ける側の与信が足りずに免責的債務引受ができないケースも考えられるでしょう。
そういった場合は売却や他の人に免責的債務引受をしてもらう必要があります。
育休中でもペアローンは組めますか?
育休中でもペアローンは組めます。
しかし、育休中ということで、復職できない可能性も考慮されるので審査は厳しくなる点には注意が必要です。
審査で承認をもらうためには、収入の安定性を証明する必要があります。
育休手当は給与ではないため年収に含まれないので、育休前の一年間の年収や育休取得の直近3ヶ月の給与明細とボーナスから割り出した金額などで年収を算出するとよいでしょう。
また、職場の実績や職場復帰の時期が記載された勤務先発行の証明書などによって、復職できる可能性が高いと判断されれば審査にもプラスになります。
まとめ
今回は、ペアローンのメリット、デメリットや夫婦で住宅ローンを借りる主な3つの方法について解説をしてきましたがいかがでしたでしょうか。
物件の価格が高騰する中、ペアローンは物件を購入する上で活用できる選択肢の一つといえます。
夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる、返済条件を生活様式に合わせて組めるなどメリットが感じられるでしょう。
しかし、ペアローンには、夫婦どちらかの一方が出産や退職などで収入が減った場合や離婚時の対応が難しいといったデメリットもあります。
ペアローンで失敗しないためには、メリット、デメリットを把握し、資金計画をきちんと立てることが重要です。
これからペアローンで住宅の購入を考えている人は、今回の記事を参考に、ペアローンを有効に活用していただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。