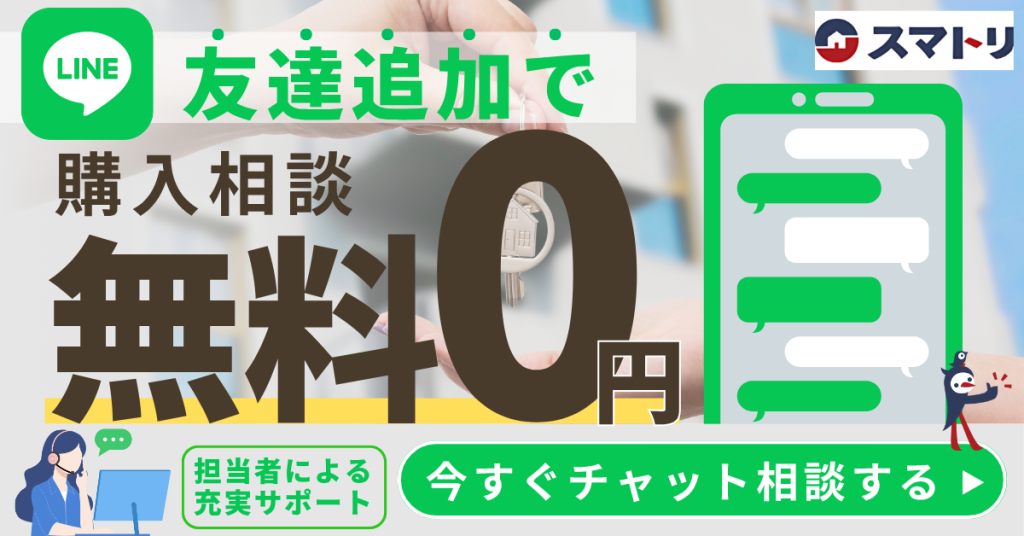長期優良住宅を建てて後悔する人の特徴とは?失敗しないための注意点を解説
「長期優良住宅の魅力を知りたい」「長期優良住宅はいろいろと控除が受けられるって本当?」など、耐震性や省エネ性に優れた長期優良住宅を建てたいという方もおられますよね。
長期優良住宅は、長期に渡って良好な状態を保って住み続けられる住宅のことです。
2024年1月以降に建築確認を受けて建てられた新築住宅においては、住宅ローン減税を受けるために省エネ性能が必須となっており、省エネ性の高い長期優良住宅の注目が高まっています。
長期優良住宅に認定されるには、耐震性や省エネ性だけでなく、バリアフリー性や劣化対策など9つの基準をクリアする必要があります。
そのため、申請費用がかかる、建築期間が長くなるなど、選んで後悔したという人が多いのも事実です。
後悔しないためにも、長期優良住宅の建てる際の注意点を抑えた上で建築を進めましょう。
税金の控除や補助金が受けられ、資産価値が落ちにくいなど、長期優良住宅には多くの魅力があります。
これから長期優良住宅の建築を検討している人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
目次
長期優良住宅とは
長期優良住宅は、長期優良住宅の認定制度によって認定された、長期的に良好な状態で使用するための基準を満たした住宅のことです。
長期優良住宅の認定制度は、2009年6月にスタートした制度で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて導入され、持続可能で快適な住まいづくりの推進を目的としています。
長期優良住宅に認定されるためには、以下の9項目の基準を満たす必要があります。
| 性能項目 | 概要 |
| 耐震性 | 極めてまれ(数百年に1度)に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図られていること |
| 省エネルギー性 | 必要な断熱性能などの省エネ性能が確保されていること |
| 劣化対策 | 長期間使える耐久性を備えていること |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理がしやすいこと |
| 可変性(共同住宅・長屋のみ) | ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすいこと |
| バリアフリー性 | バリアフリー改修の実施に対応できること |
| 居住環境 | 地域の良好な景観形成に配慮されていること |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模があること |
| 維持保全計画 | 定期点検、補修の計画が作成されていること |
長期優良住宅の認定基準のうち、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性については、住宅性能表示制度の基準をもとに設定されています。
長期優良住宅は、さまざまな基準をクリアした住宅のため、将来的に資産性が維持しやすい点が魅力のひとつと言えるでしょう。
長期優良住宅を選んで後悔する4つの理由
新居を建てる際に、長期優良住宅を選択したことで後悔するケースも少なくありません。
長期優良住宅を建てるには、申請費用がかかりますし、建築期間が長くなる、定期点検が必要であるといった
点に不満を持つ人が多いようです。
ここでは、長期優良住宅を選んで後悔する4つの理由について解説します。
申請費用がかかること
長期優良住宅を建てる際には、認定を受けるために申請が必要です。
申請には、認定申請料、審査料、 技術審査料などの費用がかかります。
一般的には、自分で用意できれば5万円~6万円、ハウスメーカーなどに代行を依頼すると20万円~30万円ほどが必要と言われています。
また、申請費用の他に、書類の準備も必要です。
準備する書類には、設計図書や耐震性や断熱性を示すデータなど性能評価のための資料などがあります。
自分で申請したほうが安く済みますが、書類の提出時にデータ作成や修正も必要なので、手間を考えるとハウスメーカーや工務店に申請の代行を依頼したほうがよいでしょう。
建築期間が長くなること
長期優良住宅は、申請だけなく、複雑な工事をともなうので、一般的な住宅よりも建築期間が長くなる場合が多いです。
長期優良住宅として認定をしてもらうためには、高い品質基準を満たす必要があり、設計や施工プロセスが通常よりも時間がかかります。
施工においても、高耐久性の材料を使用し、厳密な施工基準を守る必要があるので、慎重に作業を進める必要があります。
建築期間に余裕がない人には、長期優良住宅を建てるのは難しいかもしれません。
定期点検が必要になること
長期優良住宅は、新築1年後、以降は5年ごとに定期点検が必要です。
定期点検では、基礎や外壁、屋根などの構造部分の確認、給排水や電気系統など設備の点検、木部や金属部の腐食、シロアリの害など経年劣化の有無などについて点検します。
点検で不備があった場合は、早急に修繕をする必要があり、大きな出費が発生することもあります。
増改築に許可が必要になること
長期優良住宅の増築を行う際には、通常の建築確認申請に加え、長期優良住宅の認定変更申請が必要です。
長期優良住宅の認定変更の許可を受けないと工事が進められません。
通常の増築であれば、10㎡以下などは不要ですが、長期優良住宅の認定を受けている部分であれば10㎡以下でも認定変更申請しないと違法建築になる可能性があるので注意しましょう。
長期優良住宅の5つの魅力
後悔したという話も多い長期優良住宅ですが、税金の控除や補助金など魅力的な部分もメリットも多いです。
長期優良住宅の魅力的な部分を理解し、メリットとデメリットを比較した上で建築するかを検討しましょう。
ここでは、長期優良住宅の5つの魅力について解説します。
税金の控除が受けられる
長期優良住宅の一番の魅力は、住宅ローン減税の優遇や登録免許税などの軽減といった税金の控除が受かられる点です。
令和6年以降は、長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅でないと住宅ローン控除が受けられません。
中でも住宅ローンを使って長期優良住宅を購入する場合は、借入限度額が一般住宅よりも高く設定されています。
例えば、2025年に入居すると、ZEH水準省エネ住宅が3,500万円、省エネ基準適合住宅が3,000万円ですが長期優良住宅の借入限度額は新築の場合は4,500万円です。
住宅ローンを利用せずに現金で住宅を購入した場合は、性能強化費用相当額(上限650万円)の10%が所得税から控除されます。
他にも、登録免許税の税率が低い、不動産取得税の控除額が大きい、固定資産税は税金の控除期間が一般住宅よりも長いといった点もメリットと言えるでしょう。
補助金制度を活用できる
補助金制度が充実しているのも長期優良住宅のメリットと言えます。
補助金制度は年度ごとによって制度や内容が変わるので、利用の際には注意が必要です。
長期優良住宅の主な補助金としては、子育てグリーン住宅支援事業制度、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業制度の2つがあります。
子育てグリーン住宅支援事業制度では、長期優良住宅を新築する場合は、最大で100万円、リフォームをする場合は、一般世帯で30万円、子育て世帯で60万円が支給されます。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業制度では、長期優良住宅がZEH基準を満たす場合、追加の補助金の申請が可能です。
例えば、蓄電システムや再生可能エネルギー設備の導入などが該当します。
住宅ローンの金利優遇が受けられる
長期優良住宅は、全期間固定金利型の住宅ローンであるフラット35の金利優遇を受けられるのも魅力です。
フラット35には、省エネルギーや耐震性に優れた住宅向けのフラット35Sという商品があり、条件を満たせば当初5年間、金利が最大0.75%も引き下げられます。
住宅ローンは多額の借入をするので、5年間でも金利が下がることは資金面で大きな支援となるでしょう。
地震保険の割引が適用される
地震の多い日本では、地震保険は必須の保険と言えるでしょう。
長期優良住宅は、住宅性能が高いので耐震性に応じて地震保険料の割引が可能です。
耐震等級割引では、耐震等級2級で30%、3級で50%、免震建築物割引では、免震建築物と認められると50%の保険料の割引が受けられます。
耐震等級については、3級で震度6強~7の地震でも倒壊・損傷しない強さがあります。
地震の多いエリアの場合は、耐震等級3級を取得した建物を選んだほうがよいでしょう。
資産価値が落ちにくい
長期優良住宅は、長期間良好な状態を保つことができるので、資産価値が落ちにくいと言えます。
長期優良住宅を建てるには、高度な建築技術が必要ですし、使用している資材も一般のものより高価で高性能のものが多く、一般の住宅と比べると建物自体の価値も高いです。
初期コストは高くなりますが、住宅は長く住むので、長期的な視点で考えると十分に元は取れます。
今後は、一定の耐震性能や省エネ性能を備えていないと住宅ローン減税が受けられなくなるので、長期優良住宅の需要は高まるでしょう。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
長期優良住宅の認定を申請する手順
長期優良住宅の建設を決めたら、認定をもらうために書類を揃えて申請することが必要です。
実際の申請は、注文したハウスメーカーや工務店が行ってくれますが、ここでは個人で申請する場合の手順について解説します。
申請する手順は、注文住宅と建売住宅で異なるので注意しましょう。
注文住宅
個人で申請手続きをする場合、注文住宅の申請の手順は以下のとおりです。
1.ハウスメーカーや工務店を決定したのち、建物を建てるための請負契約を締結する
2.長期優良住宅建築計画等を策定して、申請用の書類を作成
3.登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼
4.登録住宅性能評価機関から交付される「長期使用構造等である旨の確認書」もしくは「設計住宅性能評価書」を取得
5.必要書類を添えて所管行政庁へ認定申請を行って建築関係規定への適合審査を受ける
6.所管行政庁から認定通知書が交付されて手続き完了
必要書類については、以下の4点を準備する必要があります。
①認定申請書(第一面・第二面・第四面)
②設計内容説明書
③各種図面・計算書
④長期使用構造等である旨の確認書、もしくは設計住宅性能評価書
長期使用構造等である旨の確認書、もしくは設計住宅性能評価書については、審査をスムーズに進めるために必要ではありますが必須ではありません。
取得しない場合は所管行政庁が審査をします。審査に不合格となった場合は認定されないので事前に取得しておいたほうがよいでしょう。
建売住宅
建売住宅の場合は、建売業者から認定計画実施者の地位を承継するための承認申請が必要です。
建売業者にたいして交付されている認定通知書の名義を分譲事業者から購入者本人へ変更します。
1.購入する建売住宅を選ぶ
2.建売業者が、長期優良住宅建築計画等の作成、技術的審査や認定通知書の交付、建築工事完了まですべて完了しているかを確認
3.書類が整っていることが確認できたら、分譲事業者と売買契約を結び、譲受人を決定
4.必要書類を添えて所管行政庁へと地位承継の承認申請をする
5.所管行政庁から承認通知書が交付されることで、認定通知書の名義が住宅の購入者に変更されて手続き完了
必要書類については、承認申請書、住宅購入を証明できる書類(売買契約書など)の2点のみです。
長期優良住宅の認定書類と合わせて、事前に建売業者が提出して認定をもらっている維持保全計画も引き継ぐ必要があります。
小さな工務店だと申請書類の保管が行き届いていないケースもあるので、購入の前には申請書類がすべて整っているかを必ず確認しましょう。
長期優良住宅を建てる際の注意点
長期優良住宅を建てる際には、いくつか注意するべきポイントがあります。
長期優良住宅で税制優遇を受けるためには確定申告が必要ですし、ランニングコスト、依頼する業者の選定など他にも注意すべき点は多いです。
建てたあとに後悔しないためにも、注意点については事前に確認しておきましょう。
確定申告の際に税金の控除を申請する
長期優良住宅では、住宅ローン減税、認定住宅新築等特別税額控除などの税制の優遇を受けることができますが、税制の優遇を受けるためには確定申告での申請が必要です。
住宅ローン控除・認定住宅新築等特別税額控除の控除申請を進めるにあたっては、必要な書類を早めに準備しましょう。
【申請時に必要な書類】
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
・市区町村長の住宅用家屋証明書の写し
・売買契約書、請負契約書等
・登記事項証明書等
・床面積算定調書等(※認定住宅新築等特別税額控除を受ける場合、かつ認定通知書に二つ以上の構造が記載されている家屋の場合のみ)
・年末残高証明書
・源泉徴収票
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
確定申告の申請方法が分からない場合は、最寄りの税務署に相談しましょう。
確定申告については、翌年の2月16日~3月15日(土日祝が入ると前後にずれることもあります)に実施する必要があります。
期間を過ぎると受理されないケースもあるので注意してください。
ランニングコストを考える
長期優良住宅の認定を維持するためには、提出している維持保全計画に基づいて、点検・メンテナンスが必要です。
少なくとも10年に1回、建築後30年以上の実施が法律で定められています。
点検・メンテナンスは、購入や建築したハウスメーカーに依頼するのが一般的ですが、点検・メンテナンスのランニングコストがかかります。
通常の住宅であれば、何か不具合があっても生活に支障がない場合は先送りできますが、長期優良住宅の場合はすぐに実施する必要があります。
また、点検内容については、実施記録の作成・保存をする必要があり、点検を行った場合は長期優良住宅の認定を取り消されるケースもあるので注意しましょう。
実績のある業者に建築を依頼する
長期優良住宅では、一般住宅と比べて高度な建築技術が必要ですし、建築している資材も高価なものが多いので、実績のある業者に建築を依頼する必要があります。
実績のある業者であれば、認定の基準を満たすための仕様について詳しく、申請の手続きも繰り返し行っているので、スムーズに建築を進められます。
しかし、実績のない業者に依頼すると、必要な書類の準備に時間がかかる、認定基準を満たせずに認定されないといったケースも多いです。
一般住宅と比べて工期が長期になることに加えて、不備や失敗でさらに時間がかかってしまい、予定の日程に工事が完了しない可能性も考えられます。
インターネットの口コミや実際に建てたことのある人の意見などを参考にし、後悔しないためにも信頼のおけるハウスメーカーや工務店を選びましょう。
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
まとめ
今回は、長期優良住宅を選んで後悔した理由や魅力、建てる際の注意点などを中心に解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
日本が目指す低酸素化社会において、住宅では200年住宅の取り組みが行われており、今後は長期優良住宅の普及が拡大していくことが予想されます。
これから新たに新築住宅の購入や建築を検討するにあたって、長期優良住宅を選択肢のひとつとなるはずです。
一般的に、住宅の購入においては住宅ローンを使いますが、長期優良住宅のような一定基準の省エネ性能や耐震性を満たした住宅でないと住宅ローン減税を受けることができません。
長期優良住宅については、購入や建築をして後悔したといった話もありますが、税制の優遇や補助金が利用できる点、資産価値が落ちにくいなどメリットも多いです。
長期優良住宅を建てた場合は、税制の優遇を受けるために確定申告を忘れないように申請しましょう。
長期優良住宅を検討する際には、今回の記事を参考に、長期優良住宅を建てるメリット・デメリットを把握し、建てる際の注意点を抑えていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。