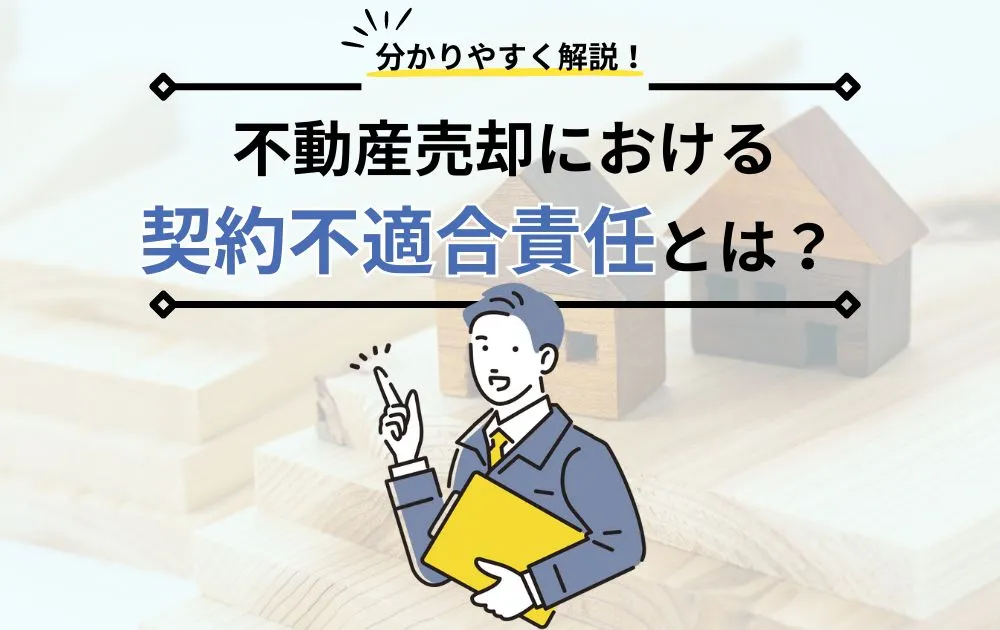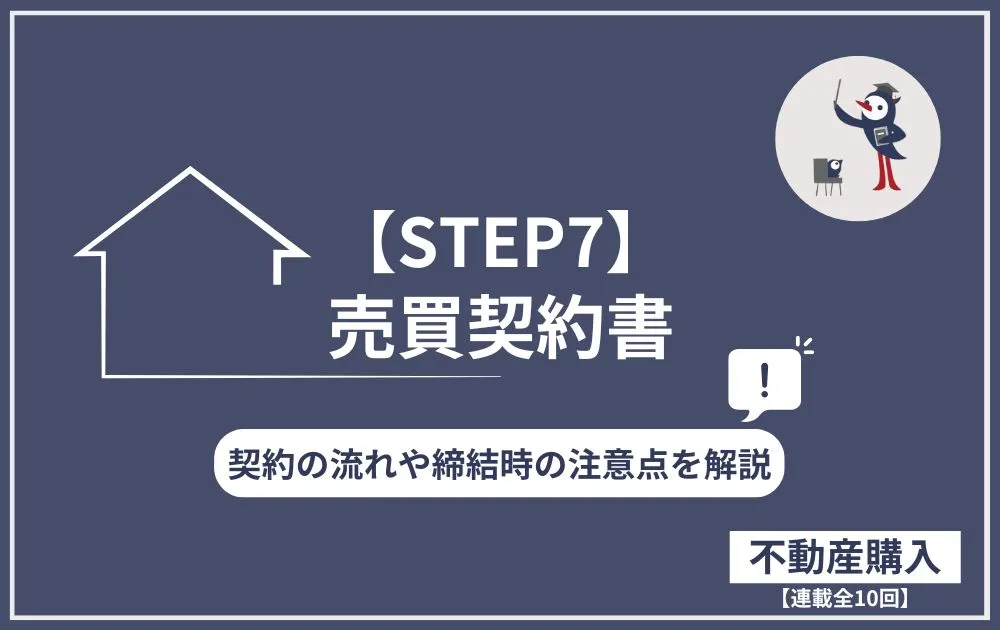不動産売買における重要事項説明書のチェックポイントとQ&Aを解説
「不動産取引の際に説明を受ける重要事項説明書って何?」「不動産会社から重要事項説明書をもらったけれど何が書いているかがよくわからない」など、住宅を購入する際に説明を受ける書面について詳しく知りたいという人も多いでしょう。
重要事項説明書は、物件の重要な事項が記載された書面のことを指します。
購入する土地や建物の建築基準法に関する事項、物件価格や支払い条件などの取引条件に関する事項などが詳しく記載されています。
仲介する不動産会社は、契約前に購入者に対して宅地建物取引士による重要事項説明書の説明が必要です。
以前は対面が基本でしたが、宅地建物取引業法の改正により、現在では電子契約が前面解禁されたことでオンライン上でも重要事項説明が行われるケースも増えています。
住宅の購入時には事前にコピーをもらい、あらかじめ確認事項や質問を考えておくことをおすすめします。
第6回となる今回は「重要事項説明書」をテーマに、説明書のチェックポイントや注意点について詳しくお伝えしていくので、ぜひ最後まで読んでみてください。
重要事項説明書とは「物件の重要な事項が記載された書面」のこと
住宅購入や賃貸契約する際には、契約の前に宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。
その際に、使用されるのが重要事項説明書です。
重要事項説明書の項目は専門家以外が見ると分からないことも多いので、事前に確認しておくことが大切です。
まずは、売買契約書とは異なる重要事項説明書の役割を理解しましょう。
重要事項説明は契約成立前に実施する必要がある
重要事項説明は、不動産購入や賃貸契約の成立前に必ず実施する必要があります。
宅地建物取引業法において、物件の内容や条件についての重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士によって重要事項説明を行うことを義務付けています。
重要事項説明は、買主や借主が契約に関連する重要事項を理解した上で、契約を締結することが目的です。
重要事項説明書と売買契約書は異なる役割を持つ
重要事項説明書は、物件に関する詳細な情報を契約前に説明するもので、売買契約書とは役割が異なります。
買主や借主に物件や契約条件について理解してもらうことが重要事項を説明する目的、売買契約書は、取引条件に関する事項を確認することが目的です。
売買契約書では、取引物件に関する事項は最小限にし、取引条件に関する事項と特約事項の記載が中心です。
一方で、重要事項説明書は取引物件に関する事項について、所有者の謄本情報や建築基準法上に関する事項、インフラの整備状況などについて詳しく記載しています。
電子書面によるオンライン上での説明が可能
2022年5月18日に施行された宅建業法の改正により、電子書面によるオンライン上での重要事項説明が可能になりました。
電子書面によるオンライン上の重要事項説明は、IT重説と言われることもあります。
以前は面前で行う必要がありましたが、電子契約とIT重説が行えるようになったことで、不動産会社へ複数回訪問する必要がなくなり、遠方でも契約できるようになりました。
IT重説の具体的な内容や方法については、来店せずに実施できるIT重説とは?説明の流れと制度の特徴を解説をご確認ください。
〔項目別〕重要事項説明書のチェックポイント

重要事項説明書には多くの項目が含まれており、確認すべきポイントがいくつかあります。
主な項目の記載内容を知っておくことで、重要事項説明書を聞く際のポイントを理解しやすくなります。
ここでは、重要事項説明書のチェックポイントについて項目別に解説します。
取引物件に関する事項
取引物件に関する事項は、物件そのものに関する情報を確認する重要な部分です。
物件の所有権の移転や建て替え時の条件などを確認できます。
特に、戸建の場合は災害警戒区域に関する事項やインフラの整備状況は重要なポイントです。
土地や建物に関する事項
土地や建物に関する事項には、取引対象となる土地の住所や地番や面積、建物の家屋番号や延床面積、構造などの基本的な情報が記載されています。
| 種類 | 記載事項 |
| 土地 | ・所在地、地番 ・地目(宅地、田、畑など) ・地積 ・権利の種類 ・敷地権割合(持分割合) ・借地権の場合は借地権の割合や存続期間 ・備考など |
| 建物 | ・所在地 ・構造 ・住宅の種類 ・延床面積 ・専有部分のある建物の場合はその詳細(家屋番号、建物の名称、間取り、建築の時期など) |
備考欄には、土地の一部が道路になっている場合に道路部分が何㎡あるかなどが記載されます。
土地の内容については、謄本や公図、測量図などを用いて確認します。
測量図が古いものである場合も多く、土地の場合は契約後に測量するか、謄本と差異があった場合は清算するかなども取り決めする必要があります。
建物に内容については、謄本や平面図、間取り図などと照らし合わせて確認します。
登記されている権利に関する事項
登記されている権利に関する事項には、謄本に記載されている所有者と権利の状況が記載されています。
登記の記載事項は、表題部、甲区、乙区の3つです。
表題部は、不動産の基本情報が記載されています。
甲区は、所有権の保存や移転、差押えなどが記載されており、乙区には、不動産に対して誰がどういった権利があるか(抵当権など)が記載されています。
特に、
甲区に市などの差押えが入っている場合は、差押えが解除されないと所有権の移転ができないので注意しましょう。
不動産会社を通じて、売主が差押えについて事前に解除ができるかを確かめましょう。
乙区については、銀行からの抵当権が設定されていることが多いです。
売買金額よりも抵当権の設定金額が高い場合は、売主が差額を準備できないと売買金額を払っても抵当権の抹消ができません。
差額について売主が準備できるかを不動産会社に確認した上で契約しましょう。
法令に基づく制限
法令に基づく制限の項目には、都市計画法や建築基準法などの法令に基づいて受ける建物を建てる上での制限について記載されています。
都市計画法では、住居系地域や商業・工業地域など用途地域によって、建ぺい率や容積率、最低敷地面積など様々な制限があります。
建築協定、まちづくり条例によって、より厳しい制限が設定されている地域も多いです。
マンションの場合は、すぐに建て替えるケースは少ないと思いますが、土地を購入して家を建てる場合や建て替えを検討している場合には、どういった制限を受けるかをきちんと確認しておく必要があります。
災害警戒区域に関する事項
災害計画区域に関する事項には、土砂災害や津波災害警戒区域内か否かなど、ハザードマップに関する事項が記載されています。
近年、台風や地震によって大きな被害を受けるケースが増えており、購入するエリアが災害警戒区域内か外かで生活上のリスクや資産価値が大きく変わります。
災害警戒区域に関する事項は、気にする人も多く、チェックポイントの中でも重要な要素のひとつです。
建物の性能評価や調査に関する事項
建物の性能評価や調査に関する事項には、建物状況調査(インスペクション)、住宅性能評価、耐震診断などの調査や診断の実施状況、結果が記載されています。
建物状況調査(インスペクション)の説明は、2018年4月から中古住宅取引の際に義務化されています。
耐震診断の調査の有無と結果については、旧耐震基準と想定される昭和56年6月30日以前の物件は記載が必要です。
築30年以上の築年数が古い建物については、アスベストが使用されている可能性があります。
アスベストを使用している建物は、リフォーム時に高額な費用がかかる場合が多いです。
アスベストの調査の有無や結果についても確認しておきましょう。
インフラの整備状況
インフラの整備状況の項目には、水道、電気、ガス、下水道などのインフラがどの程度整備されているかが記載されています。
マンションの場合は、基本的には建物全体でインフラは整備しているので、一括受電方式(電気料金が安い)を採用しているかを確認しておきましょう。
戸建の場合は、上水道管の引き込み管のチェックは重要なポイントです。
市区町村などの公設管ではなく、私設管の場合は水漏れや管の交換を自費で行う必要があります。
また、長期間にわたって放置されていた土地を購入する場合、上下水道の引き込み管がないケースも多く、引き込み管を新たに引くとなると数十万円が必要です。
引き込み管については、水道局の上下水道台帳で確認できますが、仲介する不動産会社が用意するのが一般的です。
取引条件に関する事項
取引条件に関する事項は、物件の売買価格や手付金、契約解除の条件など、取引に関する具体的な内容を確認する項目です。
売買契約書の内容と重複するケースも多いですが、手付金の保全措置や金銭の貸借に関する事項など売買契約書を補足する内容もあります。
売買契約に進む前に、不明な点があれば事前に確認しましょう。
売買代金とその他の金銭に関する事項
売買代金とその他の金銭に関する事項には、売主と飼い主の双方が合意した売買代金などの条件が記載されます。
住宅の売買の場合は以下の項目が記載されます。
・売買代金
・手付金
・固定資産税、都市計画税の精算金
・マンションの場合は、管理費、修繕積立金の精算金
売主が消費税業者の場合は、建物部分に消費税がかかります。
仲介手数料は、消費税金額を含まない金額が基準となるので注意しましょう。
契約解除や損害賠償の予定
契約解除や損害賠償の予定の項目については、手付解除や契約不適合責任による解除などの契約解除に関する条件や損害賠償の予定や違約金に関する事項が記載されています。
契約解除の条件には以下のようなものがあります。
・手付解除
・引渡し前の滅失・損傷の場合の解除
・契約違反による解除
・反社会的勢力の排除条項に基づく解除
・融資利用の特約による解除
・借地権譲渡について土地賃貸人の承諾を得ることを条件とする契約条項に基づく解除など
契約を解除する条件については、売主と買主の双方ですり合わせを行います。
融資利用の特約による解除はローン特約とも言われ、買主が個人で住宅ローンを利用して購入する場合は、基本的には条件として設定されます。
買主は、売買契約までに住宅ローンの事前審査の承認を取得するのが一般的です。
事前審査が承認されれば、本審査で否決されることはほとんどありませんが、万が一否決された場合は融資利用の特約による解除で白紙解除できます。
違約金については、「売主または買主が契約内容に違反する場合(債務不履行の場合)、相手方に対して一定金額を支払う」と記載されています。
損害賠償の金額については、手付金額と同額、売買代金の10%に設定されることが多いです。
債務の不履行の例としては、「売主に滞納による差し押さえがあって解除できない」などのケースが考えられます。
債務不履行が発生した段階で書面による催告を行い、それでも債務が履行できない場合は、契約解除をして違約金の請求となります。
「手付解除期日を越えて契約を解除したい」といった場合には、違約金を払って解除することもあります。
手付金の保全措置について
手付金の保全措置についての項目は、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合に適用される買主保護を目的とする手付の保全措置について記載されています。
売買契約をして手付金を支払ったのちに、宅建業者が倒産すると手付金が戻ってきません。
そのリスクを防止するために、宅建業者は手付金や中間金を受け取る前に、銀行等と保証契約を結んで保全措置をとる必要があるという訳です。
未完成物件の場合は、代金額の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件の場合は、代金額の10%以下かつ1000万円以下であれば、手付金の保全の必要はありません。
金銭の貸借に関する事項
金銭の貸借に関する事項については、物件の購入に住宅ローンを利用する場合、不動産会社による住宅ローンの斡旋の有無や融資金額や期間、金利などが記載されます。
融資に関して記載される内容は以下のとおりです。
・金融機関名
・融資額
・金利
・借入期間
・返済方法(元利均等方式、元金均等方式など)
・保証料
・事務手数料
融資利用の特約による解除を適用するためには、この項目に記載された融資に関する内容で金融機関の審査を受けることが条件です。
複数の金融機関を利用する場合は、それぞれの内容を記載するか、少なくともこの項目に記載された融資内容で審査の承認を得た上で他の金融機関に申し込む必要があります。
契約不適合責任に関する事項
契約不適合責任に関する事項については、売主に契約不適合があった場合に負うべき責任について記載されています。
契約不適合責任とは、売買契約などで種類や数量、品質など契約内容に適合しない目的物が引渡しされた場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
不動産における契約不適合責任には、以下のようなものがあります。
・建物にある傷や破損
・事前に知らされていた内容と異なる建物の性能や機能(躯体や設備など)
・事前に知らされていた内容と異なる建物や土地に関する情報(土地の面積や建物の延べ床面積など)
・事前に知らされていた内容と異なる法律上の規制(建築基準法に違反していて再建築できないなど)
契約不適合責任の通知期間については、不動産の売買契約では、個人間であれば3カ月、売主が宅建業者であれば2年間とされているケースが多いです。
中古物件の場合は、引渡し後に建物の不具合などが発生する可能性が高いので、契約不適合責任を免責として契約するケースもあります。
その他の事項
区分所有者建物に関する事項や特約事項がある場合は、その他の事項として記載されることもあります。
その他の事項には、取引物件や取引内容によってさまざまな事項が追加されますが、取引において重要な内容が記載されていることが多いです。
他にも、近隣の施設や自治会や町内会に関する事項などが記載されています。
引渡し後に重要になる内容も多いので、必ず確認するようにしましょう。
区分所有建物に関する事項
マンションなどの区分所有建物を売買する場合、区分所有建物に関する事項を記載する必要があります。
区分所有建物に関する事項は、建物の区分所有等に関する法律に基づいた重要事項を説明する必要があり、マンションなどの重要事項に関する調査報告書や管理規約、使用細則(※1)などを用いて説明されます。
区分所有建物に関する重要事項は以下のとおりです。
・敷地の権利の種類(敷地権、所有権)
・借地権の地代
・共用部分における管理規約や使用細則の内容
・専有部分における管理規約や使用細則の内容
・専用使用権に関する管理規約や使用細則の内容
・修繕積立金の月額、滞納額、積立総額
・管理費の月額、滞納額
・修繕積立金や管理費以外の費用
・管理委託先の情報、管理形態
・修繕の実施状況の記録
・実施が予定されている修繕工事
区分所有者に関する事項では、直近で管理費や修繕積立金の値上げの予定がないかを確認しましょう。
大規模修繕の実施時期やその時点での修繕積立金額の確認も重要です。
値上げが予定されている、大規模修繕のために臨時徴収があるといった場合は、それも踏まえた上で購入をするかを検討する必要があります。
「修繕積立金って何?」「いくらぐらいかかるの」と疑問を感じる方は以下の記事も合わせてご確認ください。
使用細則(※1): 管理規約に基づいて設定される詳細のルール
特約事項
売買契約において、売買契約書の条文以外に取り決めが必要な場合は特約事項として記載します。
売買契約書については、宅地建物取引業協会などがひな形を提供しており、それを元に不動産会社が作成するのが一般的です。
例えば、売買契約書には、契約時に買主は物件価格の一部を手付金として支払うという内容の条文があります。
手付金を支払わずに売買契約と引渡しを一括で行う場合は、条文の内容では契約できないので一括決済できる内容の特約を追記します。
特約事項は、売買契約書の条文の内容よりも優先される事項になるので注意しましょう。
重要事項説明を受ける際の注意点
では、実際に売買契約を進めるにあたって、重要事項説明を受けるにはどのように臨めばよいでしょうか。
不動産の売買契約において重要事項説明を受ける際にはいくつかの注意点があります。
落ち着いて重要事項説明を受けるためにも注意点を抑えておくことが重要です。
重要事項説明書のコピーを事前にもらう
重要事項悦明は売買契約の前に行うのが一般的ですが、全く重要事項悦明書を読まずに契約することはリスクがあります。
不動産業に携わっていない方は、聞き慣れない言葉がいくつも登場するので事前に説明書を読み込んでおくことが大切です。
契約の数日前には、重要事項説明書のコピーを事前にもらうようにしましょう。
契約日までに事前に目を通し、気になる点を不動産会社に確認することが重要になります。
変更点がある場合は新たに書類を作成してもらう
重要事項説明書に変更点がある場合は新たに書類を作成してもらいましょう。
重要事項説明書を読んでいると、不明な点や条件面で納得がいかない点が出てくることもあります。
条件に納得がいかないままでは契約することはできないので、不動産会社を通じで交渉して、条件面の調整する必要があります。
売買契約書や重要事項説明書は重要な書類になるので、不備があった場合は作り直してもらうことも検討しましょう。
重要事項説明書に関するQ&A
不動産の売買を一生に何度も行う人は少ないので、重要事項説明を受けるのが初めてという人も多いはずです。
初めての場合は、重要事項説明について何を聞けばいいのかがわからないという人も多いでしょう。
ここでは、重要事項説明について質問が多い内容をQ&A形式でご紹介します。
重要事項説明書を郵便で受け取るだけでは不十分ですか?
重要事項説明書については、郵便で受け取るだけでは不十分です。
基本的には、売買契約の前に宅地建物取引士から重要事項説明書について面前で説明を受ける必要があります。
最近では、電子取引が可能となり、インターネットを使ったIT重説が可能です。
その際にも受け取った重要事項説明書について、ウェブ会議機能などを使って、宅地建物取引士とカメラ越しに対峙して説明を受ける必要があります。
重要事項説明書が不要なケースはありますか?
不動産会社を通じて契約する場合、買主が個人であれば基本的に重要事項説明書が必要です。
不動産の知識がない人に対して、専門家である宅地建物取引士が不利な契約にならないように重要事項を説明します。
重要事項説明書が不要なケースは、不動産会社を通さない個人間の契約や買主が宅建業者の場合です。
個人間で契約すると仲介手数料は不要ですが、トラブルも多いので不動産会社を通すほうがよいでしょう。
借地権を売買する際に重要事項説明は必要ですか?
土地については、所有権の売買だけでなく、借地権を売買することもあります。
借地権についても宅建業法上の記載の対象なので、借地権を売買する際に重要事項説明は必要です。
契約解除や損害賠償の予定のところでも記載しましたが、借地権の売買には土地賃貸人の承諾を得ることを条件となるケースが多いので、事前に承諾が取れるかを確認しておく必要があります。
最後に
今回は、重要事項説明書の項目別のチェックポイントや注意点について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
重要事項説明書は、マンションや戸建て、土地など購入する不動産について、取引物件や取引に関する事項について詳しく記載された書類です。
不動産会社を通じて物件を購入する際は、その契約にかかわる不動産会社の宅地建物取引士が買主に対して重要事項を説明する義務があります。
重要事項説明書の内容については、専門用語も多く、一度見ただけでは理解することが難しいと思います。
売買契約を進めるにあたっては、事前に重要事項説明書をメールや郵送で送ってもらい、内容についてチェックすることが重要です。
不明な点は不動産会社に確認をし、条件面で納得がいかない場合は売主と交渉する必要があります。
変更があった場合は、きちんと不動産会社に修正してもらいましょう。
これから不動産を購入する予定がある人は、今回の記事を読んでいただき、重要事項説明書の項目別のチェックポイントや注意点を理解し、売買契約に臨んでいただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。