地震で潰れやすいマンションの階はどこ?階層別の危険性を解説
「マンションは地震で潰れやすい階があるって本当?」「やっぱり1階は危険なの?」など、マンション購入を考えるとき、このような不安を抱く方も少なくありません。
地震大国での日本では、階数や構造によって揺れ方や被害リスクが変わるのは事実です。
特に「潰れやすい階」と言われる理由や、安心して暮らせる階数は、多くの方が気になるポイントでしょう。
本記事では、マンションの構造や過去の地震被害例をもとに階ごとのリスクを解説し、耐震基準のチェック方法も整理しました。地震に強いマンションを見極め、安心できる住まい選びのヒントをお探しの方は、ぜひ最後までお読みください。
👉スマトリの無料診断(1分)
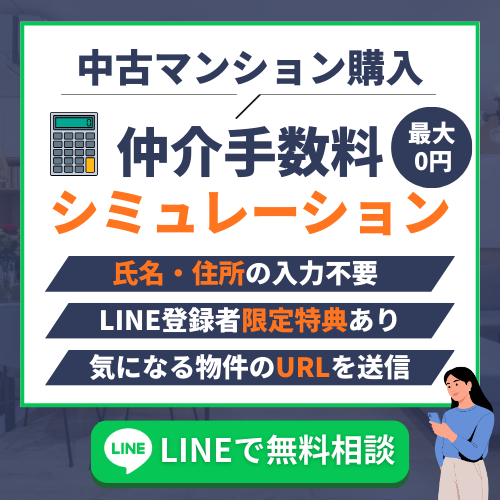
\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/
スマトリ公式LINEで無料相談する
目次
地震で潰れやすいマンションの階は1階?構造的に弱い原因
マンションの1階は建物全体の重さを支え、地盤からの揺れも直接受けるため、被害を受けやすいとされています。
とくに駐車場やエントランスで壁が少ない構造では強度が不足し、倒壊リスクが高まることもあります。こうした理由から、1階は他の階より弱点になりやすいのです。詳しくは次の項目で解説します。
1階が潰れやすいとされる理由(上部荷重・ピロティ構造・地盤からの衝撃)
1階は建物全体を支える基礎部分にあたり、上層階の重さが集中しやすい場所です。
そのため、地震時には負担が大きく、構造的に弱点となる可能性があります。
さらに、駐車場や共用スペースを確保するために柱だけで支える「ピロティ構造」が採用されている場合、壁が少なく水平方向の力に弱く、実際に倒壊した事例もあります。
加えて、1階は地盤からの衝撃を直接受けやすく、地震の影響がダイレクトに伝わる点もリスクの一因です。これらの要素が重なることで、1階部分は「潰れやすい階」と言われることが多いのです。
1階のマンションの地震の被害例
過去の大地震では、マンションの1階部分が大きな被害を受けた事例が複数報告されています。
代表的なのは1995年の阪神淡路大震災で、ピロティ構造を持つマンションやアパートで1階部分が崩壊し、大きな被害につながったケースが多く見られました。
また2016年の熊本地震でも、1階部分に被害が集中した住宅やマンションが確認されています。いずれも、上部からの荷重と横揺れに耐えられず、柱や壁が損傷したことが原因と考えられています。
もちろん、すべての1階が危険というわけではありません。ただし耐震設計が不十分だったり、旧耐震基準で建てられたりした物件ではリスクが高まります。
こうした被害例からも、建物の構造にどんな弱点があるのかを把握し、安心につながる対策を考えておくことが大切でしょう。
参考:阪神・淡路大震災教訓情報資料集【03】建築物の被害(内閣府)
参考:平成28年熊本地震による鉄筋コンクリート造等建築物被害(国立研究開発法人 建築研究所)
マンションは何階が地震に強い?安全な階数の考え方
「潰れやすい階」とされる1階を避ければ安心、というわけではありません。マンションは階数によって揺れやすさや被害リスクが異なり、必ずしも上階が安全とは限らないのです。
一般的に中層階(3~5階前後)は揺れとリスクのバランスが取れているといわれます。低層階は荷重を支える負担が大きく、高層階は揺れ幅が大きいため家具の転倒や避難の難しさが課題です。
耐震基準を満たした建物であれば、どの階でも一定の安全性は確保されます。最終的には「何階に住むか」だけでなく、建物の性能や立地、生活のしやすさを総合的に見て判断することが大切です。
〔階層別〕地震による危険性
マンションは階数によって揺れ方や被害の出やすさが異なり、低層・中層・高層それぞれにメリットと注意点があります。ここからは階層ごとの特徴を見ていきましょう。
低層階

低層階は地盤に近いため、地震の揺れを直接受けやすい位置にあります。
特に1階は建物全体の荷重が集中し、構造によっては「潰れやすい階」とされることもあります。また、駐車場やエントランスを広く取ったピロティ構造では壁が少なく、水平方向の揺れに弱いため被害が大きくなる可能性があるでしょう。
一方で、低層階は高層階に比べて揺れの幅が小さく、家具の転倒リスクやエレベーター停止時の避難のしやすさという点では有利です。つまり低層階には「構造上の負担が大きいリスク」と「生活面での安心感」の両面があるといえます。
購入を検討する際は、耐震基準や設計の工夫を確認し、自分たちの暮らしに安心をもたらせる条件かどうかを見極めることが大切です。
中層階

中層階(3~5階程度)は、低層階と高層階の中間にあたり、揺れやリスクが比較的バランスの取れた階層といわれます。
地盤に近い衝撃を直接受けるわけでもなく、高層階のように揺れ幅が増幅することも少ないため、地震に対して一定の安心感があるのが特徴です。
また、エレベーターが停止した場合でも階段での避難がしやすく、家具の転倒リスクも極端に高くありません。ただし、建物の構造や耐震性能が不十分であれば、中層階でも安全とは限りません。
特に旧耐震基準のマンションでは、1階の損傷が上階全体に影響する場合があります。中層階を選ぶ際も、建物全体の耐震性を確認することが重要です。
高層階

高層階は地震時に、揺れを大きく感じやすいのが特徴です。建物のしなりによって揺れ幅が増幅し、低層や中層よりも長時間大きく揺れる「長周期地震動」(※1)の影響を受けやすくなります。
そのため、家具や家電の転倒リスクが高まり、室内での二次被害も起こりやすくなります。また、停電やエレベーター停止時には避難が難しく、地震後の生活に不便が生じやすい点にも注意が必要です。
一方で、建物全体の耐震性能が十分であれば、倒壊リスク自体は低層階と比べて特別に高いわけではありません。高層階に住む場合は、家具の固定や非常用備蓄の確保など、揺れに備えた対策を整えることが安心につながります。
(※1)「長周期地震動」:大きな地震で発生する周期の長い揺れのこと。高層ビルなどではこの影響で大きく長時間揺れ続けることがあり、震源から遠く離れた場所にも影響が及ぶのが特徴。
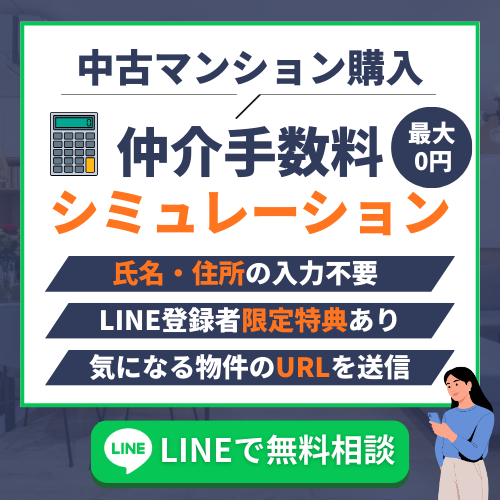
\エリア・物件選びの相談も可能/
スマトリ公式LINEで無料相談する
高層階の災害リスクが大きい理由

高層階は倒壊そのものよりも、地震による暮らしへの影響が大きいといわれます。
揺れが強く感じられるだけでなく、避難の難しさや家具の転倒による二次被害など、生活面でのリスクが高まりやすい点が特徴です。詳しくは次の項で見ていきましょう。
遠心力や風で揺れを感じやすいため
高層階は建物のしなりによって揺れが増幅し、低層階より大きく長い揺れを感じやすくなります。
これは遠心力や長周期地震動の影響によるもので、揺れが収まるまでに時間がかかるのが特徴です。
さらに風の影響も加わることで体感的な揺れは強まり、めまいや不快感を覚える人もいます。建物自体の耐震性は確保されていても、居住者にとって心理的な負担になりやすい点は高層階特有のリスクといえるでしょう。
地上までの距離が遠いため
高層階では、停電やエレベーターの停止時に避難が難しくなるという課題があります。
地上までの距離が遠いため、階段を使った移動には体力と時間が必要で、特に子どもや高齢者には大きな負担となります。
災害時にすぐ外へ出られない不安は、高層階ならではのリスクです。普段から非常食や飲料水を備え、在宅避難を想定した準備を整えておくことが大切です。
家具や設備の倒壊の恐れがあるため
高層階は揺れが大きく長引きやすく、家具や家電が転倒・移動して室内で二次被害が起こるリスクが高まります。
冷蔵庫や本棚など重量のある家具が倒れると、けがや避難経路の塞がりにつながる危険もあるでしょう。
また、給湯器や配管などの設備に負荷がかかり、破損によって生活に支障をきたすことも想定されます。
高層階で暮らす場合は、家具を固定したり耐震マットを使ったりと、室内の安全対策を欠かさないことが重要です。
地震の揺れに弱いマンションの特徴

マンションは設計や立地によって地震への強さが変わります。特に上下階の高さがそろっていない建物や、1階が柱だけで支えられるピロティ構造、複雑な形状の建物は揺れに弱い傾向があります。
ここからは、地震の揺れに弱いマンションの特徴を具体的に見ていきましょう。
上下の階で高さが異なる構造
各階の高さが均一でない場合、建物のバランスが崩れ、地震に対して弱くなる傾向があります。
たとえば、1階だけ天井を高くして店舗やエントランスに使うケースでは、他の階より柱や壁に大きな負担がかかり、揺れに耐えにくくなります。
特に大地震では、弱い部分に力が集中し損傷が広がる可能性があるでしょう。
階高のばらつきは外見ではわかりにくいこともあるため、購入時には設計図や構造を確認することが大切です。
1階がピロティ構造のマンション
1階部分を柱だけで支え、駐車場やエントランスとして利用する「ピロティ構造」は、地震に弱い代表的な例です。
壁が少なく水平方向の力に耐えにくいため、大きな揺れでは柱に負担が集中し、倒壊のリスクが高まります。
現在は耐震基準に基づき補強が行われるケースもありますが、物件選びの際には構造の安全性や補強の有無を確認することが欠かせません。
L字型・コの字型など不規則な形状
マンションの形がL字型やコの字型のように不規則だと、地震の揺れが一部に集中しやすく、損傷のリスクが高まります。
直線的な長方形の建物に比べて力の伝わり方が複雑になり、特に接合部や角に負担がかかりやすいのです。大地震では揺れの方向によって弱点が大きく揺さぶられ、ひび割れや倒壊につながる恐れがあります。
ただし、こうした不規則な形状でも、構造設計の工夫によって弱点を補うことは可能です。たとえば、耐力壁や柱を増やして力を分散させる、接合部を補強する、制震装置を設けて揺れを吸収する、建物を複数のブロックに分割して形状の負担を減らす、といった方法があります。
不規則な形状のマンションを検討する際は、このような耐震補強や設計上の工夫が取り入れられているかを確認すると安心です。
旧耐震基準のマンション
1981年6月以前に建築確認を受けたマンションは「旧耐震基準」で設計されており、大地震に対する安全性が十分ではない場合があります。
当時の基準では震度5程度の揺れを想定していたため、震度6以上の地震では倒壊や大きな損傷を受けやすいとされます。
実際、阪神淡路大震災では旧耐震の建物に被害が集中しました。耐震診断や耐震補強が行われていれば安心材料となりますが、購入時には築年数や基準適合の有無を必ず確認しましょう。
参考:住宅・建築物の耐震化について(国土交通省)
参考:阪神・淡路大震災教訓情報資料集【03】建築物の被害(内閣府)
埋立地や地盤の弱い場所
マンションは建つ地盤によっても地震への強さが変わります。埋立地や軟弱地盤では、揺れが増幅しやすく、液状化によって地盤が沈下・傾斜するリスクもあります。
建物自体が耐震構造であっても、地盤が弱ければ十分な効果を発揮できないこともあるでしょう。特に湾岸部や河川沿いの埋立地は注意が必要です。
購入を検討する際には、地盤調査報告書(※2)や自治体のハザードマップを確認し、安全性を判断することが大切です。
(※2)地盤調査報告書:土地の形状や地質の種類、地盤の固さに加え、地盤改良工事の必要性(地盤調査会社の見解)などが記載されているもの。
地震に強いマンションを選ぶためのチェックポイント
安心して暮らすには、耐震性を見極めた物件選びが欠かせません。建物の強さは外観だけでは分からないため、耐震基準や構造、立地を確認することが大切です。
ここからは、購入時に見るべきチェックポイントを紹介します。
新耐震基準に適合している
マンションは新耐震基準に適合していることが、安全性を確保するうえで最も基本的な条件です。
1981年6月以降に建築確認を受けた建物は新耐震基準に基づいており、震度6~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことを目標に設計されています。旧耐震基準は震度5程度を想定していたため、その差は大きいといえます。
購入を検討する際は竣工年だけでなく「建築確認日」が1981年6月以降かを確認することが重要です。
中古マンションなら、耐震診断や補強工事の有無もあわせてチェックし、将来にわたって安心して暮らせるかを見極めましょう。
耐震等級が高い
マンションは耐震等級が高いほど安心でき、将来の地震リスクを考えるならできるだけ上位の物件を選ぶことが望ましいです。
耐震等級は建物の耐震性能を示す指標で、1~3の3段階があります。等級1は建築基準法を満たす最低限の強さ、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性です。
特に等級3は消防署や警察署など防災拠点と同等で、もっとも高い安全性を備えています。
購入時に耐震等級の表示がない場合は、設計図書(※3)を確認したり、売主にたずねたりして確かめておくと安心でしょう。
可能であれば耐震等級2以上、特に3の物件を優先して検討すると安心です。
(※3)設計図書:設計者の意図を施行者に伝えるための設計図や仕様書のこと。
参考:住宅を選定する時に候補となる住宅の基本性能(国土交通省国土技術政策総合研究所)
ハザードマップ上のリスクが少ない
マンションを選ぶ際は、ハザードマップで地盤や周辺環境のリスクが少ない地域かどうかを確認することが重要です。
建物自体が高い耐震性を持っていても、立地が液状化や浸水の危険がある場所では安心できません。埋立地や河川沿いは特に注意が必要です。
自治体が公開するハザードマップを見れば、活断層の位置や地盤の特性、浸水想定区域などを事前に把握できます。
内覧や契約前には必ず確認し、日常の利便性だけでなく災害リスクも含めて立地を判断することが大切です。
鉄骨鉄筋コンクリート造
マンションは鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)であれば、地震に強い構造として安心材料になります。
SRC造は鉄骨のしなやかさと鉄筋コンクリートの強度を組み合わせており、揺れに対する耐久性が非常に高いのが特徴です。特に高層マンションでは多く採用され、耐震性に優れています。
鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)に比べると建築コストは高くなりますが、その分だけ安全性への信頼が厚い構造です。
購入を検討する際は、販売資料や図面で構造を確認し、SRC造であれば長期的な安心につながる判断材料になるでしょう。
【無料】住まい購入の相談はスマトリがおすすめ!
・仲介手数料最大無料
・氏名や住所の入力不要
・電話やメールの営業なし
スマトリのLINE相談では、AIではなく経験豊富な担当者が対応してくれるので、不動産の購入が初めての人でも安心して利用できます。
気になる物件が既にある方は、仲介手数料無料かどうかをお気軽に判定可能です。
「仲介手数料無料って本当?」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、まずはスマトリのLINE相談を活用してみてください。
まとめ
マンションは階数や構造、立地によって、地震の影響を受けやすさが変わります。1階は荷重や揺れが集中しやすく、特にピロティ構造や旧耐震基準の建物、埋立地などに建つ物件は被害が大きくなりやすいといわれています。
安心して選ぶための目安となるポイントは次の通りです。
- 新耐震基準に適合している
- 耐震等級が高い(できれば等級2~3)
- ハザードマップで液状化や浸水のリスクが少ない地域
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)など強度の高い構造
これらに当てはまる物件なら、地震によるリスクを軽減しやすいでしょう。大切なのは「何階に住むか」だけでなく、建物全体の性能や立地を含めて判断することです。
正しい知識を持って選ぶことで、家族が安心して長く暮らせる住まいに近づけるでしょう。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。












