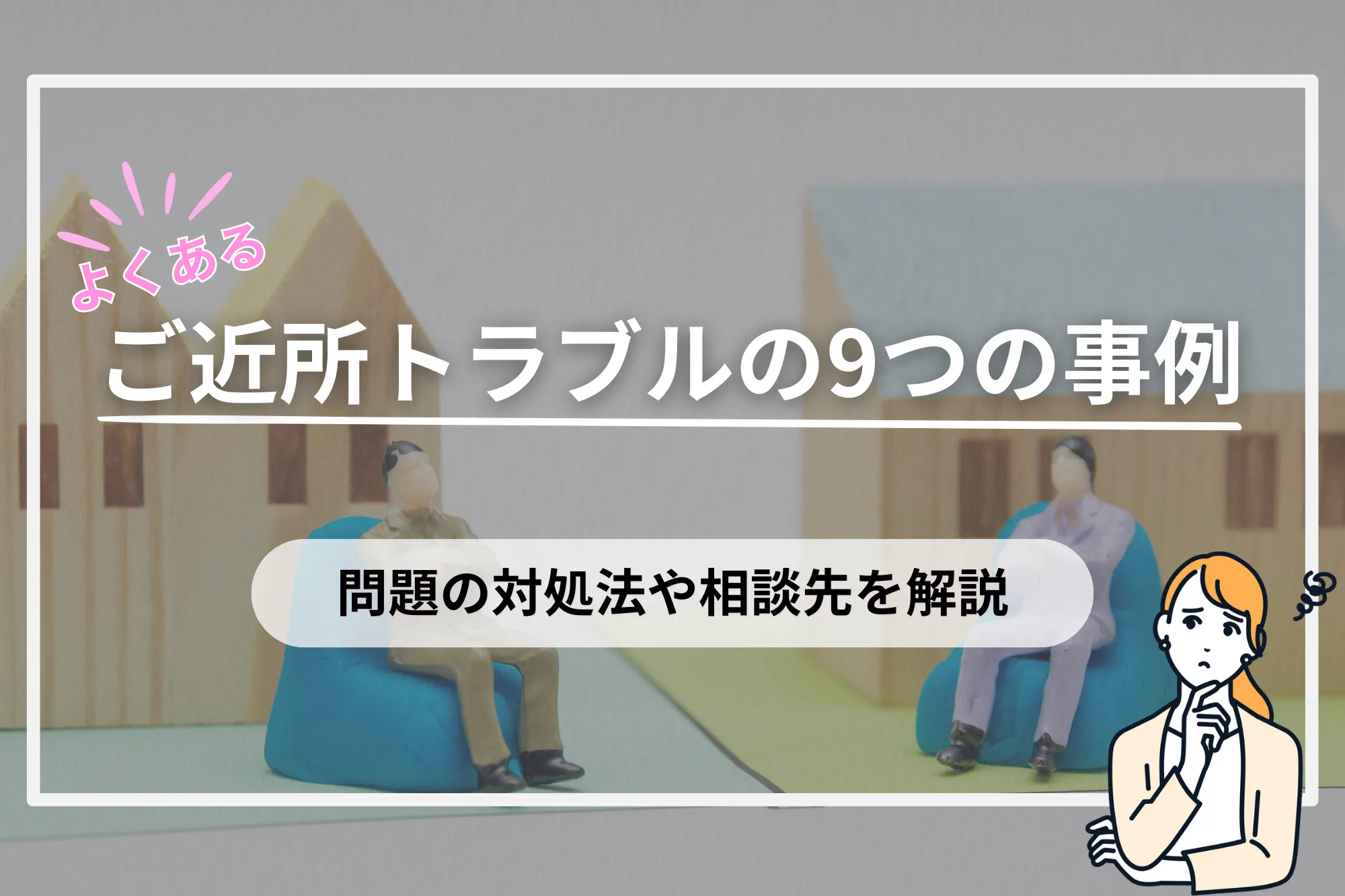日照権とは?制限や受忍限度、侵害された場合の対処法について解説
「日照権ってよく聞くけど詳しい内容を知りたい」「近隣に高層マンションが建つ予定があるけど、日当たりが悪くなったら日照権は主張できるの?」など、日照権という言葉は聞いたことがあるけど、どんな権利かは知らないという人も多いでしょう。
日照権とは、自身が住んでいる建物において、日が当たることを確保して快適に暮らせる権利です。
法律として日照権が定められているわけではありませんが、建築基準法や憲法などの法律を通じて保護されています。
日照権に関わる制限には、建築基準法に基づく斜線制限や日影規制があり、新築や増築をする場合は、制限の範囲内で建物を建てる必要があります。
ただし、建築基準法内で建物を建てても、周辺の人が社会通念上の我慢できない範囲、受忍限度を超えたと判断されるとトラブルに発展してしまいます。
実際に、日照権が侵害された、受忍限度を超えたと感じた際はどういった対処をすればよいか気になる方もおられるのではないでしょうか。
今回の記事では、日照権の制限の内容、受忍限度の範囲、侵害された場合の対処法について解説しますので、最後まで読んでいただければと思います。
👉スマトリの無料診断はこちら(1分)

\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/
スマトリ公式LINEで無料相談する
目次
日照権とは「建物の日当たりを確保する権利」のこと
日当たりが悪いと、洗濯物が乾かない、部屋が暗くてジメジメするなど、毎日の生活に支障がでます。
日照権は、住んでいる建物において、一定の日当たりを確保する権利のことです。
日照権を規定する法律はありませんが、建築基準法や各自治体の条例、憲法などの法律によって保護されており、勝手に侵害してはならないと考えられています。
新築や増築をする場合は、隣地の日当たりを考慮して、建築基準法における斜線制限や日影規制に基づいて、建物を建てる必要があります。
そのため、新しく建てられた建物は、最低限の日照権は確保されていると捉えられますが、人によって日当たりに対する感じ方が違うので、トラブルに発展するケースも多いです。
日照権に関わる制限
新築や増築など新たに建物を建てる際には、日照権に関わる制限を守らないと建築許可がおりません。
日照権に関わる制限は、建築基準法で定められた斜線制限と日影規制の2種類です。
斜線制限では建物の高さ、日影規制では日照時間が制限されています。
ここでは、斜線制限と日影規制について詳しく解説します。
隣地斜線制限
隣地斜線制限では、隣地に面した建物部分の高さが20mもしくは31mを超えた部分について、建物の高さを制限しています。
建物の高さの制限は、用途地域によって異なり、第一種及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、最初から建物の高さを10mまたは12mと制限しているので、隣地斜線制限は適用外です。
| 用途地域 | 制限される高さ | 傾斜勾配 |
|
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 20m | 1.25 |
|
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 | 20m | 2.5 |
制限される高さ20mまたは31mを超える部分にたいして、三角形の底辺と高さの比率で1.25:1か、2.5:1の2種類の傾斜勾配をつける必要があります。
街中でよく見かけるビルの上部が斜めにカットされている建物は、傾斜勾配の制限を受けて建てられています。
道路斜線制限
道路斜線制限は、設置している道路の幅員に応じて、道路側に面した建物の高さを制限しています。
前面道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍または1.5倍以下(傾斜勾配)に建物の高さが制限を受けます。
※横スクロールで表全体を見ることができます
| 用途地域 | 容積率 | 適用距離 | 傾斜勾配 |
|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 田園住居地域 準住居地域 | 200%以下 | 20m | 1.25 |
| 200%超〜300% | 25m | ||
| 300%超〜400% | 30m | ||
| 400%超 | 35m | ||
|
近隣商業地域 商業地域 | 400%以下 | 20m | 1.5 |
| 400%超〜600% | 25m | ||
| 600%超〜800% | 30m | ||
| 800%超〜1,000% | 35m | ||
| 1,000%超〜1,100% | 40m | ||
| 1,100%超〜1,200% | 45m | ||
| 1,200%超 | 50m | ||
|
準工業地域 工業地域 工業専用地域 | 200%以下 | 20m | 1.5 |
| 200%超〜300% | 25m | ||
| 300%超〜400% | 30m | ||
| 400%超 | 35m |
戸建てなどで、道路に面している部分が斜めにカットされている建物は、道路斜線制限を受けて建てられて建物です。
道路からの一定距離(適応距離)を超えると制限がなくなるので、直線的な建物が建てられます。
北側斜線制限
北側斜線制限は、北側の隣地の建物にたいして日照権を確保するための制限です。
北側の隣地の境界線もしくは北側に道路がある場合、その道路の反対側の道路と敷地の境界線からの距離の1.25倍(傾斜勾配)に建物の高さが制限を受けます。
| 用途地域 | 制限される高さ | 傾斜勾配 |
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 | 5m | 1.25 |
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 10m | 1.25 |
日影規制のある地域においては、北側斜線制限は適応されません。
また、自治体によっては、自治体が高度地区を設定しているケースがあり、高度地区が設定されている場合は、北側斜線制限と高度地区の内、厳しい規制の方が適用されます。
一般的には高度地区の制限の方が厳しいケースが多いです。
日影規制
日影規制は、中高層のマンションやビルを建てる際に、隣接する地域の日照を確保するための制限です。
冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、建物の日影が一定時間以上は生じないように建物を建てる必要があります。
建物の高さの制限に加えて、地面からの一定の高さで計測を行います。
※横スクロールで表全体を見ることができます
| 地域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ |
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 | 軒の高さが7mを超える建築物 または、地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m |
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 高さが10mを超える建築物 | 条例により以下のいずれか 4m 6.5m |
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 | 高さが10mを超える建築物 | 条例により以下のいずれか 4m 6.5m |
| 用途地域の指定のない区域 | 軒の高さが7mを超える建築物 または、地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m |
| 高さが10mを超える建築物 | 4m |
高層ビルが立ち並ぶ商業地域では、日影規制はありません。
ただし、敷地周囲の用途地域が日影規制の対象区域で、高さが10mを超える建築物を計画する場合は、日影図による検討が必要になるので注意しましょう。
日影規制の概要や法制化の経緯については、国土交通省が公表しているデータを参考にしてみてください。
\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/
スマトリ公式LINEで無料相談する
日照権の受忍限度について
日照権が侵害されていると感じたときの判断基準が受忍限度です。
受忍限度とは、社会通念上において、我慢できる限界を超えた場合に、違法と判断する基準のことを言います。
加害建物の建築基準法違反の有無、地域制、日照阻害の程度といった要素を総合的に判断し、日照権の受忍限度を超えているかを評価します。
ここでは、日照権が認められた判例と認められなかった判例について解説します。
日照権が認められた判例
日照権が認められるには、加害建物の建築基準法違反の有無、地域制、日照阻害の程度において、違法性の証明ができるかが重要なポイントです。
日影規制のない立地でも受忍限度を超えると認められた例として、 平成22年2月24日の神戸地方裁判所尼崎支部の判例を紹介します。
14階建てのマンションが、日影規制のない立地に計画されたが、その話を聞いた8階建ての隣地マンションの住民が神戸地裁尼崎支部に「日照権を侵害される」として建築差し止めの仮処分の申し立てを行った。
神戸地裁尼崎支部では、判決において、マンションの10階以上の建築を禁止する命令を下しています。
この裁判では、冬至期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸があり、これが受忍限度を超えるかどうかが焦点となり、裁判所は受忍限度を認めるに相当すると結論付けています。
日照権を認めてもらうためには、日影規制の有無といった法律的な部分だけでなく、実際の被害が受忍限度を超えていることを訴えられるかが重要と言えます。
日照権が認められなかった判例
自分では、日照権における違法性があると感じても、様々な要因を検証した結果、裁判所に日照権が認められないケースもあります。
認められない判例の中には、日照権の侵害はあるが、社会通念上の我慢できる範囲を超えて違法性があるとまでは認められないといったケースが多いです。
日照権が認められなかった判例として、平成17年9月29日の大阪地方裁判所の判例を紹介します。
大阪のマンションにおいて、南側の敷地にアパートが建設されることがわかり、1階に住む住民が日照権の侵害による損害賠償の訴訟を起こした。
大阪地方裁判所は、アパートの1階を購入するということ、将来南側にアパートが建築されることは予想の範囲内であること等から、日照権の侵害はあるが、日照権侵害の程度は軽微なもので、受忍限度を超える違法性はないと判断し、損害賠償請求を棄却しています。
裁判では、
様々な観点から総合的に判断されるので、個人的な感覚ではなく、社会通念上、一般的に見て違法性があるかを証明できないと日照権は認められません。
自分だけでなく、親族や知人、弁護士や専門家などの見解を聞いた上で日照権の侵害を訴えるかの判断したほうがよいでしょう。
\気になる物件の仲介手数料をすぐに判定/
スマトリ公式LINEで無料相談する
日照権が侵害された場合の対処法
南側の空き地や駐車場に建物が建設されるなど、新たに近隣に建物が建つと日照権が侵害される恐れがあります。
日照権が侵害せれていると感じた場合は、どのように対応すればよいでしょうか。
ここでは、日照権に侵害された場合の対処法について解説します。
当事者同士で話し合う
日照権を侵害する可能性のある建物が建てられる計画が判明した場合、最初に行うのは建築主や建築会社との話し合いによる交渉です。
当事者同士で話し合って解決できれば、トラブルを未然に防ぐことができます。
しかし、ほとんどの場合は、当事者同士の話し合いでは解決しません。
話し合いが進まない場合は、近隣住民と団結して交渉するのも有効な手段と言えるでしょう。
管理会社や自治会に相談する
既存建物の場合、増築や設備の交換などによって日照権が侵害される場合があります。
賃貸物件やマンションであれば、管理会社が建物や環境トラブルの窓口となっているケースが多いので、管理会社に相談しましょう。
管理会社は、日照権の侵害の事実が確認できれば、オーナーへ改善をするように働きかけてくれます。
また、複数の住民に日照権の侵害の影響がある場合は、自治会に相談するのも有効な手段です。
地域住民の代表である自治会は、地域の住民間のトラブルや環境問題に対応する役割を持っています。
自治会を通すことで、当事者間の交渉をスムーズに進められるだけでなく、問題の共有や解決策の提案も期待できます。
建築指導課に問い合わせる
建物の建築の許可を出す、建築指導課に問い合わせるのも有効な手段です。
まずは、建築指導課に建築基準法や条例の違反がないかを確認します。
建築基準法や条例に違反している可能性があれば、建築指導課が調査をし、是正措置を取ってくれます。
建築指導課に相談する際は、できる限り証拠(写真や測定データなど)を用意しておくことが重要です。
違反がない場合でも、建築指導課が隣地の所有者や建設業者と話し合いの場を提供してくることもあります。
弁護士や専門家に相談する
日照権は、建築基準法などの法律や専門知識が必要になるので、弁護士や専門家に相談するのもひとつの方法です。
弁護士であれば、法律的な観点から日照権の侵害についてアプローチすることができ、実際に損害賠償請求や建築差し止め請求を行う場合は、裁判の進め方について具体的な説明が受けられます。
また、建築士や不動産コンサルタントに相談するのも、日照権の問題を理解する上で有効でしょう。
これまでの経験から日照権の侵害を防ぐ方法や交渉の仕方をアドバイスしてもらえるので交渉をスムーズに進められます。
まとめ
今回は、日照権についての基礎知識や実際の判例、日照権を侵害された場合の対処法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか
日本で住宅に住む限りは、どこでも日照権が侵害される可能性はあります。
万が一、日照権を侵害された場合は、建築の計画がわかった段階で、建築指導課や弁護士などの専門家の力を借りながら当事者間で話し合って解決することが重要です。
話し合いで解決しない場合は、建物が建ってしまうと解決が難しくなるので、損害賠償請求や建築差し止め請求を行うなど、法的な手段を早急に取る必要があります。
購入や賃貸の物件を検討する場合、建物の南側や周辺に空き地や駐車場があれば、日照権が侵害されるリスクを想定した上で、検討する必要があるでしょう。
日照権の侵害を受けないためにも、周辺環境を確認した上で物件を選ぶことが重要と言えます。
これから自宅の購入や賃貸を検討している人は、今回の記事を参考にしていただき、日照権が起こった場合の対応や日照権のトラブルに巻き込まれないための物件選びをしていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。