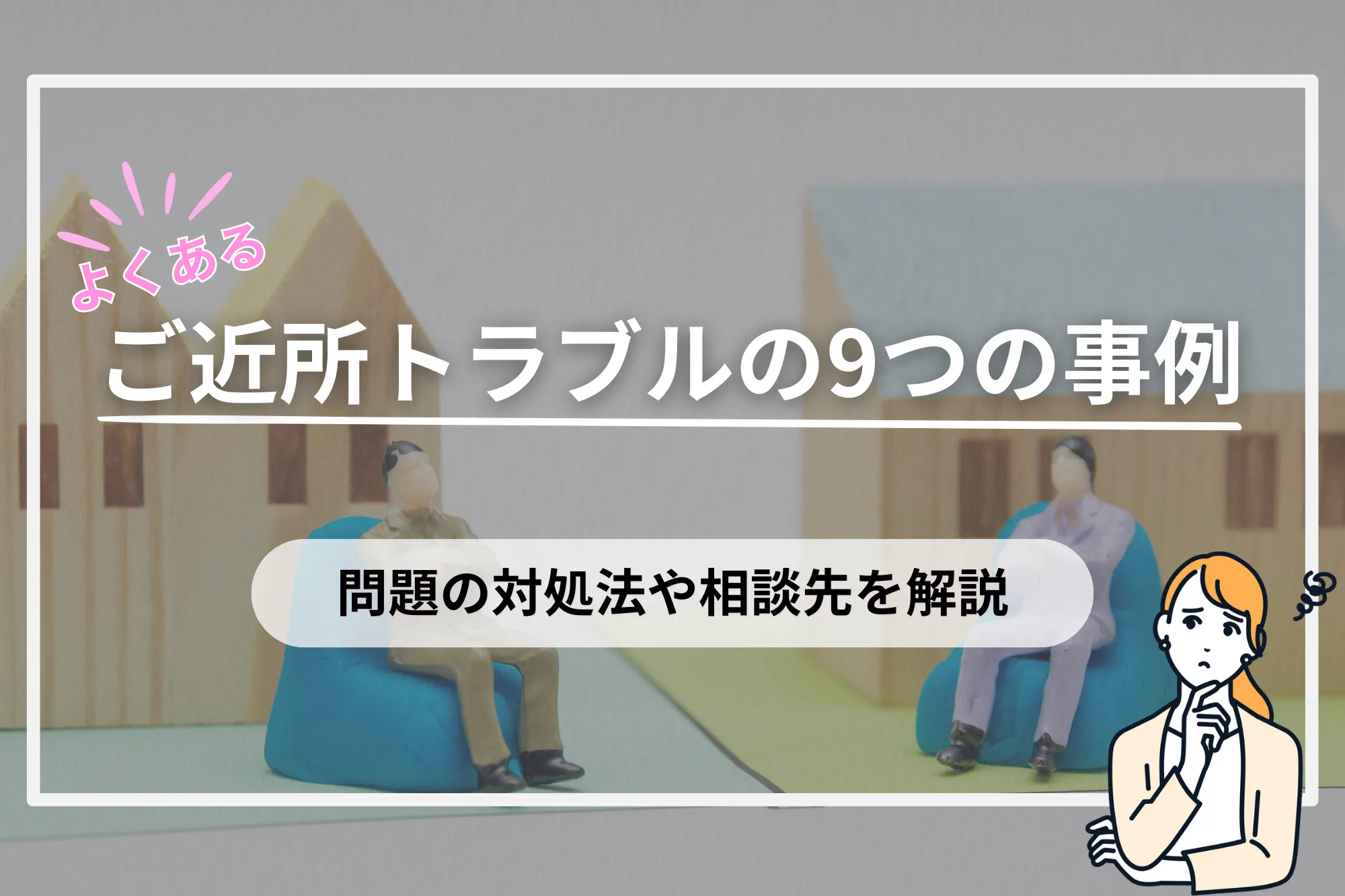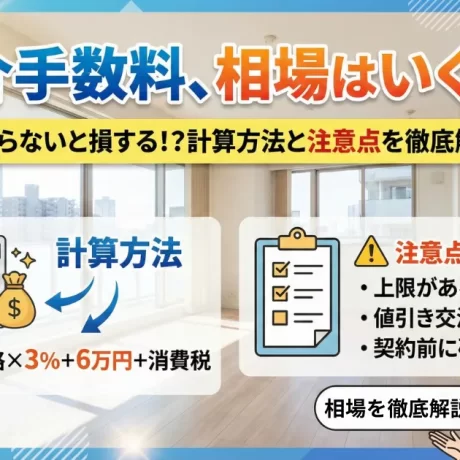一人暮らしでペットを飼うのはやばい?メリットと注意点を解説!
「一人暮らしの住居でペットを飼いたい」「周りの人やネットの声を集めていると不安になった」
そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。確かに、一人暮らしでペットを飼うにはさまざまな課題があります。ただし、しっかりと準備を整えて責任を持って向き合う覚悟があれば、不可能ではありません。
マーケティング・リサーチ会社「クロス・マーケティング」の調査によれば、2024年にペットを飼っている人は全体の28.6%です。
また、賃貸住宅に住む人のうち、すでにペットを飼っている割合は18.2%。今後飼いたいと考えている人も44.5%(2022年度 賃貸契約者動向調査(首都圏)株式会社リクルート)にのぼっており、一人暮らしでのペット需要は年々高まっていることがうかがえます。
この記事では、一人暮らしでペットを飼うことが「やばい」と言われる理由を整理しながら、後悔しないためのポイントを具体的に解説します。
自分の暮らしに本当にペットを迎えていいかどうか、冷静に判断したい方は、ぜひ読んでみてください。
👉スマトリの無料診断はこちら(1分)
参考:【お知らせ】ペットに関する調査(2024年)(クロス・マーケティング)
目次
一人暮らしでペットを飼うのはやばいと言われる5つの理由
一人暮らしでペットを飼うことが「やばい」と言われる理由には、具体的な根拠があります。事前にこれらの課題を理解しておくことで、適切な対策を立てられます。
初期費用や維持費にお金がかかる
ペットを飼う上で大きな負担となるのが経済面です。
アニコム損害保険の2023年の調査によると、年間の平均支出額は犬で約34万円、猫で約17万円、小動物でも約10万円にのぼります。
初期費用として、ケージやトイレ用品で数万円、ワクチンや去勢・避妊手術でさらに数万円かかります。加えて、毎月のエサ代や消耗品も継続的な出費です。
一人暮らしでは収入に余裕がないことも多く、これらの費用を長期的に負担するのは簡単ではありません。特に医療費は高額になりがちで、準備が不十分だと「やばい」と感じる状況になることもあります。
参考:2023最新版 ペットにかける年間支出調査(アニコム損害保険株式会社)
外出や旅行の時間が制限される
一人暮らしの魅力である自由な時間が、大きく制限される点も見逃せません。
たとえば犬は、1日2回・各30分ほどの散歩が必要になる種類が多くいます。
急な飲み会やデート、趣味の予定も、ペットの世話を優先せざるを得ない場面も考えられるでしょう。
旅行や帰省の際にはペットホテルを手配する必要があり、1泊あたり3,000~5,000円の費用も発生します。
さらに、長期間の外出が難しくなることで、出張や研修などキャリアに関わる予定を見送らざるを得ない場合もあるでしょう。こうした自由の制限は、一人暮らしでペットを飼う上で大きな負担となり得ます。
体調不良時にお世話ができない
一人暮らしでは、自分が体調を崩してもペットの世話を代わってくれる人がいないケースが多くなります。
高熱で動けないときや、けがで入院が必要になったときでも、ペットには毎日の食事やトイレの掃除、散歩といったケアが欠かせません。
特に犬は、散歩を怠ると運動不足からストレスがたまり、問題行動につながることもあります。猫の場合も、トイレ掃除を怠れば衛生面の悪化や強いニオイの原因になります。
こうした事態に備えて、家族や友人、ペットシッターなどの協力体制を事前に整えておくことが大切でしょう。準備が不十分なままだと、飼い主にもペットにも負担がかかるおそれがあります。
鳴き声やにおいによる近隣トラブル
集合住宅では、ペットの鳴き声やにおいが原因で近隣とのトラブルが起きやすくなります。
犬の無駄吠えは早朝や深夜に迷惑となり、猫のトイレのにおいが廊下に漏れることもあります。
集合住宅では音やにおいが想像以上に周囲に伝わりやすく、住民からクレームが入る可能性は十分にあるでしょう。
また、毛やトイレの清掃が不十分だと共用部分を汚してしまい、管理会社から注意を受けることもあります。
改善されない場合は退去を求められるケースもあり、新たな引っ越しにかかる費用負担も無視できません。
最後まで責任を持つ覚悟が必要
犬や猫の寿命は10~15年、小動物でも数年と、ペットとの暮らしは長期にわたります。その間に、就職や転職、結婚、出産、親の介護など、ライフスタイルが大きく変わることもあるでしょう。
どのような環境の変化があっても、飼い主にはペットを最期まで世話する責任があります。
たとえ転勤でペット不可の物件に移ることになったり、結婚相手がアレルギーを持っていたりしても、手放すのではなく、解決策を模索する必要があります。
安易に手放す行為は、動物愛護の観点からも許されるものではありません。長期的な責任を引き受ける覚悟があってはじめて、ペットとの暮らしが成り立ちます。
一人暮らしでペットと生活するメリット
一人暮らしでペットを飼うことにはデメリットもありますが、それ以上に多くの飼い主が実感しているメリットもあります。そうした利点を知ることで、ペットを迎える価値をより適切に判断できるでしょう。
寂しさや孤独がやわらぐ
一人暮らしで感じやすい孤独感を和らげてくれることは、ペットを飼う大きなメリットのひとつです。仕事や学校から帰宅した際に、尻尾を振って迎えてくれる犬や、甘えてくる猫がいるだけで心が癒やされます。
特にリモートワークが増えた今、誰とも話さない日でも、ペットがいることで自然と会話が生まれ、精神的な安定につながります。さらに、SNSで写真や動画を共有すれば、ペットをきっかけにした新たな交流も生まれやすく、社会的な孤立の防止にもつながるでしょう。
日常生活のリズムが整う
ペットを飼うと、自然と規則正しい生活が身につきます。たとえば犬は朝晩の散歩が必要なため、早起きが習慣になり、夜更かしも控えるようになるでしょう。猫も食事や遊びの時間がある程度決まっているため、生活にメリハリが加わります。
一人暮らしでは生活が不規則になりがちですが、ペット中心のスケジュールが健康的な暮らしを後押しします。散歩は飼い主の運動不足解消にも効果的です。
また、帰宅時間を調整したり、体調管理を心がけたりするうちに、自己管理能力も自然と高まります。こうした変化は、仕事や私生活にも良い影響をもたらします。
ペットを通じて交流が増える
ペットは、飼い主の社交的なつながりを広げるきっかけにもなります。たとえば、犬の散歩中に近所の人と挨拶を交わしたり、同じ犬種を飼う人同士で情報を共有したりする中で、自然とコミュニティが生まれることもあります。
ペットショップや動物病院、ドッグランなどでも会話が始まりやすく、新たな友人ができることも少なくありません。また、ペット関連のイベントやサークルに参加すれば、趣味を共有する仲間との出会いも期待できます。
特に、新しい土地での一人暮らしでは、ペットが地域とのつながりを築く助けになります。自然なコミュニケーションのきっかけとなり、社会との接点を保つうえでも心強い存在です。
一人暮らしで飼いやすいペットの種類
ペットの種類によって必要な世話の内容や時間、費用が大きく異なります。一人暮らしの環境に適したペットを選ぶことで、飼い主とペット双方にとって快適な生活が叶えられます。
犬

一人暮らしで犬を飼うなら、小型犬が適しています。チワワ、トイプードル、ポメラニアンなどは室内で飼いやすく、散歩時間も中・大型犬より短くて済みます。
小型犬でも1日2回、各30分程度の散歩が必要ですが、体力的な負担は軽めです。しつけがしやすく、無駄吠えの少ない犬種を選べば、近隣トラブルのリスクも抑えられるでしょう。
ただし、犬は社会性が高いため、長時間の留守番がストレスになることも考えられます。なるべく早めに帰宅し、十分にふれあう時間を持つことが大切です。
猫

猫は一人暮らしに最適なペットのひとつです。散歩の必要がなく、留守番にも比較的強いため、忙しいライフスタイルでも飼いやすいでしょう。
室内飼いが基本となるため、交通事故や感染症のリスクが少なく、平均寿命も長めです。トイレのしつけは比較的容易で、爪とぎ対策を行えば賃貸住宅でも問題なく飼えます。
ただし、トイレ掃除は毎日欠かせません。怠るとニオイが強くなりやすく、近隣への配慮が必要です。また、猫によっては夜間に活発になることがあるため、生活音にも注意しましょう。
去勢・避妊手術を受けさせることで、発情やマーキングといった問題行動を防げます。
ハムスター

ハムスターは体長が最大でも約10cmと小さく、限られたスペースでも快適に飼える点が魅力です。初期費用や月々の維持費も比較的安く、経済的な負担は軽めです。
鳴き声が小さいため、集合住宅でも騒音トラブルになりにくく、一人暮らしに向いています。ケージ内での飼育が基本なので、家具や床を傷つける心配もほとんどありません。
ただし、寿命は2~3年と短く、ペットロスの可能性は高めです。また、夜行性のため、回し車の音が睡眠を妨げることもあります。
さらに、気温の変化に弱いため、室温の管理には十分な注意が必要です。
鳥

インコやカナリアなどの小鳥は、鮮やかな色合いや美しいさえずりで飼い主の心を癒やしてくれます。ケージ内で飼えるため、散歩の必要がなく、省スペースでも飼育可能です。
知能が高く、名前を覚えたり、簡単な言葉をまねしたりすることもあり、日常の中でコミュニケーションを楽しめる点も魅力のひとつです。お世話は餌と水の交換、ケージの清掃が中心で、手間も比較的少なめです。
一方で、鳴き声が意外に大きく、特に早朝に鳴く種類もいるため、防音対策は欠かせません。また、放鳥する際は飛び出し防止のため、窓やドアの管理に注意が必要です。
金魚

金魚は最も手間のかからないペットの一つです。毎日の餌やりと週に1~2回の水替えを行えば、健康に飼育できます。鳴き声やにおいがなく、近隣トラブルの心配もほとんどありません。
初期費用は水槽やフィルター、ヒーターなどを含めて数万円程度。水中を優雅に泳ぐ姿は癒し効果があり、日々のストレス軽減にもつながります。
ただし、水質が悪化すると病気にかかりやすくなるため、環境の維持には基本的な知識が求められます。停電時にはフィルターやヒーターが使えなくなるため、電池式のエアポンプを用意しておくなど、事前に備えておくことも大切です。
マンションで飼いやすいペットや、ペットのお世話のコツをさらに知りたい方は以下のページをご覧ください。
ペットを飼う前に知っておくべき注意点
ペット飼育を成功させるためには、事前の準備と計画が重要です。以下のポイントを確認することで、トラブルを未然に防げます。
ペット可物件かどうかを必ず確認する
賃貸住宅でペットを飼う際に最も重要なのは、物件の規約をしっかり確認することです。
「ペット可」「ペット相談可」とあっても、すべてのペットが許可されているわけではありません。犬・猫はOKでも小鳥は不可、小型犬のみ可で中・大型犬は不可など、物件ごとに細かな制限があります。
飼いたいペットの種類や大きさ、頭数を具体的に伝え、事前に許可を得ることが必須です。無断で飼うと契約違反となり、強制退去や高額な違約金が発生することもあります。
退去時の原状回復費用も高額になるケースが多いため、ペット飼育に関する特約条項は必ず確認しておきましょう。
事前に必要なものを準備しておく
ペットを迎える前に、必要な用品をすべてそろえておくことが重要です。犬の場合はケージ、トイレ用品、食器、首輪、リード、おもちゃなど、初期費用として3~5万円程度がかかります。
猫の場合もケージ、トイレ、猫砂、キャリーケース、爪とぎ、キャットタワーなどが必要で、同様に3~5万円程度の予算を見込んでおきましょう。小動物や鳥は適切なケージと専用フードが最低限必要です。
また、近隣への配慮として防音マットや脱臭剤、ペット用カメラなどを準備すると安心です。緊急時に備え、近くの動物病院の場所や診療時間を事前に確認しておくこともおすすめします。
将来のライフプランと照らし合わせる
ペットの寿命は犬や猫で10~15年、小動物でも数年に及びます。その間に起こりうる生活の変化を想定しておくことが大切です。
就職、転職、結婚、出産、親の介護など、さまざまなライフイベントが起こる可能性があり、それぞれの状況でペットの世話を続けられるか事前に検討しましょう。
特に賃貸住宅の場合、転居が必要になった際にペット可物件を見つけられるかが重要です。ペット可物件は数が限られ、家賃も高めに設定されることが多いため、経済的な余裕も考慮する必要があります。
一人暮らしでペットを飼う人のよくある質問
ペットを飼う前に、多くの人が抱く疑問や不安について詳しく解説します。これらの質問への回答を知ることで、安心してペット飼育を検討できるようになるでしょう。
仕事が忙しくてもペットを飼える?
仕事が忙しくても工夫すればペットを飼うことは可能です。ポイントはペットの種類選びと環境整備にあります。猫や小動物、魚類など、長時間の留守番に適したペットを選ぶのが基本です。
犬の場合でも、自動給餌器やペットカメラを活用すれば、外出中も安心して仕事に集中できます。さらに、朝の出勤前と帰宅後に十分なコミュニケーション時間を確保し、休日にはたっぷり遊んであげることで、平日の留守番時間を補えます。
賃貸物件でトラブルにならないためには?
賃貸物件でのトラブルを防ぐには、近隣への配慮と適切な管理が不可欠です。防音対策として床にカーペットやマットを敷き、ペットの足音を和らげましょう。
トイレ掃除はこまめに行い、ニオイが廊下に漏れないよう脱臭剤や空気清浄機を活用することが大切です。また、ペットの毛やフケは定期的に掃除し、共用部分を汚さないよう心がけましょう。
引っ越し時には近隣への挨拶でペットの飼育を伝え、迷惑をかけない配慮をしていることを伝えるのも効果的です。トラブルが発生した場合は速やかに管理会社に相談し、適切に対応しましょう。
体調不良や急な入院のときはどうすればいい?
一人暮らしで特に心配なのが、飼い主の体調不良や急な入院時の対応です。事前に緊急時の預け先を複数確保しておくことが重要となります。
家族や親しい友人にペットの世話を頼めるよう、日頃から関係を築いておきましょう。また、ペットシッターや一時預かりサービスを利用できる施設をあらかじめ調べ、連絡先を控えておくのもおすすめです。
ペットの性格や注意点、普段の世話の方法をまとめたメモを作成し、預け先の人がスムーズに対応できるよう準備しておくことも大切です。
【無料】住まい購入の相談はスマトリがおすすめ!
・仲介手数料最大無料
・氏名や住所の入力不要
・電話やメールの営業なし
スマトリのLINE相談では、AIではなく経験豊富な担当者が対応してくれるので、不動産の購入が初めての人でも安心して利用できます。
気になる物件が既にある方は、仲介手数料無料かどうかをお気軽に判定可能です。
「仲介手数料無料って本当?」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、まずはスマトリのLINE相談を活用してみてください。
まとめ
本記事では一人暮らしでペットを飼うことが「やばい」と言われる理由について詳しく解説しました。
・外出や旅行が制限される
・体調不良時に世話が難しい
・鳴き声やにおいによる近隣トラブル
・最後まで責任を持つ覚悟が必要
確かに課題は多いものの、しっかり準備し覚悟を持てば、ペットは癒しと充実感を与えてくれる心強い存在です。
大切なのは、自分の生活スタイルやライフプランと照らし合わせ、無理なく責任を持って飼えるかを冷静に判断すること。
経済的・時間的な余裕、そして強い責任感があれば、一人暮らしでも素晴らしいペットライフを築けます。
まずは自分に合ったペットを選び、必要な準備を整えてから迎え入れましょう。
適切な環境とケアがあれば、ペットとの暮らしは一人暮らしの質を大きく高めてくれるはずです。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。