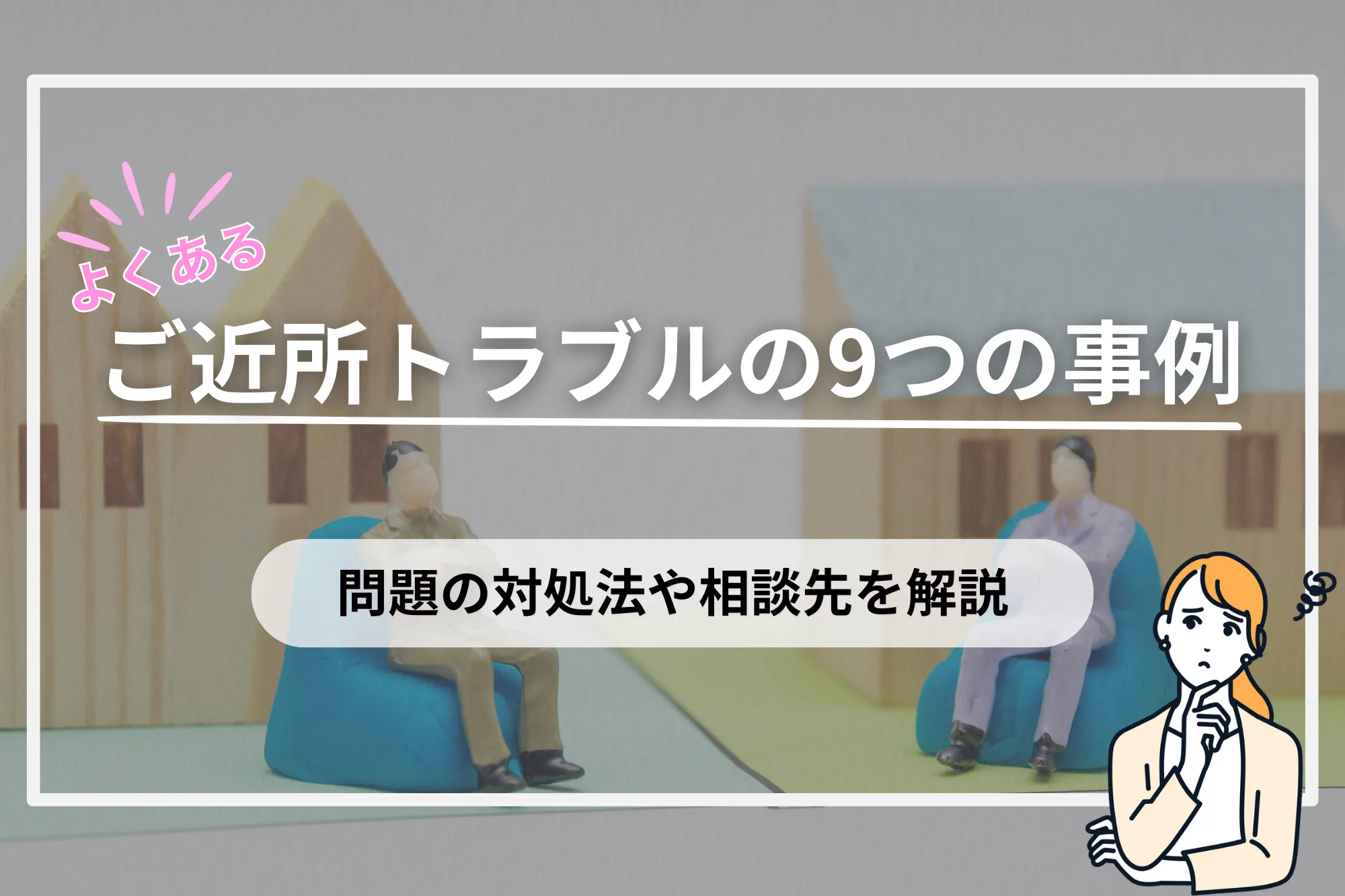マンションで飼いやすいペット7選!お世話のコツや注意点を解説
「マンションでも犬や猫を飼えるのかな?」 「近所迷惑にならないペットは?」 など、マンションでペットを飼いたいと考えている方にとって、どんな種類を選べばいいのか、飼育上の注意点は何かなど、気になる点は多いのではないでしょうか。
この記事では、マンション暮らしに適したペットの選び方から、近隣トラブルを防ぐための具体的な対策まで、ペットとの快適な暮らしに必要な情報を詳しく解説します。
これから初めてペットを飼おうと考えている方はもちろん、すでにペットを飼っている方にとっても参考になる情報が満載です。
マンションでのペット飼育を成功させるためのポイントをしっかり理解して、素敵なペットライフをスタートさせましょう。
👉スマトリの無料診断(1分)
\LINE登録者限定特典あり/
今すぐ無料特典を受け取る
目次
マンションのペット飼育の可否は管理規約で定められている
マンションでペットを飼う前に、まず確認しなければならないのが管理規約です。
ペット可・不可の条件は物件によって異なり、以下のようなパターンがあります。
・完全にペット禁止
・小型犬や猫のみ可能
・檻やケージで飼育する小動物のみ可能
・サイズや種類の制限付きで可能
・飼育可能頭数が決められている
・管理組合への事前申請が必要
ほかにもペットを飼うにあたって上下左右の住戸の同意書が必要な場合や、半年に1度ペットクラブ(※1)主催の獣医師による講義を聞くことが求められるケースもあります。
また、賃貸マンションの場合は、管理規約に加えて使用細則、賃貸借契約書の内容も確認が必要です。
確認について不安がある場合には、不動産会社の担当者に相談するとよいでしょう。
ペットクラブ(※1):ペットの飼い主たちによって運営される組織で、マンションによって組織の有無やその名称は異なる。
マンションで飼いやすいペットの特徴

マンションでペットを飼うには、室内という限られた環境のなかでも快適に過ごせる動物を選ぶことが重要です。
近隣住民にも迷惑をかける心配の少ないペットを選ぶことも大切でしょう。
この項では、マンションで飼いやすいペットの特徴について解説します。
鳴き声や足音が小さいこと
ペットによる騒音は近隣とのトラブルになりやすい問題のひとつです。
マンションは上下階や隣室に音が伝わりやすい環境のため、ペットの鳴き声や足音の大きさには特に注意を払う必要があります。
騒音トラブルを避けるためにも、以下のような特徴を持つペットが適しているといえるでしょう。
・基本的に静かな性格
・夜間に活動的ではない
・体重が軽く、走り回っても大きな音を立てにくい
特に、マンションは大型犬を複数飼うことを禁止しているケースが多くあります。
小動物であり、かつ夜型ではないペットのほうが騒音問題は起きにくいでしょう。
室内飼育に向いていること
マンションでペットを飼うには、猫や小型の犬、ハムスターなどが適しているといえます。
散歩の頻度も少なくてすみ、広い空間を必要としないからです。
また、飼い主が留守のあいだに食べ物以外の物を口に入れてしまったり、いたずらをしてしまったりするケースも考えられるので、ケージで飼えるペットもおすすめです。
ケージがあれば、留守中だけでなく、来客時にもペットが落ち着いて過ごせる場所となります。
ペットも人間もストレスなく生活できるよう、ペットは室内飼育に向いているものを選ぶようにしましょう。
臭いが強すぎないこと
マンション内でペットを飼う際は臭いへの配慮も重要です。
おとなしい小動物であっても、体臭や尿の臭いが強いためにトラブルになることもあります。
トイレのしつけができる、また、トイレの管理が容易でこまめに清掃できる、といった特徴のある生き物がおすすめです。
体臭が比較的少ないペットとしては、カメや観賞魚などがあげられます。
また、臭い対策として消臭剤を置く、こまめに換気をするといった配慮も忘れずにおこなうようにしましょう。
\ペット購入可マンション紹介可能/
中古マンション購入を相談する
マンションで飼いやすいおすすめのペット
マンションでも飼いやすいペットとしておすすめの小動物を7種類ご紹介します。
飼う際の注意点なども解説するので、よく確認したうえでペットを選択するようにしましょう。
小型犬

| 平均寿命 | 10~15年 |
| メリット | ・しつけがしやすい ・飼い主との愛着関係を築きやすい ・飼い主も一緒に運動できる ・比較的寿命が長い |
| 注意点 | ・毎日の散歩が必要 ・すべらないように床にはカーペットを敷く ・においが出るので時々洗ってあげる必要がある ・留守番が苦手 |
犬はひとりでの留守番が苦手なため、はじめは30分程度の短い時間から慣らすようにしましょう。
寂しくないよう、おもちゃなども用意しておくこともおすすめです。
猫

| 平均寿命 | 12~18年 |
| メリット | ・静かで室内飼いに向いている ・散歩の必要が無い ・比較的寿命が長い ・体臭が少ない |
| 注意点 | ・爪とぎ対策が必要 ・高い所に登るので棚の上などに気軽に物を置けない ・毛がよく抜けるのでこまめな掃除が必要 |
壁や家具で爪をとがないように、爪とぎはいくつか用意して数か所に置く必要があります。
また、運動ができるようにキャットタワーや段差がある家具を設置するようにしましょう。
ウサギ

| 平均寿命 | 約8年 |
| メリット | ・あまり鳴かないので室内飼いに向いている ・ケージの中など省スペースでも飼育可能 ・体臭が少ない |
| 注意点 | ・電気コードなどをかじる習性がある ・温度や湿度に注意が必要 ・できるだけ毎日運動させる(30分~2時間程度) |
ケージを置く部屋は、室温20~28℃、湿度40~60%が目安です。
運動させるためにケージから出すときは、電気コードをかじらないよう、カバーをかけるなど対策をしておきましょう。
ハムスター

| 平均寿命 | 2~3年 |
| メリット | ・ほとんど鳴かないので静か ・ケージの中で飼育可能 ・エサ代があまりかからない ・掃除をきちんとすればほとんど臭いがない |
| 注意点 | ・夜行性のため夜中に活動する ・寿命が短い ・聴覚が優れているため、テレビなど大きな音が出る機器の近くにケージを置かない ・湿気が苦手 |
ハムスターは湿気が苦手なため、ケージは風通しがよいところに設置しましょう。
また、寿命が短いため、飼い始めても3年くらいでお別れしなくてはなりません。
子どものペットとしては考慮が必要でしょう。
ハリネズミ

| 平均寿命 | 2~5年 |
| メリット | ・鳴かないので静か ・ケージの中で飼育可能 ・体臭があまりない |
| 注意点 | ・専門の獣医が少ない ・慣れるまでは皮手袋をして世話する必要がある ・夜行性なので世話やコミュニケーションは夕方がよい |
臆病な性格のため、飼い始めの頃は針を立てることが多くあります。
慣れるまでは手袋をしてお世話をしたり、ふれあったりするようにしましょう。
また、野生のハリネズミの主食は虫ですが、野外のミミズやバッタなどはあげないように注意してください。
農薬や除草剤、寄生虫がついている危険があります。
主食にはハリネズミ専用フードを与えるようにしましょう。
観賞魚

| 平均寿命 | 1~10年 |
| メリット | ・音も臭いもほとんどない ・癒し効果が高い ・水槽のインテリア効果がある |
| 注意点 | ・専門医が少ない ・飼育する知識が必要 ・水質の管理が難しい |
観賞魚は低水温に弱い種類が多いため、適した水温を保つ必要があります。
冬はヒーターなどが必要になるでしょう。
また、水温の急変は魚の体調不良を招くため、水換えのときには必ず水温を合わせておこなうようにしましょう。
さらに、飼う環境すべてが整ってから観賞魚を購入する、ということも重要なポイントです。
爬虫類(カメ・トカゲ)

ここではカメとトカゲについて紹介します。
| 平均寿命 | カメ:約30年~50年 トカゲ:約10年 |
| メリット | ・音も臭いもほとんどない ・寿命が長い ・散歩の必要がない |
| 注意点 | ・日光浴が必要 ・専門医が少ない ・トカゲのエサはミミズや昆虫などの生餌 |
爬虫類は変温動物なので、温度が低い時は体温を上げるために日光浴が必要です。
日光浴には、皮膚につく寄生虫や菌類を死滅させたり、甲羅が変形する病気を防いだりする効果もあります。
カメの場合は水から時々上がって日光浴ができるように、水槽内にレンガや大きめの石を陸場として設置しておくようにしましょう。
\ペット購入可マンション紹介可能/
中古マンション購入を相談する
マンションでペットを飼う際の注意点
マンションでのペット飼育は、近隣とのトラブルを防ぐために様々な配慮が必要です。
この章では、しつけや清掃、温度管理といった重要なポイントについて解説し、快適なペットライフを送るためのコツをお伝えします。
ペットのしつけを行う
ペットが騒がしくしたり、物を傷つけたりしないようにしつけは重要です。
特にマンションでは、以下のしつけが求められます。
・無駄吠え
・トイレのしつけ
・基本的な命令への従順性
・来客時の対応
無駄吠えがひどかったり、共用部で粗相をしてしまったりすると他の住民に迷惑をかけてしまいます。近隣トラブルの要因になることもあるでしょう。
また、爪とぎを壁や家具でしてしまうと、修繕に大きな金額がかかることもあります。
しつけとともに壁に布を貼ったり、猫用の「爪とぎ」を用意したりと、しっかり対策をおこなっておくことも必要です。
なお、しつけは子犬や子猫といったまだ小さい時期からおこなうことが重要ですが、自分では難しいという場合はプロのトレーナーに相談することも検討してみましょう。
こまめに掃除する
ペットの毛が溜まってしまうことやにおいを抑えるため、こまめな掃除が欠かせません。
床とトイレはできれば毎日掃除することを心がけましょう。
犬や猫の毛は毎日抜けるので、床は掃除機をかけることをおすすめします。
また、食事スペースの衛生管理も重要です。
食器は毎日洗い、ペットが食べこぼした際にも速やかに清掃するようにしましょう。
ケージや水槽も定期的な清掃をおこない、清潔を保つことにより、においの発生を抑えることが大切です。
騒音や臭いを対策する
ペットの鳴き声やにおいは、近隣トラブルの原因になりがちです。
ペットの騒音対策、臭い対策について以下でみていきましょう。
【騒音対策】
・防音マットの設置
・窓に厚手のカーテンや防音カーテンを取り付ける
・無駄吠えのしつけを徹底する
・おもちゃは音の出にくいものを選ぶ
・爪切りを定期的に行う(爪とぎの音対策)
自分が思っている以上に、無駄吠えや走り回る足音は響いていることがあります。
足音を軽減する防音マットの設置や、防音カーテンの取り付けなど、音が外に漏れにくいよう工夫をしましょう。
また、ペットにあたえるオモチャは音の出ないものにするといった配慮も必要です。
【臭い対策】
・消臭剤の活用
・定期的な換気
・空気清浄機や脱臭機の設置
・トイレの位置や種類の工夫
におい対策は近隣への配慮にもなります。
定期的な換気をおこなうことのほか、においの分子を装置やフィルターを通して分解、除去し、においを消してくれる脱臭機の使用もおすすめです。
ペットのしつけなど、生活上の近隣トラブルの原因を確認しておくことで、あらかじめ対処方法を身に付けておくことが大切といえるでしょう。
温度や湿度の管理を徹底する
ペットの健康管理には、適切な温度や湿度が必要です。
種類や年齢、体格、毛量などによっても快適な環境は異なります。
エアコンや加湿器を使って、ペットが快適に過ごせる環境を整えましょう。
また、直射日光が苦手なペットについては日の当たり具合への配慮、寒さや暑さに弱いペットについては室温調節を欠かさないことなども注意しておく必要があります。
近隣の動物病院を確認する
万が一のときに備え、動物病院を確認しておきましょう。
確認しておくべきポイントは以下のとおりです。
・かかりつけ医の診療時間
・24時間対応の救急病院の場所
・専門医の有無
・休日診療の可否
ペットのケガや病気は、人間と同じでいつ起こるかわかりません。
いざというときに慌てず対応できるよう、動物病院の場所、連絡先、診察時間などを事前に調べておくようにしましょう。
ペットが珍しい生き物だった場合、専門医がいる病院が近くにないケースもあります。
緊急時に頼れる相手を見つける
急な外出や入院などの際、ペットを預かってくれる相手を探しておくと安心です。
親族や友人などに頼むほか、ペットシッターサービス(※1)の利用を検討しておくのもよいでしょう。
また、急にペットのお世話を頼むことになった場合でもスムーズにお願いできるよう、お世話の手順をマニュアル化しておくのもおすすめです。
ペットシッターサービス(※1):ペットシッターが飼い主の自宅に訪問し、飼い主の代わりにペットの世話をするサービス。飼い主が帰ってくるまで食事や散歩トイレや健康管理などをおこなってくれる。
飼育にかかる費用を把握しておく
ペットの飼育にかかる費用を把握しておきましょう。
主な初期費用は以下のとおりです。
・ペットの購入費
・飼育に必要な設備や用品
・予防接種費用
継続的にかかる主な費用は以下のとおりです。
・餌代
・トイレシートなどの消耗品費
・ケガや病気の治療費
なお、アニコムホールディングスの「家庭どうぶつ白書 2023」によると、ペットにかける年間支出額(2022年)は、犬が35万7,353円、猫が16万0,766円となっています。
また、犬・猫ともに平均寿命が延び、高齢による病気などの治療費が増加の傾向にあります。
ペットの購入費だけでなく、飼育にどれだけの費用がかかるのか把握しておくようにしましょう。
参考:犬・猫の平均寿命は更に延伸、高齢犬・猫の診療費も調査
~世界最大規模のペット統計データ集 アニコム『家庭どうぶつ白書2023』公開~(アニコムホールディングス)
\ペット購入可マンション紹介可能/
中古マンション購入を相談する
ペット不可の物件で黙って飼育すると契約違反になる
ペット不可物件で、無断でペットを飼育していることが発覚すると契約違反になり、ペナルティーを受けることになってしまいます。
ペットを手放すか、即座に引っ越す必要が出てくるのです。
罰金が発生することもあるでしょう。
無断でペットを飼育した場合は以下のようなケースが起こり得ます。
・即時契約解除の可能性
・退去要求
・原状回復費用の請求
・近隣トラブルの発生
ペットの飼育は、においや音のほか、ゴミといった思いもよらぬところから発覚してしまうこともあります。
ペット不可の物件では、くれぐれもペットを飼わないようにしましょう。
また、ペット可の物件であっても無断で飼い始めた場合は契約違反となり、トラブルにつながることもあります。
入居後にペットを飼いたくなった場合は、まず管理会社や大家さんへ相談することをおすすめします。
まとめ
この記事では、マンションで飼いやすいペットの紹介と飼う際の注意点について解説しました。
マンションでペットを飼う際の重要ポイントは以下のとおりです。
・管理規約は必須の確認事項
・生活環境に適したペットを選ぶ
・音やにおいなど近隣への配慮
・事前の十分な準備
・責任を持った飼育の実践
ペットとの生活は、日常に癒しと幸福感をもたらしてくれますが、同時に責任も伴います。
人もペットも快適に過ごせるよう、適切な準備と配慮が必要となることに注意しておきましょう。
マンションでのペットの飼育を検討されている方はこの記事を参考にして、ご自身の生活環境に合ったペットを選び、素敵なペットライフをお送りください。
\LINE登録者限定特典あり/
今すぐ無料特典を受け取る
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。