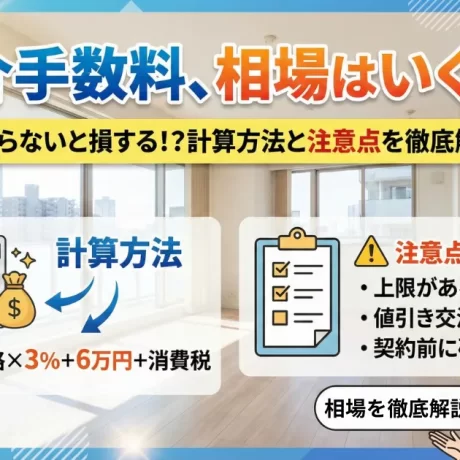マンションの天井高の平均は?天井が高い物件のメリットを解説
「マンションの天井は高いほうが開放感を感じられるのは本当?」「理想の天井高はどのくらい?」など、
天井の高いマンションのメリットについて知りたいという方も多いでしょう。
天井の高いマンションは、開放感を得られるだけでなく、高級感のある部屋を演出することも可能です。
マンションの床面から天井までの高さを天井高といいます。
築年数の古いマンションは天井が低い傾向にありますが、天井高の平均は約2,400㎜で近年では2,600㎜~2,700㎜といった天井の高いマンションが増加している現状です。
天井の高いマンションにはメリットがたくさんありますが、照明器具の電気使用量が多くなる、カーテンやブラインドの費用が割高になることなど、費用面ではデメリットもあります。
まずは、メリット・デメリットを理解した上で天井高の高いマンションの購入を検討しましょう。
これから天井の高いマンションの購入を検討している方や、天井高について知りたいという方は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。
目次
マンションの天井高の基準は建築基準法で定められている
マンションの居室の天井高は、建築基準法で2,100㎜と定められています。
居室の天井の高さが異なる場合は、平均して2,100mm以上の高さでなければなりません。
これは居室のみで継続して使用しないトイレや浴室、納戸、廊下などは対象外です。
築年数が古いマンションの天井高は2,100㎜に近い物件が多いですが、身長の高い人だと天井が近いと圧迫感を感じるので、最近では2,300㎜~2,500㎜の物件が増えています。
長期優良住宅は天井高の認定基準が高く設定されている
長期優良住宅の躯体天井高(※1)は2,650㎜以上が認定基準です。
長期優良住宅とは、長期に渡って良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、長期優良住宅の建築および維持保全の計画書を所管行政庁に申請すれば認定を受けることができます。
長期優良住宅で天井高が2,650㎜以上に設定されている理由としては、多様な間取りに対応して空間利用ができるように高さ方向においてゆとりのある居住空間を確保するためです。
天井高が低いと間取り変更のときに、配管や配線スペースが限定されることで設備の設置する場所の変更が制限され、居住空間が圧迫されます。
建築基準法よりも高く設定することで、良好に過ごせる躯体天井高を確保しています。
躯体(※1)…基礎や壁、柱、床、梁などの建物の骨格部分のことです。
築年数が古い物件の天井高は近年の物件よりも低い傾向がある
旧耐震基準のマンションや築年数が古いマンションは天井高が低いケースが考えられます。
昔は畳で暮らすスタイルが主流で1970年代の男子の30代の平均身長が164cmに満たない状況もあって、築年数が古いマンションは2,200㎜~2,300㎜の天井高が多いです。
天井高については、リフォームで高くできますが、旧耐震基準のマンションや築年数が古いマンションは壁式構造で建てられており、柱や梁が多いのでリフォームしても天井高が変えられないケースもあります。
参考:日本人の平均身長・平均体重の推移
参考:古い中古マンションに多い壁式構造とは?そのメリットとデメリット
天井高を確認する上で知っておきたい建築用語
天井高だけではなく、マンションを建築する際には建築用語が出てきます。
すべてを覚えておく必要はありませんが、覚えておくとリフォームの打合せで役に立つ建築用語も多いです。
ここでは天井高を確認する上で知っておきたい建築用語について解説します。
階の床面から上の階の床面までの高さを指す「階高」
階高は、階の床面から上の階の床面までの高さを指す建築用語です。
天井高に階の天井から上の階の床面の部分が加わります。
たとえば、マンションの3階に住んでいる場合は、自室の床面から4階の床面までと考えるとわかりやすいでしょう。
階高については建築段階で耳にすることが多く、天井高とは違って建築後に変更ができません。
参考:階高とは?天井高との違いや高低差で生じるメリット・デメリットを解説
鉄筋コンクリート造の家の床や屋根の厚みを指す「スラブ厚」
スラブ厚は鉄筋コンクリート造の家の床や屋根の厚みを指す建築用語です。
スラブとは、鉄筋コンクリートの家に用いる構造床のことで日本語では平板や石板を意味します。
木造や鉄骨造に比べて凹凸がなく、平べったいことからスラブと言います。
スラブの種類は以下のとおりです。
・コンクリート床スラブ(土間コンクリートスラブ・構造スラブ)
・二重スラブ
・フラットスラブ
・片持ちスラブ
マンションの床にはコンクリート床スラブ、二重スラブ、フラットスラブなどが使われています。
コンクリート床スラブは遮音性が高く、子供が飛び跳ねるようなドンドンと重量衝撃音に対して効果を発揮します。
スラブ厚は120㎜~300㎜までありますが分譲マンションだと180~250mm程度です。
スラブ厚が大きくなるほど遮音性は高くなりますがその分コストが上がります。
参考:スラブとは?スラブ厚・種類・鉄筋コンクリート造の建築用語
スラブから内装天井を離して仕上げる「二重天井」
スラブから内装天井を離して仕上げるが二重天井です。
二重天井は、上の階の床から下地枠を吊り下げて天板を貼り付けて仕上げます。
天井裏ができることから、そのスペースを利用してリフォームで天井高を高くできます。
一方で、天井に直接クロスを貼って仕上げるのが直天井です。
二重天井と直天井は見た目では判断が難しいですが、コツコツとたたくと見分けることができます。
二重天井は空洞のような音がしますが、直天井はコンクリートの感触がします。
直天井はリフォームで天井高を上げることができないので購入する際には注意しましょう。
参考:二重天井はどんな構造?直天井との違いやメリットとデメリットを解説
天井高が高いマンションの5つのメリット
天井高が高いマンションは天井高の低いマンションと比べて、空間の解放感や部屋が広く見える点などメリットが多いです。
天井高の高いマンションのメリットを理解しておけばマンションの購入を検討する際に非常に役に立ちます。
ここでは、天井高が高いマンションの5つのメリットについて解説します。
空間の開放感が生まれること
天井高の高いマンションの一番のメリットは空間の解放感が生まれる点です。
天井高が低いと上部から圧迫感があって息苦しさを感じます。
身長が高い人や成長期の子供だと閉塞感を感じることで生活にも悪影響が出る可能性もあります。
特にリビングなど多くの人が集まってくつろぐ場所の天井高は高い方がよいでしょう。
部屋のインテリアの自由度が高いこと
天井高が高いことで部屋のインテリアの自由度が高まります。
天井が高いとでデザイン性の高いシャンデリアや機能性の高いシーリングライトなどのボリュームのあるインテリアの設置が可能です。
また、天井が低い、梁があるといった場合は、高さのある家具や冷蔵庫などの家電製品を設置できませんが、天井が高い場合は高さを気にせずインテリアを設置できます。
充分な収納スペースを確保できること
天井高を高くすることで充分な収納スペースを確保できます。
天井高が低いと余分なスペースが取りにくく、家具やカラーボックスなどを置く必要があるでしょう。その結果として、部屋が狭くなってしまいます。
一方で、天井が高ければ壁全面を利用した壁面収納棚や壁の上部に棚を設置できるので、収納の確保に加えて
部屋を広く使うことが可能です。
自然光を効率的に取り入れられること
天井高が高いと自然光を効率的に取り入れることができます。
天井高の低いマンションの場合は、日中は室内に日差しも入りにくく、1階などの低層階では湿気などによるカビも気になるところです。
天井高が高いとサッシも高さのあるものを使用することで開口部が広くなって自然光が入りやすくなるので気持ちよく快適な生活を送れます。
高級感のある部屋を演出できること
天井高が高いと高級感のある部屋を演出することも可能です。
天井が低いと電気が近くなるのでので、明るくて落ち着かないといった方もいるでしょう。
一方で天井が高いと豪華なシャンデリアや背の高い海外製の家具などを設置することができ、天井や側面に間接照明などを使えば落ち着いた雰囲気の部屋を作れます。
天井高が高いマンションの4つのデメリット
メリットの多い天井高の高いマンションですがデメリットはあります。
特に、電気代やカーテン、ブランドの費用など天井高が低いマンションと比べるとお金がかかる点には注意が必要です。
ここでは天井高が高いマンションの4つのデメリットについて解説します。
照明器具の電気使用量が多くなること
天井高が高いと照明器具の電気使用量が多くなります。
なぜなら、天井が高いと床との距離が長くなり、強い光で照らす必要があるので、電力量の高い照明器具を設置する必要があるからです。
また、高級感のある部屋を演出するために豪華なシャンデリアなどを使うと通常の電球が使えない場合があるのでよりコストがかかります。
部屋の高い位置にあるものを掃除しづらいこと
部屋の高い位置にある照明器具や棚など部屋の高い位置にあるものは掃除がしづらいです。
天井だけでなく壁も高くなっているので掃除する範囲も広くなります。
背が高ければある程度対応できますが背が低いと脚立などを活用して掃除をしないといけません。
また、料理の臭いや煙が充満しやすく、換気に時間がかかるのもデメリットです。
カーテンやブラインドの費用が割高になること
天井高が高いとカーテンやブラインドの費用が割高になります。
カーテンやブラインドは、既製品であれば180cm~200cmが多く、天井高が高いと使えません。
天井高の高さに合わせて220cm以上を作るとなるとオーダーメードをする必要があるので費用が割高になるというわけです。
家具の交換に費用や時間がかかること
天井高が高いと家具の交換に費用や時間がかかることもあります。
天井の高さに合わせて背の高い家具を設置している場合、玄関から家具を出し入れできないケースも多いです。
その場合、玄関の扉を外す、ベランダから出し入れするといった方法を取らないといけません。
家具を壊して搬出するという方法もありますが、いずれにしても費用と時間がかかります。
最後に
今回は、天井高のマンションの基礎知識やメリット・デメリットについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
天井高の高さはマンション選びにおいて重要なポイントのひとつです。
開放感や高級感のある部屋や快適な生活を送りたいという人にとっては天井高の高いマンションはメリットが多いですが、コスト面や掃除のしづらさなどデメリットも理解しておく必要があります。
マンションを購入するにあたって、快適さやコストなど何を重視するかを明確にしておけば自分に適した天井高のマンションを選ぶことができます。
また、中古マンションを購入する場合はリフォームで天井高を変えられますが、築年数が古いと直天井や梁で工事ができないこともあるので注意しましょう。
これからマンションの購入を検討している人は、天井高の高いマンションのメリット・デメリットを把握して自分に合った物件を購入してください。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。