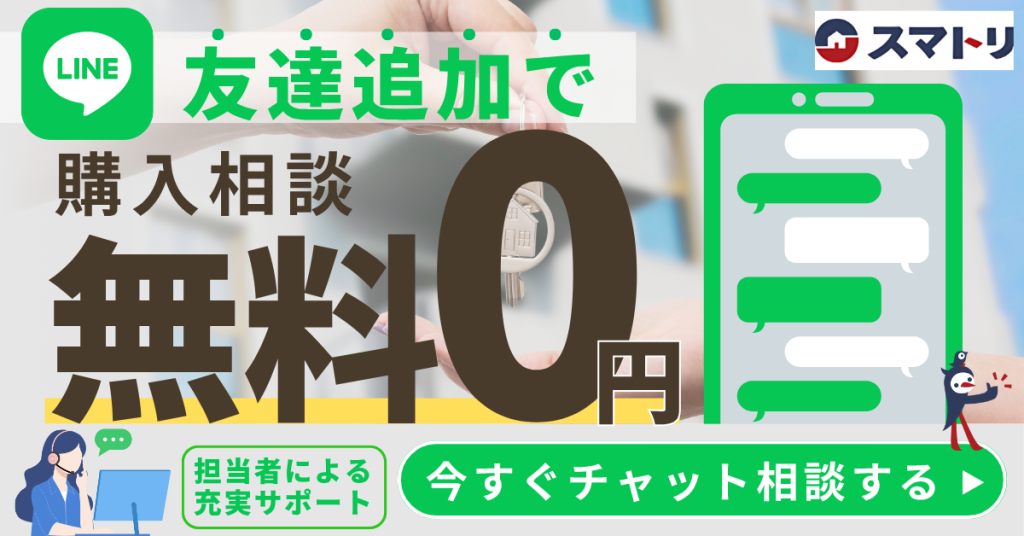坪単価とは?単価が変動する4つの要素と確認する際の注意点を解説
「ハウスメーカーに坪単価で話をされたがよくわからない」「坪単価の計算方法を知りたい」など、マンションや戸建てを購入する際に、商談の中で坪単価といった用語を耳にした人も多いでしょう。
多くの国では面積を計測する場合は、㎡を使いますが、日本では、古くから土地や建物の面積を表す際に、坪という単位が使われてきました。
坪単価とは、1坪(約3.3㎡)にかかる建築費用のことです。
不動産や建築業界では、広さを測る基準として「坪」が根付いていたため、今でも売買価格や建築費用を計算する際に「坪あたりの価格」を算出する習慣が残っています。
坪単価は、建物の構造や形状、設備のグレードなどによって変動します。
注文住宅を建築する際は、依頼するハウスメーカーや工務店によって坪単価が大きく変わるので、依頼する際には事前に確認しましょう。
また、建築コストは、坪単価×家の広さだけでなく、建物本体以外にも費用がかかる点には注意が必要です。
これから注文住宅を建てたいという人や不動産を購入したいという人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
目次
坪単価とは1坪(約3.3平米)当たりの建築費用のこと
1坪は、約3.3㎡で畳の大きさでいうと約2畳分です。
坪単価とは、戸建てなどの建物を建築する際に、1坪にかかる建築費用のことを言います。
他の国では、メートル法に基づいて㎡単価が使われますが、日本では、江戸時代以前から土地や建物の面積を表す単位として坪が使われており、不動産関連の業界においては現在でもその習慣が残っています。
坪単価は、以下の計算式で算出が可能です。
【坪単価の計算式】
例えば、物件の坪数が30坪で建築費用が1,500万円であれば坪単価は50万円、物件価格が3,000万円であれば坪単価は100万円となります。
2階建てや3階建ての場合は、すべてのフロアを合計して坪数を算出します。
現在では、不動産関連の広告を見ると、㎡単価と坪単価が併記されているケースも増えており、坪単価を把握することで物件の広さがイメージしやすくなるでしょう。
坪単価の価格相場
坪単価は、マンションや注文住宅など、住居の種類によって異なります。
住宅金融支援機構が公表している「フラット35利用者調査(2023年度)」のデータを利用し、さまざまな坪単価の価格相場の算出できます
例えば、マンションの場合は、購入価格の平均価格が5245.4万円、住居の平均面積が66.2㎡(20.6坪)なので、物件の坪単価は、254.6万円です。
注文住宅であれば、建設費の平均額が3861.1万円、住居の平均面積が119.5㎡(約36.1坪)なので、建築費用の坪単価は106.95万円と計算ができます。
依頼するハウスメーカーや工務店によって、使う設備やグレードが違うので、あくまで平均値として参考にしましょう。
参考:フラット35利用者調査2023年度(住宅金融支援機構)
坪単価の計算に含まれるもの
坪単価の計算に含まれるものは、算出する範囲や対象によって異なります。
例えば、建物を建築する費用の坪単価を算出する場合、工事の費用以外にも設計や人件費が必要です。
・本体工事費(基礎、構造、内外装など)
・付帯工事費(外構、給排水設備、空調設備など)
・設計・人件費
建売や土地付きの注文住宅を購入する際には、物件価格は建物+土地の価格となるので、建築にかかる費用の坪単価を計算したいのであれば、建物価格のみを確認して計算をする必要があります。
どの指標の坪単価を算出したいのかを明確にし、使うデータを正確に選びましょう。
坪単価別で見る注文住宅の特徴
注文住宅は、依頼するハウスメーカーや工務店によって、ローコストやフルオーダーといった特徴があります。
使用する工法や資材、設備が違うので、建築にかかる費用の坪単価もそれぞれ異なります。
注文住宅を建築する際には、予算に合わせた選定が重要です。
注文住宅の特徴によって、建築にかかる坪単価がどのくらい必要になるかを把握しておくことをオススメします。
ここでは、坪単価別で見る注文住宅の特徴について解説します。
坪単価40~60万円:ローコスト
ローコスト注文住宅は、建物の構造は木造が中心で、コストを抑えた仕様、設備が特徴です。
全国展開しているハウスメーカーが多く、部材の大量発注や効率的な工法を採用し、原料費や施工費を削減することでローコストを実現しています。
建売住宅と比べると自由度は高いですが、資材や設備の選択肢が限られることが多く、あまり複雑な間取りは選べないケースもあります。
坪単価60~80万円:ミドルクラス
ミドルクラスの注文住宅は、ローコスト注文住宅と比べると、設備や間取りの自由度も増し、デザイン性も高いのが特徴です。
壁紙や床材などの資材やキッチンなどの設備、外壁などの選択肢も広がり、依頼者のこだわりが反映しやすいと言えます。
注文住宅として、こだわった作りにしたい場合は、ミドルクラス以上のハウスメーカーを選ぶ必要があるでしょう。
坪単価80~100万円:大手ハウスメーカー
大手ハウスメーカーの注文住宅は、ブランド力やお客様の理想を実現する技術力の高さだけでなく、品質管理や施工管理の充実しているのが特徴です。
耐震性能も高く、アフターサービスも万全なので、安心して住める家が建てられます。
ホームセキュリティやスマートハウスなどの最新の設備も導入がしやすいでしょう。
坪単価100万円以上:鉄骨造・フルオーダー
フルオーダーの注文住宅は、鉄骨造が多く、設計の自由度が非常に高く、依頼者の希望を反映したオーダーメイドの家づくりが特徴です。
高耐久、高性能な資材を使用し、間取りやデザインも自分好みに変更できるので、理想の住空間が作れます。
初期費用は高くなるが、耐久性やメンテナンス性に優れており、売却時も資産価値の減少が少なく、長期的な視点で考えると資産性は高いと言えるでしょう。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
坪単価が変動する4つの要素
構造を鉄骨造にしたり、グレードの高い設備を採用したりすると、費用が増えるので建築にかかる費用の坪単価は上がります。
一方で、大手ハウスメーカーよりも、地元の工務店に依頼したほうが、建築にかかる費用の坪単価は下がります。
建築にかかる費用の坪単価が変動する要素は、大きく分けて4つです。
ここでは、坪単価が変動する4つの要素について詳しく解説します。
建物の構造
建物の構造は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3つです。
建築にかかる費用は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順番で高くなります。
注文住宅においては、木造を採用しているケースが多く、鉄骨造、鉄筋コンクリート造は、建築にかかる費用が大幅に増加するので、資金に余裕がないと難しいでしょう。
2024年の全国の構造別の建築にかかる費用の坪単価は、鉄筋コンクリート造で約122万円、鉄骨造で約100万円、木造で約73万円です。
建物の形状
平屋や二階建て、三階建てや一般的な形の家、複雑な形の家など、建物の形状によっても建築にかかる費用の坪単価は変わります。
平屋と二階建てを比較すると、工事費の高い基礎工事と屋根工事は同じなので、建築にかかる費用の坪単価は二階建てのほうが安くなります。
三階建ては、基準が変わって構造壁が増えるので、平屋よりも坪単価が高くなるケースが多いです。
また、複雑な形の家を作るとなると構造計算も大変なのでより高くなります。
デザイン面では不満があるかもしれませんが、二階建ての四角い建物を建てると坪単価を抑える方法と言えるでしょう。
設備のグレード
注文建築で家を建設する場合は、設備にこだわりがある方や条件の良い家で暮らしたいという方も多いでしょう。
設備のグレードは、最新の良いものを使えば使うほど、建築にかかる費用の坪単価は上がります。
特に、キッチンや浴室など水回りの設備は、一流メーカーや海外メーカーの設備を入れると、数百万円かかるケースもあります。
設備にお金をかけすぎて、建物と釣り合わないといったことがないように、設備は建物とのバランスを考えて選びましょう。
ハウスメーカー
注文住宅を建てるにおいて、ハウスメーカー選びは重要なポイントです。
大手ハウスメーカーは、ブランド力や信頼性の高さがあり、安心して任せられますが、一般のハウスメーカーや工務店に依頼するよりも坪単価は高くなります。
価格を抑えようと、地場のハウスメーカーに依頼して、思った通りの家ができないとなると、注文住宅で建てる意味がなくなってしまいます。
ハウスメーカーによって、デザイン面が優れている、よい設備が手配できるなど、得意な部分は違うので、自分の要望に合うハウスメーカーを探して依頼するとよいでしょう。
坪単価を確認する際の注意点
建築にかかる費用以外にも、坪単価に影響を与える要素はあります。
建築にかかる坪単価は、建築にかかる費用÷物件の坪数で計算できますが、建築以外にかかるコストやハウスメーカーによって坪単価は異なる点には注意が必要です。
ここでは、坪単価を確認する際の注意点について解説します。
坪単価×家の広さでは建設できない
注文住宅は、坪単価×家の広さでは建設できません。
なぜなら、建物を建てるためには、建築以外にかかる費用があるからです。
例えば、建物を建てるために必要な設計費、建物以外の庭や外構費などは、建築にかかる費用の坪単価とは別の計算になります。
他にも、地盤改良や地盤の補強工事が必要場合も別途費用がかかります。
建物本体以外の費用を確認しておく
注文住宅を建てる前に、建物本体以外の費用を確認しておくことが重要です。
建物本体以外にかかる費用については、以下のようなものがあります。
地盤改良費:土地が弱い場合は補強工事、土壌汚染がある場合は浄化工事
外構費:庭・駐車場・フェンスといった建物以外の設備
諸費用:税金、建築確認申請費、保険料など
建物本体以外に費用だけでも、数百万円~数千万円かかるケースもあります。
建築にかかる費用の坪単価だけでなく、トータルでいくら必要かを計算したうえで、注文住宅を建てるための予算を計画しましょう。
坪単価はハウスメーカーによって異なる
ハウスメーカーによって、建築にかかる坪単価は異なります。
なぜなら、ハウスメーカーごとに標準仕様や設計の考え方や材料・工法が違うからです。
ハウスメーカーが行うプレハブ工法の場合は、コストを抑えられますが、職人による施工が中心の在来工法であればコストは上がってしまいます。
また、大手ハウスメーカーであれば、広告・営業費やアフターサービスの充実度も建築コストに含まれるので坪単価は高くなる傾向にあります。
コスト面も重要ですが、予算内で自分の夢を実現してくれるハウスメーカーを選ぶとよいでしょう。
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
まとめ
今回は、注文住宅を建てる際に重要な坪単価について、計算方法や変動する要素、確認する上での注意点などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
注文住宅を建築する際には、坪単価の知識がなくても問題はありませんが、知識があると共通言語としてハウスメーカーとスムーズな商談が可能です。
建物構造・形状、設備のグレードや選ぶハウスメーカーによって変動することを理解しておけば、どこを重視すればよいかがわかるので、予算を計画する際に役立ちます。
また、坪単価を確認する際に、建物本体以外の費用を確認しておくことも重要なポイントと言えます。
建築にかかる坪単価が安いからといってハウスメーカーを決めると、他の費用が予想以上にかかって、最終的に予算オーバーしてしまったというケースも多いです。
坪単価だけに惑わされず、トータルでかかる費用を確認して進めることで、予算オーバーすることなく、理想の注文住宅を建てられるでしょう。
これから注文住宅を建てる人は、この記事を参考に、ハウスメーカーと協力して、理想のマイホームを手に入れていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。