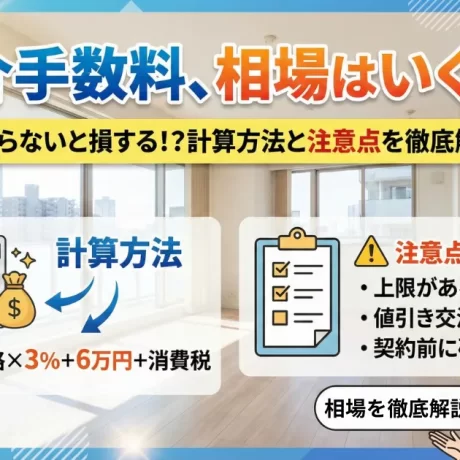住宅ローン控除はいつまで受けられる?令和7年度の改正点を徹底解説
「マイホームを購入したいけれど、住宅ローンの負担が気になる…」「子育て世帯は控除額が違うって本当?」そんな疑問や不安を抱える方は多いのではないでしょうか。
第10回となる今回、そのような悩みを解決するために紹介するのが「住宅ローン控除」制度です。
1972年の制度開始以来、定期的な見直しを重ね、現在は最長13年間にわたり税負担を軽減できる制度として定着しています。
令和7年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯への支援拡充、省エネ性能基準の厳格化などの延長措置が実施されました。
本記事では、住宅ローン控除の基本的な仕組みから最新の改正内容、具体的な控除額のシミュレーション、申請手続きまで、制度活用に必要な情報を詳しく解説します。
今回で最後になるので、ぜひ最後までお読みいただき、住宅購入の参考にしてみてください。
目次
住宅ローン控除とは
「住宅借入金等特別控除」は、一般的に住宅ローン控除や住宅ローン減税として知られています。
1972年に設けられた「住宅取得控除」から制度がスタートしており、この制度により住宅ローン返済者の負担軽減が図られました。
制度の見直しは定期的に行われ、住宅ローン控除の適用期間は13年間に設定されています。
住宅ローンの年末残高と住宅購入価格のどちらか低い方の金額に、0.7%を掛けた金額が控除対象です。
特例対象の子育て・若年夫婦世帯向けの措置と、特例に該当しない世帯の借入限度額は以下の通りです。
| 特例対象の子育て・若年夫婦世帯 | |||
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
| 認定住宅 | 5,000万円 | 13年 | 0.70% |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 13年 | 0.70% |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 13年 | 0.70% |
| 特例に該当しない世帯 | |||
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
| 認定住宅 | 4,500万円 | 13年 | 0.70% |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 13年 | 0.70% |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 13年 | 0.70% |
適用期間は令和7年12月31日まで
令和4年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限は令和3年から令和7年まで延長されることが決定しました。
省エネ性能基準を満たす新築住宅については、所得税の控除期間が10年から13年に延長されています。
この改正の背景には、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの促進があります。
地球環境問題が深刻化する状況下において、住宅分野においても環境負荷の低い建物への移行が求められているためです。
住宅購入時の税制優遇措置は、住宅選びに大きな影響を与える要因です。
そのため政府は、省エネ性能の高い住宅を控除対象とすることで、環境配慮型住宅の普及促進を目指しています。
なお、この制度改正には、消費活動が低迷している経済情勢を考慮した景気対策としての側面もあります。住宅購入の支援を通じ、経済活性化への効果も期待されています。
対象期間は10年もしくは13年
住宅ローン控除を受けられる期間は、基本的に10年間に設定されていました。
ただし、一定の条件を満たした場合に限り、特例措置として13年間まで延長される仕組みとなっています。
特例措置の適用には、物件の契約時期や入居時期などが定められた基準に適合する必要があります。
改正された住宅ローン控除制度では、住宅の種類によって控除期間が異なるため注意が必要です。
新築住宅や、不動産会社による買取再販物件(一定基準を満たすもの)の場合、控除期間は13年間です。
一方、通常の中古住宅の控除期間は10年間になります。
2024年以降に入居予定の方は、住宅が省エネ基準に適合している必要があります。
基準を満たさない場合、控除期間は13年ではなく10年に制限されるので注意してください。
中古住宅の購入方法によっても控除期間は変動します。
個人から中古住宅を不動産会社の仲介で購入する場合は、買取再販物件とは異なり、控除期間は10年間です。
省エネ性能に関係なく、10年間の控除期間が適用されます。
令和7年度の税制改正のポイント
住宅ローン控除の制度内容が令和6年度の税制改正大綱で見直されることになりました。
改正の主な内容としては、子育て世帯への支援拡充、住宅条件の見直し、そして床面積基準の緩和措置が含まれることです。
以下では、各改正内容を具体的に解説します。
子育て世帯や若者夫婦世帯の支援を強化
改正される住宅ローン控除では、世帯の収入制限に加え、子育て世帯や若い夫婦に対する優遇策が設けられています。
子育て世帯、若者夫婦世帯として優遇措置の対象となるには以下の条件のいずれかを満たさなくてはいけません。
令和7年度(2025年)の税制改正では、前年(令和6年度)に実施された住宅ローン減税の優遇措置が1年間延長されました。
具体的には、19歳未満の子どもがいる世帯や40歳未満の夫婦世帯が2025年中に新築住宅等へ入居する場合、住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置が従来どおり適用されます。
長期優良住宅・低炭素住宅では上限5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円までローン残高が控除対象となります。この延長措置により、該当する世帯は前年同様の減税が利用できます。
1. 19歳未満の子どもがいること
2. 夫婦のどちらかが40歳未満であること
住宅ローンの控除対象借入金額の上限は、2024年から引き下げが実施される予定でした。
しかし、
子育て世帯と若者夫婦の世帯に限り、引き続き2023年までの限度額が維持され、2025年についても同様の措置が検討されています。
住宅の種類による控除対象借入金額の上限差は以下の通りです。
| 住宅の種類 | 子育て・若夫婦世帯とその他世帯の差額 |
|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 1,000万円 |
省エネ基準に適合しない新築・再販住宅は控除の対象外
令和6年以降の住宅ローン控除は、『省エネ基準適合住宅』以上の性能を持つ物件のみが対象となります。
この変更は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた日本の住宅政策の一環です。
令和7年からは、全住宅に省エネ基準適合が義務付けられる予定です。
住宅ローン控除の基準改正は、その前段階として位置付けられています。
経過措置として、以下の条件を満たす住宅については、省エネ基準未満でも控除対象になります。
1. 令和5年12月末までに建築確認を受けた住宅
2. 令和6年6月末までに竣工が完了した住宅
令和6年から7年に入居する場合の控除内容は以下のとおりです。
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 住宅区分 | 性能区分 | 借入限度額 | 年間控除額 | 控除総額 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築・買取再販 | ①長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 | 13年 |
| 新築・買取再販 | ②ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 | 13年 |
| 新築・買取再販 | ③省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21万円 | 273万円 | 13年 |
| 既存住宅 | 上記①②③の基準適合 | 3,000万円 | 21万円 | 210万円 | 10年 |
| その他 | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 | 10年 |
省エネ性能が高い住宅ほど控除額が大きくなる仕組みが設けられ、環境配慮型住宅の普及が促進されています。
新築住宅の床面積要件40㎡以上の緩和措置が延長
住宅ローン控除を受けるための床面積要件は、原則として50㎡以上と定められていますが、新築住宅を購入する場合で、以下の条件を満たす場合には例外が適用されます。
1. 年間所得1,000万円以下であること
2. 床面積が40㎡以上50㎡未満であること
令和6年度の税制改正により、床面積要件の緩和措置における建築確認申請期限が令和6年12月31日まで延長されました。
したがって、令和6年末までに建築確認を取得した新築住宅で上記の条件を満たした場合、住宅ローン控除を利用できます。
この床面積要件の緩和措置は、子育て世帯や若者夫婦世帯といった特例対象者に限定されないため、幅広い層が活用できる制度です。
住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除には、共通する基本的な要件があります。
年間合計所得が2,000万円以下であり、住宅ローンの返済期間は10年以上(一部5年間の緩和措置あり)です。
対象となる物件は自己居住用の住宅に限定され、別荘や賃貸用の物件は控除対象外です。
床面積については50㎡以上が基準ですが、年間所得が1,000万円以下の方については40㎡以上の物件も対象となります。
また、自営業など事業用と併用する住宅の場合は、居住部分が床面積の半分を超えていることが条件になります。
これらの基本条件に加えて、住宅の取得方法によって個別の要件を満たすことが必要です。
・新築住宅
・買取再販住宅
・中古住宅
・リフォーム・増改築
新築住宅
新築住宅で住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
入居に関する要件として、契約者本人が住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居を開始し、同年の12月31日まで居住を継続することが必要です。
なお、契約者本人が単身赴任となる場合でも、家族が6ヶ月以内に入居し、同年の12月31日まで居住を継続すれば控除は適用されます。
特例との併用制限については、住宅の譲渡に関する他の特例と住宅ローン控除を同時に利用できません。
具体的な例には、以下のようなものがあります。
・3,000万円特例(住宅の譲渡所得から最大3,000万円を控除)
・長期譲渡所得の課税特例(10年超保有住宅の譲渡時の税額軽減)
これらの特例を利用した場合、その適用時期が以下の期間に該当する場合、新築住宅の住宅ローン控除は受けられません。
・居住開始年とその前2年間
・居住開始年の翌年から3年以内
買取再販住宅
買取再販住宅とは、不動産業者が中古住宅を購入し、リフォームやリノベーションを実施した後に販売する物件です。
この住宅タイプで住宅ローン控除を利用するには、新築住宅の条件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
【買取再販の基本要件】
1. 宅地建物取引業者による取得から販売までが2年以内であること
2. 取得時点で築10年以上経過している住宅であること
3. 過去に居住用として使用された実績があること
【建物の性能要件】
1. 1982年1月1日以降の建築物件、または耐震基準適合証明を受けた住宅であること
2. リフォーム工事費用が物件価格の20%(上限300万円)以上であること
3. 大規模修繕や耐震性能向上のための工事が実施されていること
買取再販住宅は、適切な改修により新築同等の借入限度額が認められます。
ただし、要件が詳細に定められているため、購入前に販売業者への確認が重要です。
中古住宅
中古住宅の場合の住宅ローン控除の適用には、新築住宅の基本条件に加え、居住実績と建築時期に関する以下の要件が必要になります。
1. 過去に居住用として使用された実績がある住宅
2. 1982年1月1日以降に建築された住宅、または耐震基準適合証明を受けた物件
2022年度の税制改正により、築年数の制限が撤廃され、新耐震基準(1982年以降)への適合を基準とする仕組みに変更されました。
この改正により、築年数が古くても性能の高い中古住宅であれば、控除対象となりやすくなっています。
1981年以前の建築物件でも、耐震基準適合証明書と既存住宅性能評価書の提出により控除を受けることは可能です。
ただし、これらの古い建物は現行の耐震基準を満たすことが難しく、実際の適用は容易ではありません。
リフォーム・増改築
リフォームや増改築費用も住宅ローン控除の対象です。
新築・中古住宅の基本条件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
【基本要件】
1. 契約者本人が所有・居住する住宅の改修であること
2. 工事費が100万円以上で、半分以上を居住部分の改修に使用すること
3. 工事完了から6ヶ月以内に入居し、年末まで居住を継続すること
適用範囲は、居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所など住居の主要部分です。
大規模工事を除き、省エネ改修、バリアフリー化、耐震改修のいずれかの目的を含む必要があります。
ただし、以下の場合には住宅ローン控除の対象外となるので注意が必要です。
1. 単身赴任は例外として認められるが、両親名義の住宅改修は対象外になる
2. 控除期間は最大10年間と、住宅購入時より短くなっている
住宅ローン控除額のシミュレーション
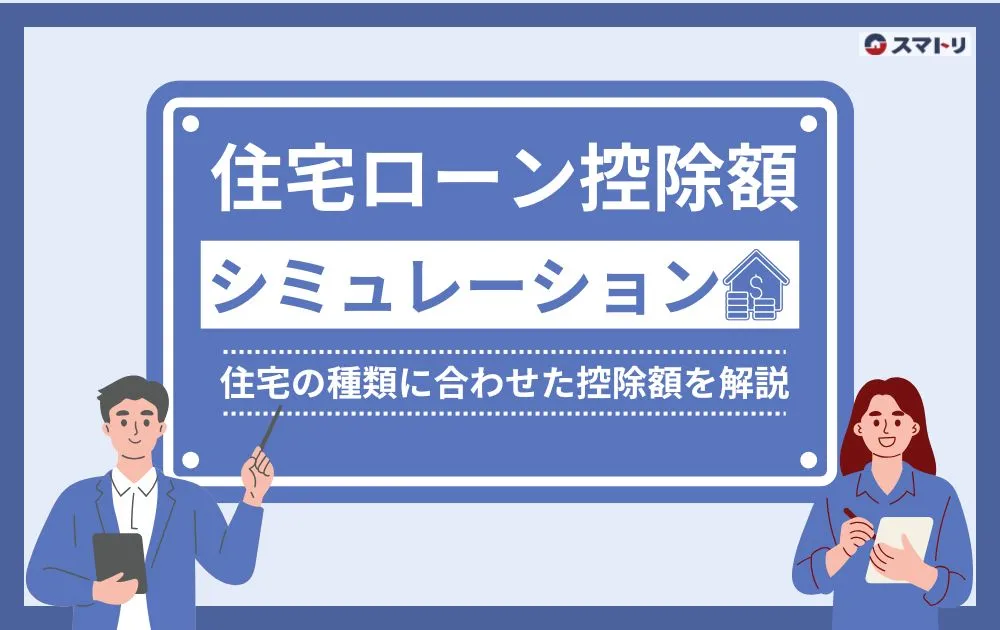
住宅ローン控除が適用された場合のさまざまなシミュレーションを、以下に表としてまとめました。
ぜひ、参考にしてみてください。
2024年〜2025年入居の控除額シミュレーション
次の表は2024年から2025年に入居する場合の住宅ローン控除の概要です。
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 対象の住宅 | 借入限度額 (万円) | 控除率 | 各年の控除額上限 (万円) | 控除合計額(13年間) (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 5000 | 0.7% | 35.0 | 455.0 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4500 | 0.7% | 31.5 | 409.5 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4000 | 0.7% | 28.0 | 364.0 |
参考:株式会社エルハウジング「住宅ローン減税で還元される税金はいくらか?具体例をみてみよう。【2024年~2025年新築住宅購入】」
2024〜2025年の新築認定住宅における控除額シミュレーション
続いて、年収別にまとめた表を見てみましょう。
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 年収 | 借入額2000万円 | 借入額4000万円 | 借入額6000万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 144万円 | – | – |
| 400万円 | 150万円 | 210万円 | – |
| 500万円 | 150万円 | 253万円 | – |
| 600万円 | 150万円 | 298万円 | 338万円 |
| 700万円 | 150万円 | 300万円 | 403万円 |
| 800万円 | 150万円 | 300万円 | 403万円 |
参考:ダイヤモンド不動産研究所「住宅ローン控除額(減税額)シミュレーション! 年収別に計算可能」
控除額は、主に以下の3つの要素によって変動します。
1. 年収の金額
2. 住宅ローンの借入額
3. 購入する住宅の種類
低年収層の場合、借入額が多くても最大控除額を受けられない可能性があります。
控除制度を最大限活用するには、自身の収入状況と借入予定額を考慮した詳細なシミュレーションが重要です。
実際の控除額は、個人の状況によって表中の数値と異なる場合があります。
年末残高を考慮した場合の控除額シミュレーション
住宅ローン控除額は、年末の住宅ローン残高に基づいて計算されます。
具体的には、以下の計算式で求められます。
住宅ローン控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 0.7%
ただし、この計算結果が各住宅タイプの年間最大控除額を超える場合は、最大控除額が適用されるので注意が必要です。
具体的な例として、借入額4,000万円、金利1.5%、35年返済の場合のシミュレーション例を見てみましょう。
| 年数 | 年末残高(万円) | 控除額(万円) |
|---|---|---|
| 1年目 | 3,939.56 | 27.58 |
| 2年目 | 3,847.92 | 26.94 |
| 3年目 | 3,755.08 | 26.29 |
| 4年目 | 3,661.02 | 25.63 |
| 5年目 | 3,565.74 | 24.96 |
この例では、年々住宅ローンの残高が減少していくため、控除額も徐々に減少していきます。
これらの表から以下のポイントが読み取れます。
・住宅の種類によって借入限度額と控除上限額が異なる。
・年収と借入額によって、実際の控除額が変動する。
・年末残高を考慮すると、年々控除額が減少する。
住宅ローン控除を最大限活用するためには、これらの要素を考慮し、個人の状況に合わせた詳細なシミュレーションを行うことが重要です。
住宅ローン控除を適用するための手続き
住宅ローン控除は自動的に適用される制度ではなく、定められた期限内に申請手続きが必要です。
申請の時期や方法は、入居からの経過年数や職業によって異なります。
入居1年目か2年目以降か、また会社員か自営業かで、必要書類や手続き方法が変わるため注意が必要です。
ここからは、それぞれの状況における申請手続きについて解説します。
1年目
住宅ローン控除は、入居した年の翌年に確定申告を行うことで初めて適用されます。
会社員であっても、初年度は確定申告が必要です。
職業によって申告期限が異なり、会社員は入居翌年の1月から3月15日まで、自営業者やフリーランスは2月16日から3月15日までとなっています。
申告時に必要な書類は、新築か中古かで異なるので注意が必要です。
しかし、基本的には住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書、源泉徴収票などをもとに、確定申告書と計算明細書に必要事項を記入し提出します。
会社員の場合、申請方法によって還付までの期間が異なります。
税務署での申請は1〜2ヶ月程度、e-Taxでの申請なら約3週間で還付金を受け取ることが可能です。
2年目以降
2年目以降は、給与所得者(会社員)と自営業者で申告の期限が異なります。
給与所得者(会社員)の場合は、通常、勤務先の年末調整で控除を受けることができます。
申請時期は一般的に11月中旬から12月末頃ですが、具体的な締め切りは会社ごとに異なるため、担当者への確認がするようにしましょう。
ただし、以下の場合は確定申告が必要です。
1. 年収が2,000万円以上
2. 給与所得以外の収入が年間20万円を超える
3. 複数の会社から給与を受け取っている
自営業者・フリーランスの場合は、毎年の確定申告時に住宅ローン控除の手続きを行います。
申告期間は例年2月16日から3月15日までです。
申請期限を過ぎた場合
住宅ローン控除の申請は、期日までに行わなくてはいけませんが、申請期日を超過してしまった場合でも、申請が可能な場合があります。
給与所得者(会社員)の場合は、初年度の確定申告を忘れた場合でも、5年以内であれば、遡って還付申告を住宅ローン控除の申請を行うことが可能です。
ただし、期限は5年間と定められているため、気づいた時点で速やかに申請することをおすすめします。
入居2年目以降の年末調整での申請忘れについては、1月末までなら勤務先での修正が可能です。
修正できない場合は、確定申告による申請が認められています。
自営業者・フリーランスの場合は、住宅ローン控除を適用せずに確定申告を済ませてしまった場合、原則として遡っての還付は認められません。
ただし、「更正の請求」という手続きにより還付を受けられる可能性があります。
具体的な対応については、税務署の判断となるため、管轄の税務署への相談をおすすめします。
住宅ローン控除を適用する際の注意点
住宅ローン控除を活用する際には、以下の3つの重要な注意事項があります。
1. ローンの期間が10年未満の場合は適用できない
2. 住宅ローン控除と併用できない控除がある
3. 住宅ローン控除は上限額が設定されている
ここからは、3つの注意点について具体的に解説します。
ローンの期間が10年未満の場合は適用できない
住宅ローン控除を受けるには、各適用年度においてローンの残存期間が10年以上であることが必要です。
【15年ローンの場合】
当初15年で組んだ住宅ローンでも、6年間返済を続けると残期間が9年となり、その時点で控除の適用対象外になります。
【繰り上げ返済をする場合】
繰り上げ返済によってローンの残存期間が10年を下回ると、その年から控除を受けることができなくなります。
そのため、繰り上げ返済を検討する際は、住宅ローン控除の適用期間も考慮に入れて、返済額や時期を慎重に計画することが重要です。
住宅ローン控除と併用できない控除がある
住宅ローン控除には、その他の控除・特例と併用できる場合と、併用できない場合があります。
併用可能な控除・特例は以下のとおりです。
【住宅ローン控除と併用可能な控除・特例】
1. ふるさと納税(確定申告の方法によって控除額に影響が出る可能性があります)
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
3. 医療費控除
4. マイホーム買い替え時の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(ただし、譲渡損失が優先され、所得状況によっては住宅ローン控除の恩恵を受けられないこともあります)
次に、併用できない控除・特例を見てみましょう。
【併用できない控除・特例】
1. 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除
2. 住宅売却時の軽減税率特例
3. 居住用財産の買換え特例
これらは主に住宅売却時の利益に関する控除・特例です。
どの制度を選択するかは、売却益の金額や新規住宅のローン額を考慮して判断する必要があります。
税制上の選択は取り返しがつかない場合もあるため、必要に応じて専門家への相談をおすすめします。
住宅ローン控除は上限額が設定されている
住宅ローン控除には上限額が設定されているため、実際の住宅ローン残高が高額だった場合でも、限度額までしか控除を受けることができません。
控除率は全ての住宅で一律0.7%となりますが、控除額の上限は住宅の種類や性能によって異なります。
これは借入限度額が物件によって設定が異なるためです。
以下で、新築や中古、世帯による違いを見てみましょう。
【新築の認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合】
一般世帯:総額409万5,000円(4,500万円×0.7%×13年)
子育て世帯:総額455万円(5,000万円×0.7%×13年)
【中古住宅の場合】
総額210万円(3,000万円×0.7%×10年)
このように、住宅の種類(新築・中古)や世帯区分(一般・子育て)によって、受けられる控除の総額に大きな差が生じます。
新築の認定住宅では中古住宅と比べて約2倍の控除を受けることができ、さらに子育て世帯では一般世帯よりも高い控除額が設定されています。
最大限の節税効果を得るには、これらの仕組みを十分に理解したうえで住宅購入を計画することが重要です。
最後に
住宅ローン控除は、住宅ローン利用者の税負担を軽減する制度で、適用期限は令和7年12月31日までです。
控除期間は物件により10年または13年で、住宅の省エネ性能により控除額が異なります。
令和6年度の改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯への支援強化や、省エネ基準適合住宅以上の性能を持つ物件のみが対象となるなど、環境配慮型住宅の促進が図られています。
申請方法について、入居1年目は確定申告、2年目以降は給与所得者なら年末調整で手続き可能です。
控除を受けるには年収2,000万円以下、10年以上の返済期間など基本要件を満たす必要があり、併用できない特例もあるため注意が必要です。
最大限の節税効果を得るには、これらの制度を理解した上で住宅購入を計画することが重要です。
全10回にわたって、不動産購入についてのポイントについて解説してきました。
住宅の購入は、ライフイベントの中でも大きな金額が動く、重要なものです。
今までの記事を参考に、後悔のない住宅の購入につなげていただければ幸いです。
参考:住宅ローン減税
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。