持ち家がない人の老後は?賃貸のメリットと安定して暮らす方法を解説
「老後を迎えるにあたってマイホームがないけど大丈夫?」「老後を賃貸で送るメリット・デメリットを知りたい」など、老後を賃貸で暮らすことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
近年では、ライフスタイルの変化によって、老後を賃貸で暮らすことも選択肢のひとつになっています。
非正規雇用の増加や転勤・単身赴任などの働き方の多様化、住宅価格の上昇、さらには結婚や出産をしない生き方の広がりにより、持ち家を持たないまま老後を迎える人も多いです。
賃貸暮らしには、柔軟な住み替えができる、と修繕費や固定資産税の維持コストが不要といったメリットがあります。
ライフステージや健康状態に合わせて、バリアフリー対応の物件やサービス付き高齢者向け住宅などに移り住むことができるのは、持ち家にはない強みです。
しかし、老後の生活では、収入の柱となる年金が限られており、医療費や介護費などの支出が大きな負担になります。
今後ますます進む長寿社会の中で、安心して住まいを維持するには、家計管理・資産運用・住まい選びを早めに見直す必要があります。
今回は、老後に持ち家がない場合に想定される生活費や住まいの課題、賃貸暮らしのメリット・デメリットをわかりやすく解説しますので最後まで読んでいただければと思います。
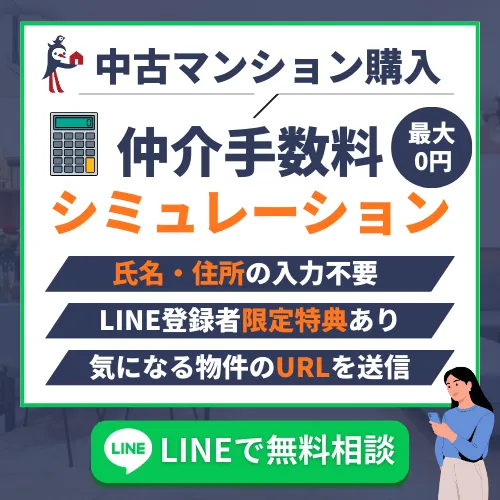
\エリア・物件選びの無料相談も可能/
▶スマトリ公式LINEで無料相談する
目次
持ち家がない人の老後はどうなる?
持ち家がない人の中には、老後の住まいについて不安を感じる人も多いと思います。
家賃の支払いが続くことや、高齢になってからの住み替えの難しさなど、さまざまな心配の種があります。
しかし、老後の生活を安心して過ごすためには、まず「どのくらいの生活費が必要になるのか」を把握し、自分に合った住まいの形を選ぶことが大切です。
ここでは、老後にかかる生活費の目安を確認しながら、賃貸と持ち家のどちらを選ぶべきかを、現実的な視点で考えていきます。
老後にかかる生活費の目安
老後にかかる生活費については、それぞれの世帯で異なりますが、公共財団法人生命保険文化センターの調べでは、65歳以上の夫婦2人の無職世帯の場合、平均的な収入は月額25.3万円、支出は月額約25.6万円です。
◎ 65歳以上の夫婦2人の無職世帯の平均的な収入と支出
| 項目 | 月額(平均) |
|---|---|
| 収入 | |
| 公的年金(2人分) | 約22.5万円 |
| その他収入(預貯金取り崩し・資産運用など) | 約2.7万円 |
| 収入合計 | 約25.2万円 |
| 支出 | |
| 住居費 | 約1.6万円 |
| その他支出(食費・税金・社会保険料など) | 約24.0万円 |
| 支出合計 | 約25.6万円 |
| 月間収支差額 | ▲0.4万円(赤字) |
可処分所得(手取りに相当)は22.2万円となるので、約3.4万円の不足となります。
参考:老後の生活費はどれくらい?(公共財団法人生命保険文化センター)
今回のデータは、賃貸世帯と持ち家世帯が混在した平均値である点に注意が必要です。
総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、65歳以上の夫婦のみ無職世帯の住居形態の87.6%が持ち家、賃貸は12.4%となっています。
借家に住む世帯のうち、家計を主に支える者が高齢者(65歳以上)である世帯の1ヶ月当たりの家賃の平均額(家賃0円は含まない)は58,076円です。
賃貸で暮らしている場合は、平均的な世帯よりも4.2万円ほど支出が大きくなることを踏まえておく必要があります。
賃貸と持ち家はどっちが得?
賃貸と持ち家、どちらが得かは老後のライフスタイルと収入状況によって異なります。
まずは、賃貸と持ち家のメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 比較項目 | 賃貸 | 持ち家 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 少ない(敷金・礼金など) | 多い(購入費・ローン) |
| 毎月の支出 | 家賃が発生し続ける | 固定資産税・修繕費など |
| 自由度 | 引っ越ししやすい | 売却・住み替えは手間 |
| 安心感 | 更新拒否・立ち退きリスクあり | 住居の安定性が高い |
賃貸は、自由度が高く身軽に暮らせる反面、老後の家賃負担が大きなリスクです。
家賃を考えると、持ち家よりも賃貸のほうが住居費の負担は増えます。
一方で、持ち家は、住居費は抑えることができますが修繕費や固定資産税が必要です。
また、35年など長期で住宅ローンを組んでいる場合は、30歳未満で契約をしない限りは65歳を超えても住宅ローンが残ります。
賃貸と持ち家のどちらが得であるかは一概には言えず、各世帯の状況や考え方によって変わるので、年金収入・貯蓄・健康状態、家庭環境などを踏まえて、自分に適した住まいを選ぶことが大切です。
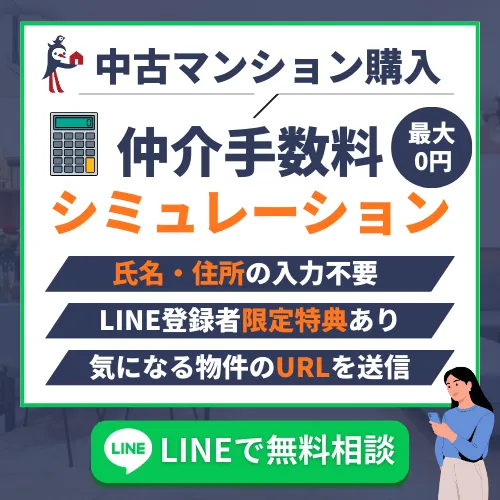
\エリア・物件選びの無料相談も可能/
▶スマトリ公式LINEで無料相談する
持ち家がない人が老後に賃貸で暮らすメリット
老後に持ち家がない人は、老後の資金や住まいに不安を感じるかもしれません。
しかし、賃貸の場合は、持ち家と比べるとライフスタイルの変化に柔軟に対応できるだけでなく、経済的な負担を抑えながら安心して暮らせるなどメリットは多いです。
ここでは、老後に賃貸で暮らす主な3つのメリットについて解説します。
- 引っ越しや住み替えに対応できる
- 修繕費や税金が抑えられる
- 相続によるトラブルの心配がない
引っ越しや住み替えに対応できる
賃貸の一番のメリットは、ライフステージや健康状態の変化に合わせて住み替えに対応できる点です。
たとえば、老後に階段の上り下りがつらくなった場合、戸建てからマンションに引っ越しする、車に乗るのが不便になったら駅近の物件へ移るなど、柔軟に住まいの選択ができます。
また、介護施設やサービス付き高齢者向け住宅への移行が必要になった場合、持ち家であれば、売却するなど手間がかかりますが、賃貸であれば引っ越しもスムーズに行えます。
修繕費や税金が抑えられる
持ち家の場合、住居費以外に、老朽化に伴う修繕やリフォーム、毎年の固定資産税などの費用が発生しますが、賃貸の場合、修繕費や税金などの費用を抑えられるのがメリットです。
建物の修繕や設備の交換は大家や管理会社が行うため、自分で修繕費などの大きな出費を負担する必要がありません。
また、固定資産税や都市計画税といった税金も不要なため、家計への負担を減らすことができ、収入が少なくなった年金生活においても安心して暮らせます。
相続によるトラブルの心配がない
賃貸であれば相続によるトラブルの心配はありません。
持ち家があると、相続の際に「誰が住むか」「どう分けるか」といったトラブルが起きることが考えられます。
特に複数の子どもがいる場合、遺産分割の対象になる不動産が原因で家族関係がこじれるケースも多いです。
家を持たないことで、相続時の煩雑な手続きや争いを避けることができるのは賃貸の大きなメリットと言えます。
持ち家がない人が老後に賃貸で暮らすデメリット
老後を賃貸で暮らすことは、多くのメリットがある一方でデメリットもあります。
特に高齢になるほど、収入や健康状態、社会的信用などの面で賃貸契約に不利になることがあり、生活の安定性に影響するケースも多いです。
ここでは、老後に賃貸で暮らす際に考慮すべき4つのデメリットを解説します。
- 入居審査で不利になるケースがある
- 家賃を一生支払い続ける必要がある
- 介護や医療のサービスを受けづらくなる
- 地域コミュニティの関係性が築きづらい
入居審査で不利になるケースがある
高齢者は、年金など限られた収入や健康上のリスク、身元保証の問題などから、賃貸の入居審査で不利になるケースが多いです。
国土交通政策研究所の調査によると、大家の約7割が高齢者の入居に拒否感を示し、その理由の約9割が「居室内での死亡事故などへの不安」とされています。
こうした心理的・実務的リスクから、賃貸人側は高齢者の入居に慎重になる傾向があります。
ヒアリング調査から明らかになった、高齢者の賃貸における入居審査のトラブル事例は以下の通りです。
- 緊急連絡先が確保できない単身高齢者は審査が通りにくい
- 保証会社の利用がほぼ必須になっているが、審査基準は年齢よりも収入や属性に依存するため、年金収入のみでは厳しい場合もある
他にも、孤独死や死亡後の残置物処理、原状回復費用への懸念が、入居拒否の要因として大きく影響しています。
特に単身高齢者が死亡した場合、特殊清掃や残置物処理、相続人対応に多額の費用と手間がかかるため、リスクを避けたいということで、賃貸人が入居を拒否するケースもあります。
高齢者が賃貸を借りる際ためには、収入や健康だけでなく、信頼できる保証体制や支援ネットワークを確保しておくことが、入居の可否を左右する重要なポイントです。
参考:高齢者の建物賃貸借契約における実務上の課題(国土交通省)
家賃を一生支払い続ける必要がある
賃貸では、住み続ける限り家賃の支払いが必要です。
年金生活に入ると収入が限られる中で、毎月の家賃が家計を圧迫します。
また、家賃は物価上昇や再契約のタイミングで賃料を値上げされる可能性もあり、安定した住まいを確保することが難しいケースもあります。
持ち家であれば、ローン完済後は資産になり、住まいに掛かる費用は、固定資産税や修繕費のみです。
一方で、賃貸は家賃の支払いが一生続くので、住居費が大きなコストになる点が持ち家と大きな違いと言えます。
長く安定した住まいを確保するために、家賃補助のあるセーフティネット住宅や高齢者向け賃貸の活用、家賃支援制度を検討しましょう。
介護や医療のサービスを受けづらくなる
賃貸では、介護や医療サービスを受けづらくなるケースもあります。
たとえば、訪問介護や訪問診療を利用する際には、大家の許可が必要になる場合もあり、スムーズにサービスを受けられないケースも多いです。
手すりの設置や段差の解消といったリフォームが必要になっても、大家さんの許可なくリフォームをすることができないため、住環境を整えることが難しいでしょう。
そのため、入居する物件を検討する際に、段差が少なく、手すりなどバリアフリー対策をしている物件を選んでおくと老後も安心です。
介護・医療サービスと連携できる住まいを提供してくれる、居住支援法人や地域包括支援センターのサービスの活用も有効な選択肢と言えます。
地域コミュニティの関係性が築きづらい
賃貸で暮らす高齢者は、地域コミュニティとの関係を築きにくい傾向があります。
持ち家の住民に比べて地域活動や町内会への参加が限定的になりやすく、近隣住民との交流機会も少なくなることが多いです。
その結果、孤立感が強まり、緊急時の助けを得にくくなるリスクと言えます。
地域コミュニティとの関係性を築くためには、地域の高齢者向けサークルや自治体の見守りサービスに積極的に参加することが重要です。
また、近隣住民との日常的なあいさつや交流の機会を意識的に増やすことで、孤立を防ぐことができます。
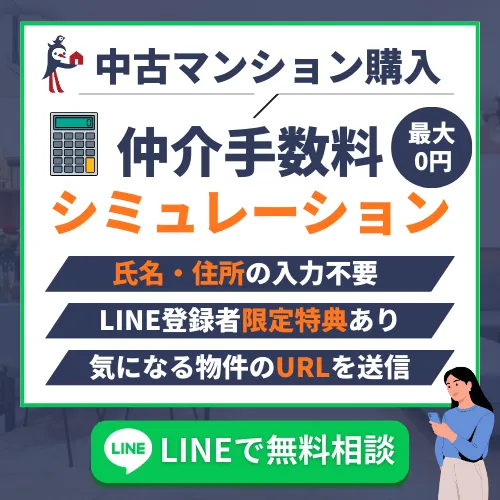
\エリア・物件選びの無料相談も可能/
▶スマトリ公式LINEで無料相談する
持ち家なしの老後を安定して送るためのポイント
老後を持ち家なしで安心して暮らすためには、資金・住まい・生活設計の3つの観点から準備を進めることが大切です。
老後に備えて家計を整え、住まいの選択肢を多く持ち、資産運用や投資などにも目を向けるなどしておくことで、賃貸生活でも安定した暮らしが実現できます。
ここでは、具体的な工夫や利用できる制度を交えながら、安定した老後を送るためのポイントを紹介します。
なるべく早いうちに家計を見直す
老後資金を確保するためには、早めに家計の見直しをしておくことが大切です。
現役時代から生活費や固定費をできるだけ減らし、余裕資金で資産運用や投資を行うなど、老後資金を計画的に貯めておけば、老後も安心し暮らすことができます。
たとえば、保険の見直しや通信費の節約、サブスクリプションサービスを見直すだけで月数千円単位の改善が可能です。
他にも、カーシェアなどを利用することで、駐車場代や車検費用などの固定費を減らすことができます。
高齢者向けの賃貸住宅を利用する
高齢者が賃貸住宅を借りにくいという課題を解消するため、自治体や民間では高齢者向けの住宅制度が整備されています。
代表的なのがサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やシニア向け賃貸住宅です。
高齢者向けの住宅は、バリアフリー設計や安否確認サービスが付いており、単身でも安心して暮らせます。
ただし、一般の賃貸住宅に比べて家賃や管理費、サービス費が高めに設定されているケースが多いです。
資金面で厳しい場合は、自治体によって利用できる、高齢者向け入居支援制度や家賃補助制度を活用しましょう。
たとえば、東京都の「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度」では、家主と協力して高齢者が入居しやすい住宅を提供しており、高齢者の入居を拒まない賃貸物件の情報を公開することで、住まい探しの不安を軽減しています。
早めにサービスや制度の内容を確認し、老後の住居の選択肢を増やしておくことが大切です。
資産運用や投資を検討する
貯金だけではインフレや物価上昇に対応しづらいため、少額からでも資産運用を始めることが重要です。
老後に安定した生活を送るには、預金だけでなく、増やすといった視点も必要になります。
代表的な資産運用や投資の方法には以下のようなものがあります。
| 投資の種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 株式投資 | 企業の株を購入して利益や配当を得る | 成長企業に投資すれば高いリターンも可能 | 価格変動が大きく、短期的な損失リスクがある |
| 投資信託 | 多くの投資家から集めた資金をプロが運用 | 少額から始められ、分散投資でリスクを抑えられる | 手数料や信託報酬が発生する |
| 不動産投資 | 物件を購入して賃貸収入を得る | 長期的な安定収入や資産形成が可能 | 初期費用が高く、空室リスクや管理負担もある |
| 債券・国債 | 国や企業にお金を貸して利息を得る | 比較的安全性が高く、定期的な利息収入 | 金利上昇時に価格下落のリスクあり |
投資といっても種類によってリスク・リターンのバランスが大きく異なりますので、自身のリスク許容度に合わせて、分散しながら複数の手段を組み合わせることが大切です。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISAなどの制度を活用すれば、税制優遇を受けながら効率よく老後資金を積み立てることができます。
老後に備えてマンションを購入する
ずっと賃貸では不安という人は、老後を見据えてコンパクトなマンションを購入するのもひとつの選択肢です。
高齢期の住まいを早めに確保しておけば、家賃負担がなくなり、将来的な住居不安を解消できます。
特に、駅近でバリアフリー設計の中古マンションなどは、資産価値が維持されやすく、万一の場合は売却や賃貸運用も可能です。
また、マンションを購入しておけば、売却やリースバック、リバースモーゲージといったサービスの活用など、老後の住まいの選択肢を増やせます。
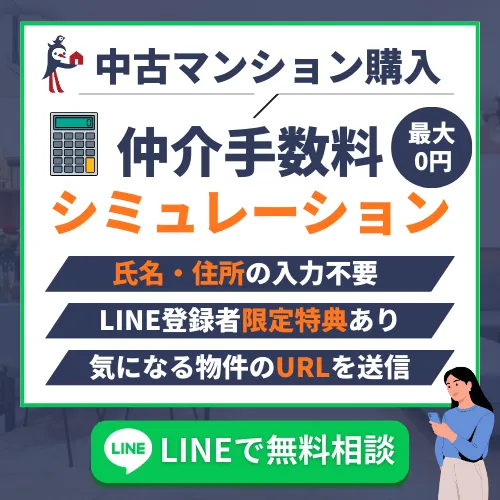
\エリア・物件選びの無料相談も可能/
▶スマトリ公式LINEで無料相談する
持ち家がない人の老後に関するよくある質問
老後の住まいに関する悩みとして多いのが、家賃の支払いや住まいについての不安でしょう。
持ち家がないことで、将来の住居費が負担に思う人が多いと思いますが、実際には制度や支援を上手に活用することで安定した生活が可能です。
ここでは、よくある3つの疑問についてご紹介します。
老後に家賃が払えない場合はどうなる?
老後には、収入が年金だけになってしまうので、病気や事故などで急な資金が必要になった場合、家賃を払えなくなるケースも多いです。
しかし、すぐに住まいを失うわけではなく、生活を支える公的制度や支援策が用意されています。
たとえば、所得が一定以下の人は生活保護制度を利用でき、住宅扶助によって家賃の一部または全額が支給される場合があります。
また、各自治体には高齢者向け家賃補助制度や入居支援制度があるケースも多いです。
他にも、改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者に見守り等の入居中のサポート提供を行う住宅(居住サポート住宅)の認定制度が令和7年10月1日から始まっています。
参考:居住サポート住宅情報提供システムの公開 ~10月1日より認定制度が始まります!~(厚生労働省)
早めに自治体や地域包括支援センターに相談しておくことで、家賃負担が難しくなった場合の選択肢を確保しておくことが大切です。
年金で家賃を支払い続けることは可能?
老後に賃貸に住み続ける場合、不安なのが年金収入だけで家賃を払い続けられるのかという点だと思います。
2025年度における標準的な夫婦2人世帯では、厚生年金の平均受給額は232,784円です。
このくらい収入があると、家賃・光熱費・食費などを支払っても生活に問題はないでしょう。
しかし、年金額については、各家庭で異なります。
受給額が少ない人は、生活費を抑える工夫や制度利用して少ない家賃で住める家を確保するなどの対策が必要です。
たとえば、家賃の安い地域やUR賃貸などの公的住宅を選ぶ、家賃補助制度や生活支援給付金を活用することで負担を軽減できます。
また、家計を補う手段として、パート勤務や年金受給後の在宅ワーク、副収入(投資信託・不動産収入など)など、年金以外の収入を確保しておく必要があります。
年金だけに頼らず、複数の収入源を持つ意識が、年金生活になっても安心して暮らせるポイントです。
持ち家がない人は生涯賃貸でも大丈夫?
持ち家がないことで不安を感じる人は多いと思いますが、しっかり準備すれば生涯賃貸でも安心して暮らせます。
近年は、高齢者の入居に前向きなオーナーや、見守り・安否確認サービス付きの賃貸住宅が増えています。
また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やシニア向け賃貸マンションなど、高齢者の暮らしに特化した住宅も選択肢のひとつです。
生涯賃貸を安心して続けるためのポイントは、以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 早めに長く住める物件を確保しておく
- 保証人・緊急連絡先の確保(親族・専門サービス利用)
- 将来的な収入減に備えた家計設計(NISA・iDeCo・不動産投資・貯蓄)
また、体調の変化や介護が必要になった場合は、自治体やNPO法人を通じて住み替え支援を受けることも可能です。
「生涯賃貸=不安」ではなく、準備と制度の理解によって安定した暮らしを築ける時代になっています。
【無料】住まい購入の相談はスマトリがおすすめ!
・仲介手数料最大無料
・氏名や住所の入力不要
・電話やメールの営業なし
スマトリのLINE相談では、AIではなく経験豊富な担当者が対応してくれるので、不動産の購入が初めての人でも安心して利用できます。
気になる物件が既にある方は、仲介手数料無料かどうかをお気軽に判定可能です。
「仲介手数料無料って本当?」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、まずはスマトリのLINE相談を活用してみてください。
まとめ
今回は、老後を賃貸で暮らすメリット・デメリットを中心に、老後を賃貸で安定した生活を送るポイントなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
持ち家がない人の老後は、家賃の支払いが続く点で経済的な不安を抱えやすいものの、早めの準備と制度の活用により安定した暮らしを実現できます。
まずは、老後を見据えて家計を見直し、無駄な支出を減らして生活費の基盤を整えることが重要です。
生活の基盤が安定していれば、年金だけの収入になっても生活に支障はないでしょう。
住まいの面では、家賃の支払いが難しい場合は、自治体の家賃補助制度の活用やNPO法人の支援を受けることで、安全で安心できる住環境を確保することができます。
また、資金面では、預貯金だけに頼らず、NISAやiDeCoを活用した資産運用で将来に備えておくと安心です。
株式や投資信託、不動産投資などを組み合わせ、長期・分散・積立の姿勢で安定的に資産を増やしましょう。
制度やサービスを理解し、現実的な生活設計を立てておくことで、持ち家がなくても、より自分らしい豊かな老後が実現できます。
これから老後を賃貸で過ごす可能性がある人は、今回の記事を参考に、老後の賃貸生活に向けて準備を行い、安定した生活を送っていただければと思います。
横浜市で口コミ1位の葬儀社である横浜葬儀社はばたきグループの運営するメディア「葬儀の豆知識」内の記事「【2025年版】終活・相続に備えて検討したいおすすめの不動産会社・サービスまとめ」に当社が掲載されました。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。











