マンションに虫が出る原因は?侵入経路と害虫対策を徹底解説
「マンションなのになぜ虫が出るの?」
「効果的な虫対策の方法を知りたい」
こうした疑問や悩みを抱えている方は少なくありません。マンションは戸建てに比べて虫が出にくいと思われがちですが、実際にはさまざまな経路から虫が侵入し、多くの住民が頭を悩ませています。
実際、甲南防疫株式会社が実施した調査(2024年7月実施)では、マンション住民の半数以上が「月に数回以上、室内で害虫を見かける」と回答しています。
また、発生する虫としては「クモ」「ハエ」「ゴキブリ」が上位を占め、最も多く見かける場所はエントランスや階段、ベランダなど、共用部での目撃例も多く報告されました。
特に夏場に発生するゴキブリや蚊は、快適な生活環境を大きく損なう原因となります。
本記事では、マンションで虫が発生しやすい原因や侵入経路、そして効果的な予防・駆除方法について詳しく解説。
虫の発生を大幅に減らし、安心して快適に暮らせるマンション生活を目指すために、ぜひ最後までお読みいただき、日々の対策にお役立てください。
参考:【マンションの衛生管理】2人に1人が「月に数回以上害虫を見かける」と回答。4割の方がオーナー・管理会社に満足していないことも明らかに(PR TIMES)
目次
マンションで虫が発生しやすい原因と侵入経路
マンションで虫が発生しやすいのは、建物の構造や立地、住環境の管理状態などが影響しているためです。まずは、虫が侵入しやすい条件と主な侵入経路を把握しておきましょう。
低層階(3階以下)は虫が侵入しやすい

マンションの低層階、特に1~3階の住戸は、虫の侵入リスクが高い傾向にあります。これは多くの害虫が地表付近で活動し、飛行能力にも限界があるためです。
ゴキブリやアリなど地表を移動する虫は、外壁を伝って上階にも侵入できますが、多くは3階程度までに留まります。蚊やハエなど飛行する虫も、風の影響を受けやすく、低層階での遭遇率が高くなります。
さらに、1階部分は地面からの湿気や植栽を通じた虫の移動も起こりやすく、虫の生息環境に近いぶん、侵入の機会も増えるため注意が必要です。
築年数が古い・隙間の多い建物

築年数の経過したマンションは、経年劣化によって建物の各所に微細な隙間が生じやすく、虫の侵入経路になりがちです。
特に注意すべきなのは、窓サッシの劣化、玄関ドア周辺のゴムパッキンの劣化、配管まわりのシーリング材の収縮などです。わずか1ミリの隙間でも、小さな虫にとっては十分な侵入口となります。
さらに、古い建物では換気設備に防虫対策が施されていないケースも多く、換気口や排水口からの侵入も起こりやすくなります。
建物のメンテナンス状況は、虫の侵入リスクを左右する重要な要素です。
周囲の環境(緑地や飲食店など)

マンション周辺の環境は、虫の発生頻度に大きく影響します。特に自然が多い立地では、虫の生息数が増える傾向にあるでしょう。
公園や緑地に隣接していると、樹木や草花にいる虫が建物に飛来しやすくなります。また、川や池など水辺が近い場合は、蚊やユスリカなど水生昆虫の発生源になることも。
さらに、近くに飲食店があると、生ゴミの臭いに引き寄せられてゴキブリやハエが集まりやすくなります。夜間にはコンビニの照明に集まった虫が、住戸へと入り込むケースも少なくありません。
生ゴミや汚れが放置されている

室内の清潔さは、虫の発生に直結します。特に生ゴミを適切に処理しないと、強い臭いが害虫を引き寄せてしまいます。
キッチンの三角コーナーにゴミがたまったままだったり、シンクに食べかすが残っていたりすると、腐敗臭に誘われてゴキブリやハエが集まりやすくなってしまうのです。
さらに、食べこぼしや飲み残しが床や棚に残っていると、アリの侵入を招く原因になります。
また、排水口のヌメリや浴室のカビなど水回りの汚れも要注意です。日頃から掃除を心がけ、ゴミはこまめに処分することで、虫を寄せ付けない環境を維持できます。
虫の侵入経路が複数存在する
マンションにおける虫の侵入経路は、主に以下の3つに分けられます。これらを把握することで、より効果的な防虫対策が可能になります。
1. 開口部からの侵入
玄関ドアや窓は、虫が最も侵入しやすい場所です。人が出入りする際に一緒に入り込んだり、わずかな隙間から侵入したりします。
2. 水回りからの侵入
キッチンや洗面所の給排水管周辺の隙間、そして排水トラップの封水切れが主な侵入経路となります。封水が切れると、下水管から虫が上がってきやすくなります。
3. ダクト系からの侵入
換気口、通気口、エアコンの室外機につながるドレンホースなどは、虫にとって格好の通り道です。
これらすべての侵入経路に対策を講じることで、マンションへの虫の侵入を大幅に減らせるでしょう。
マンションでよく見られる害虫の種類
マンションで遭遇する虫の種類を理解することで、適切な対策を講じられます。それぞれの虫の特徴と出現パターンを詳しく見ていきましょう。
ゴキブリ
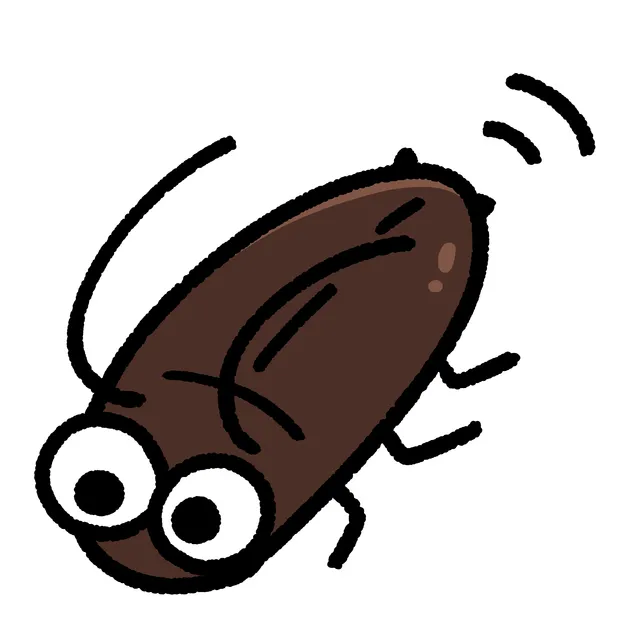
ゴキブリはマンションでも見られることの多い虫です。主にクロゴキブリとチャバネゴキブリの2種類が住宅内でよく見られます。
| 種類 | 体長 | 特徴 | 侵入経路・生息場所 |
|---|---|---|---|
| クロゴキブリ | 27~33mm | 大型・黒色 | 下水道・建物地下部分 |
| チャバネゴキブリ | 12~15mm | 小型・茶色 | 冷蔵庫裏・電子機器内部 |
出現頻度は夏場が最も高く、気温が25度を超える6月から9月にかけてピークを迎えます。夜行性のため、深夜に遭遇することが多く、繁殖力も非常に強いため、早期の対策が重要です。
蚊

蚊は主にヒトスジシマカとアカイエカの2種類が住宅地でよく見られます。両種とも人の血を吸って繁殖するため、不快な害虫とされています。
| 種類 | 活動時間 | 特徴 | 繁殖場所 |
|---|---|---|---|
| ヒトスジシマカ | 昼~夕方 | 白いストライプ模様 | 庭の水たまり・竹の切りかぶ |
| アカイエカ | 夕方~夜 | 茶褐色 | 下水溝・ドブなどの汚水 |
出現時期は5月から10月が中心で、特に梅雨時期から夏場にかけて個体数が急増します。
マンションにおける主な発生源としては、ベランダの排水口やエアコンの室外機周辺にできる水たまりが挙げられます。これらの場所に水がたまらないようにすることで、発生を抑えられるでしょう。
ハエ
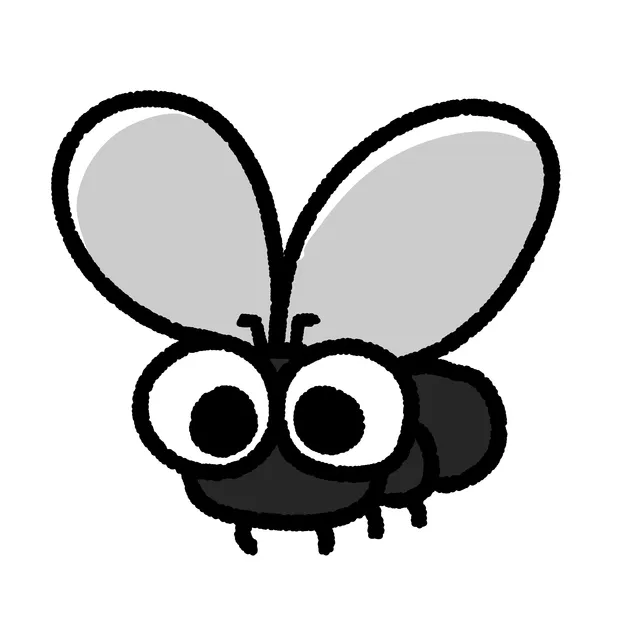
住宅でよく見られるハエには、イエバエ、オオイエバエ、ショウジョウバエなどがあります。それぞれ生態や発生原因が異なります。
| 種類 | 体長 | 色・特徴 | 発生源 |
|---|---|---|---|
| イエバエ | 6~8mm | 灰色 | 生ゴミ・動物のフン |
| オオイエバエ | 8mm以上 | 灰褐色・大型 | 腐敗した有機物 |
| ショウジョウバエ | 2~3mm | 小型・黄褐色 | 果物・調味料 |
年間を通して発生しますが、特に夏場は活動が活発になります。
キッチンの生ゴミ、特に果物の皮や野菜くずが主な発生源となるため、こまめなゴミの処理が発生抑制の鍵となるでしょう。
アリ

マンションで見られるアリは、主にイエヒメアリとトビイロケアリです。わずかな隙間からでも侵入し、食べ物を求めて屋内に入り込みます。
| 種類 | 体長 | 好む食べ物 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| イエヒメアリ | 2mm | 雑食性 | 様々な食べ物に集まる |
| トビイロケアリ | 3~4mm | 甘いもの | 砂糖や蜜など甘いものに集まる |
アリの活動が活発になるのは春から秋にかけてです。
一度侵入を許すとフェロモンで仲間を呼び寄せ、大群で押し寄せるため、早期の対策が重要です。サッシや壁の微細な隙間など、ほんのわずかな開口部からも侵入します。
ダニ
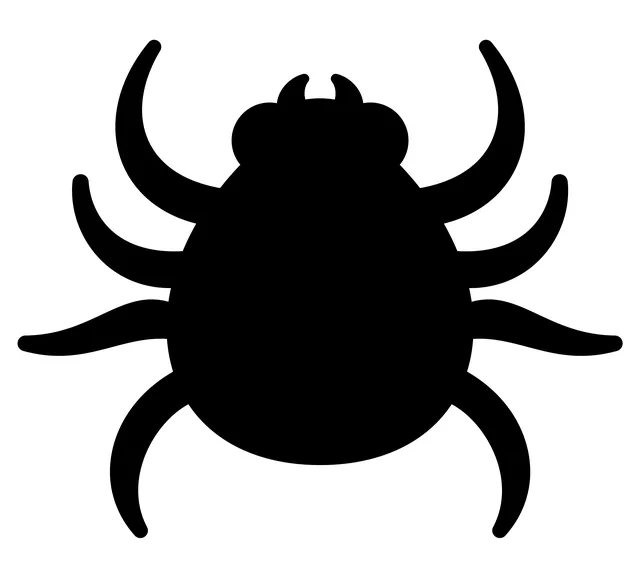
室内で問題となるダニは主にヒョウヒダニとツメダニの2種類です。直接的な害よりも、アレルギーの原因となることが問題視されています。
| 種類 | 体長 | 餌・特徴 | 生息場所 |
|---|---|---|---|
| ヒョウヒダニ | 0.3~0.4mm | 人間の皮膚片・繊維くず | 布団・カーペット・ソファ |
| ツメダニ | 0.5~1mm | 他のダニを捕食・人を刺す | 畳・カーペット |
ダニは通年で見られますが、梅雨から夏にかけて急増します。室内の湿度が60%を超えると繁殖が活発になるため、湿度管理が最も重要な対策となります。
カメムシ
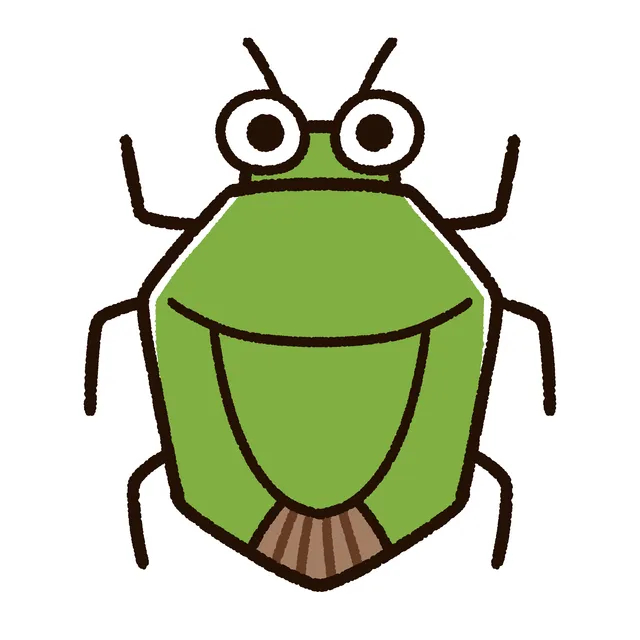
カメムシは特に秋口に住宅への侵入が増える害虫です。主にマルカメムシやクサギカメムシがマンションでよく見られます。
| 種類 | 体長 | 色・特徴 | 侵入時期・経路 |
|---|---|---|---|
| マルカメムシ | 5~6mm | 暗い黄褐色・小型 | 9~11月・窓の隙間 |
| クサギカメムシ | 13~18mm | 茶褐色・大型 | 9~11月・換気口 |
カメムシは9月から11月にかけて越冬のために、窓や換気口から建物内へ侵入します。発見しても無理に触ると悪臭を放つため、慎重に対処しましょう。
また、洗濯物に付着して室内へ入り込むこともあるため、秋口は洗濯物を取り込む際にも注意が必要です。
マンションで虫を寄せ付けないための予防対策
虫の侵入を防ぐためには、侵入経路の遮断、忌避効果のある製品の活用、清潔な環境の維持という3つのアプローチが効果的です。
侵入経路をふさぐ

虫の侵入を防ぐには、まず物理的に経路を遮断することが基本です。窓や玄関ドアの隙間は、隙間テープやコーキング材でしっかりと埋めましょう。
換気口や通気口には、市販の防虫フィルターを設置します。破損している場合は、目の細かいメッシュタイプに交換するとより効果的です。
エアコン室外機のドレンホースには、防虫キャップを取り付けることで虫の侵入を防げます。
また、長期間使わない排水口は封水が切れやすいため、定期的に水を流しておくようにしましょう。配管周辺に隙間がある場合は、パテやシーリング材でしっかりと塞ぐことが大切です。
虫よけグッズ・忌避剤を活用する

玄関や窓周辺に市販の忌避スプレーを定期的に散布することで、虫の侵入を化学的に防げます。
化学薬品が気になる方には、ミントやユーカリ、ラベンダーなどの精油を水で薄めた天然スプレーがおすすめです。これらの香りは人にとっては心地よく、多くの害虫が嫌う性質を持っています。
また、玄関やベランダでハーブを育てるのも効果的です。生きた植物が放つ香りにより、持続的な虫よけ効果が期待できます。
さらに、超音波式やファン式などの電気式虫よけ器具を玄関・窓際に設置することで、物理的に侵入を防げます。夜間の虫対策には、虫が寄りにくい波長のLED照明を選ぶのも有効です。
こまめな清掃とゴミ捨ての徹底

清潔な環境を維持することは、虫を寄せ付けないための最も基本的かつ重要な対策です。キッチンでは、調理後の清掃を徹底し、食べかすや油汚れを残さないようにしましょう。
生ゴミは密閉容器に入れて早めに処分し、三角コーナーや排水口のゴミ受けはこまめに清掃してヌメリを除去します。食品・調味料・砂糖類は密閉容器での保管が必須です。
床や棚の隙間に落ちた、食べかすも定期的に確認しましょう。
掃除機やモップによるこまめな清掃で、虫の餌となるものを徹底的に除去できます。
マンションに虫が出たときの駆除方法
しっかりと対策をしていても虫が出てしまった場合には、迅速かつ効果的に駆除することが大切です。虫の種類によって最適な駆除方法は異なるため、正しい方法を選びましょう。
ゴキブリの駆除方法
ゴキブリを見つけたら、目の前の個体を駆除するだけでなく、隠れている仲間も退治する必要があります。目に見えるゴキブリには、冷却スプレーや殺虫スプレーを使って確実に駆除しましょう。
隠れている個体には毒エサが有効です。ホウ酸ダンゴやジェルタイプの毒エサをキッチンや水回りに設置すると、巣に持ち帰って仲間にも効果が及びます。
部屋全体を虫から守るには、煙が出るタイプの殺虫剤(くん煙剤)が有効です。煙により、見えない場所に隠れているゴキブリも一度に退治できます。
使用時は食器や食品を保護し、使用後はしっかり換気しましょう。卵には効果が薄いため、2週間後に再度使用し、ふ化した幼虫も駆除します。
蚊の駆除方法
蚊の駆除には、成虫の対処と発生源の除去が欠かせません。室内にいる蚊には、電気式の蚊取り器や殺虫スプレーが効果的です。
根本的な対策として、水たまりをなくすことが重要です。ベランダの排水口、植木鉢の受け皿、雨水がたまりやすい場所はこまめに確認し、水を除去しましょう。
どうしても水をためておく必要がある場合は、10円玉を入れるのがおすすめです。銅イオンの作用によって、蚊の幼虫の成長を抑制する効果が期待できます。
ハエの駆除方法
ハエの駆除には、成虫の除去と発生源の管理が重要です。室内のハエには、粘着式ハエ取り紙や電撃式捕虫器が効果的。
発生源となる生ゴミは密閉容器に入れ、こまめに処分します。
排水口や三角コーナーは清潔に保ち、パイプクリーナーで内部の汚れも除去しましょう。シンクや調理台はアルコールで拭き、ハエを引き寄せる臭い対策を徹底することが大切です。
コバエの詳しい対処法については、以下の記事もぜひご覧ください。
参考:マンションでコバエ大量発生!どこから来るのか原因と防止策を解説
アリの駆除方法
アリが室内に侵入した場合は、まず侵入経路を特定し、遮断することが重要です。アリの行列をたどって侵入口を見つけたら、周囲に市販の毒餌を設置しましょう。
毒餌は働きアリが巣に持ち帰ることで、巣ごと駆除する効果が期待できます。効果が出るまで1~2週間ほどかかる場合がありますが、根本的な対策となります。
即効性を求める場合は、侵入経路にスプレータイプの殺虫剤を使用するとよいでしょう。侵入口の隙間はコーキング材や隙間テープでしっかり塞ぎ、再侵入を防ぎます。
また、シナモンパウダーやコーヒーの出し殻を侵入経路にまくと、天然の忌避効果が期待できます。
アリの対処法ついて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考:家の中のアリは駆除できる?効果的な対処法や侵入を防ぐ対策を解説
ダニの駆除方法
ダニの駆除には、高温処理と湿度管理が効果的です。布団や枕などの寝具は、50℃以上で20分以上加熱すると死滅します。
布団乾燥機や衣類乾燥機を使った後は、ダニの死骸をしっかり吸い取りましょう。表面だけでなく、マットレスの縫い目や枕の周辺なども丁寧に処理することが重要です。
室内の湿度を50%以下に保つことで、ダニの繁殖を抑えられます。特に梅雨時期や夏場は、除湿機やエアコンの除湿機能を活用して湿度管理を徹底しましょう。
カーペットやソファなどの布製品も定期的に掃除機をかけ、可能であれば丸洗いすることで、より効果的にダニを除去できます。
カメムシの駆除方法
カメムシは刺激を受けると強い悪臭を放つため、臭いを出させる前に静かに駆除することが大切です。
効果的な方法のひとつが、ペットボトルで作る簡易捕獲器。(作り方は「カメムシ、ペットボトルで簡単捕獲 灯油やLEDライト活用」日本農業新聞を参照)
カメムシは下に逃げる習性があるため、容器をそっと差し出すと自ら入り込みます。
大量発生時には凍結式の殺虫スプレーが有効です。殺虫成分を含まず、瞬時に凍らせて悪臭を出す前に駆除できる点がポイントです。
注意すべきなのは、カメムシをたたいたり潰したりしないこと。刺激で悪臭を放ち、壁や床に臭いが残る恐れがあります。
万が一手に臭いがついた場合は、オリーブオイルや食器用洗剤を使うと効果的に落とせます。
【無料】住まい購入の相談はスマトリがおすすめ!
・仲介手数料最大無料
・氏名や住所の入力不要
・電話やメールの営業なし
スマトリのLINE相談では、AIではなく経験豊富な担当者が対応してくれるので、不動産の購入が初めての人でも安心して利用できます。
気になる物件が既にある方は、仲介手数料無料かどうかをお気軽に判定可能です。
「仲介手数料無料って本当?」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、まずはスマトリのLINE相談を活用してみてください。
まとめ:虫を寄せ付けない環境づくりで快適なマンション生活を
本記事では、マンションの虫対策について詳しく解説してきました。効果的な虫対策のポイントをまとめると以下のようになります。
- 開口部・水回り・ダクト系の3つの侵入経路を塞ぐ
- 物理的な遮断と忌避剤を組み合わせる
- 日常的な清掃とゴミ処理を徹底する
- 虫の種類に応じた適切な駆除方法を選ぶ
- 早期発見・早期対処を心がける
特に、低層階や築年数の古いマンションにお住まいの方は、隙間の補修や設備点検をこまめに行いましょう。生ゴミの密閉保管、水回りの清潔な状態の維持、食品の適切な保管によって、虫が好む環境をつくらないことが最も重要です。
万が一虫が出てしまっても、慌てずに正しい方法で対処すれば問題ありません。こうした対策を継続することで、虫の心配のない快適なマンション生活を送れるでしょう。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。












