SRC造でもうるさいと感じるのはなぜ?構造と音の関係・騒音対策を解説
「SRC造は騒音が少ないと聞いていたのに、実際に住んでみると意外とうるさくて困っている」「構造によって防音性能に差があるって本当?」など、マンションでの暮らしにおいて騒音に悩まされる人は少なくありません。
快適な住環境を選ぶうえで、「音の問題」は非常に重要な判断材料です。
騒音の感じ方には個人差がありますが、その原因は住戸の立地や周辺環境だけでなく、建物の構造そのものによっても大きく左右されます。
一般的に、マンションの構造には「SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)」「RC造(鉄筋コンクリート造)」「S造(鉄骨造)」といった種類があり、その中でもSRC造は防音性が高く、騒音トラブルが起こりにくい構造として知られています。
国土交通省の調べでは、民間の建築物は単価の安い木造や鉄骨造が65%を占めており、RC像、SRC造は35%程度です。
参考:民間と公共建築工事には、建物用途、構造種別の構成に違いがある(国土交通省)
しかし、SRC造だからといって必ずしも静かとは限りません。
上階からの足音、隣室からの話し声やテレビの音、外部からの交通騒音など、さまざまな音が生活の中でストレスとなるケースもあります。
とくに建物の築年数や設計、内装材の種類、窓のサッシの性能などによっても、音の伝わり方や聞こえ方は異なります。
騒音によって日常生活に支障が出るような場合には、早めの対策が必要です。
これからSRC造のマンション購入を検討している方にとっても、「静かな住環境」を実現するための基礎知識として役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
👉スマトリの無料診断(1分)
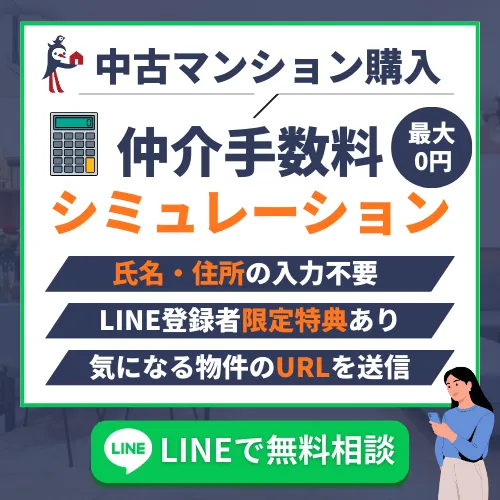
\エリア・物件選びの無料相談も可能/
▶スマトリ公式LINEで無料相談する
目次
SRC造でも「うるさい」と感じるのはなぜか
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)は、数ある建物構造の中でも遮音性に優れており、騒音トラブルが起こりにくいとされています。
そのため、静かな住環境を求めてSRC造のマンションを選ぶ人も少なくありません。
しかし、実際には、「SRC造なのにうるさい」と感じてしまうケースも多いです。
期待していたほどの静音性が得られないことに戸惑う声もあります。
SRC造でもうるさいと感じてしまう要因について、まずは、SRC造の構造的な特徴や、防音に関わる仕組みを正しく理解しましょう。
SRC造の構造的な特徴と遮音性の仕組み
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)は、鉄骨(S)と鉄筋コンクリート(RC)を組み合わせた構造で、主に中高層のマンションやビルなどで採用される建築工法です。
鉄骨による高い強度と柔軟性に、鉄筋コンクリートの耐火性・遮音性・耐久性を組み合わせたもので、構造的に非常に優れたバランスを持っています。
また、遮音性の高さは、SRC造の大きな特徴のひとつです。
SRC造は、壁や床の厚みと重さ(質量)によって音を遮り、隙間の少ない構造と変形しにくい強さ(剛性)によって音の振動も伝わりにくくすることで、遮音性を高めています。
他の構造と比較してSRC構造は遮音性が高い
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)は、RC造(鉄筋コンクリート造)やS造(鉄骨造)と比較して、上記で説明した仕組みにから最も遮音性が高い構造です。
S造は、主に鉄骨で構成されており、構造体自体が軽量なため、音や振動が伝わりやすい傾向があります。
RC造は、コンクリートを使用しており、遮音性は比較的高いですがSRC造と比べると劣ります。
SRC造は、他の構造と比べると質量・剛性・気密性の点で優れており、遮音性に関しては他の構造より性能は高いです。
音のストレスを少しでも軽減したい人にとって、SRC造は有力な選択肢となるでしょう。
古いSRC造や設計により生活音が響く場合もある
SRC造は遮音性が高いと言われていますが、すべてのSRC造のマンションが静かとは限りません。
特に、築年数の古いSRC造のマンションや、設計の工夫が不十分な物件では、思った以上に生活音が響くケースが多いです。
築年数が経つと、経年劣化によって壁に隙間が生じたり、建材の劣化によって遮音性能が落ちてしまったりすることも考えられます。
また、床スラブ(床の厚み)が薄い、間仕切り壁が薄い、配管が壁や床を貫通している箇所の防音処理が甘いといった設計上の要因も騒音の原因になります。
SRC造・RC造・S造の防音性比較
マンションや住宅を選ぶ際、防音性は重要な判断材料のひとつです。
SRC造、RC造、S造など、それぞれの建物の構造によって、音の伝わり方や遮音性能には大きく異なります。
ここでは、SRC造、RC造、S造について、防音性の違いを比較しながら解説します。
SRC造とRC造における遮音性能の違い
SRC造とRC造は、いずれもコンクリートを用いた構造で、一般的に遮音性能は高いとされています。
しかし、SRC造とRC造と比較すると、SRC造のほうが遮音性能は高いです。
RC造は、柱・梁・床・壁などの構造体をすべて鉄筋コンクリートで構成しており、コンクリートの質量と密度の高さによって、音や振動を伝わりにくくします。
一方、SRC造は、鉄骨の周囲を鉄筋コンクリートで覆う構成をしており、鉄骨により構造の剛性(変形しにくさ)が増すため、RCよりも音や振動が伝わりにくくなるというわけです。
鉄骨造(S造)はなぜ音が響きやすいのか
鉄骨造(S造)は、鉄骨を主要な構造材として使用しており、SRC造やRC造と比べて薄い壁や床材が使われています。
他の構造と比べて、質量や密度が低く、剛性も劣るので音が響きやすいというわけです。
そのため、他の構造と比べて、鉄骨造のマンションやアパートでは、上下階や隣戸との遮音に不満を感じるケースが多く、物件を選ぶ際には、建物の防音対策がしっかりと施されているかどうかが重要なチェックポイントになります。
床スラブ厚と壁構造が防音性に与える影響
建物の構造だけでなく、床スラブの厚さや壁の構造も、防音性に大きな影響を与えます。
床スラブとは、上下階の間にある床部分のコンクリート層のことです。
一般的に、厚さが200mm以上あると遮音性能が高いとされており、下階に伝わる足音や振動音を抑えてくれます。
隣の住戸との間の壁(戸境壁)は、厚さや素材によって防音性が大きく変わります。
180mm以上の鉄筋コンクリート壁や鉄骨鉄筋コンクリート壁が使われていれば、防音性は高いです。
鉄骨造では、ALC壁や石膏ボードが使われます。
ALC壁は、発泡材入りの軽量コンクリート板をパネル状にした壁材で、石膏ボードと比べて防音性能が高いとされています。
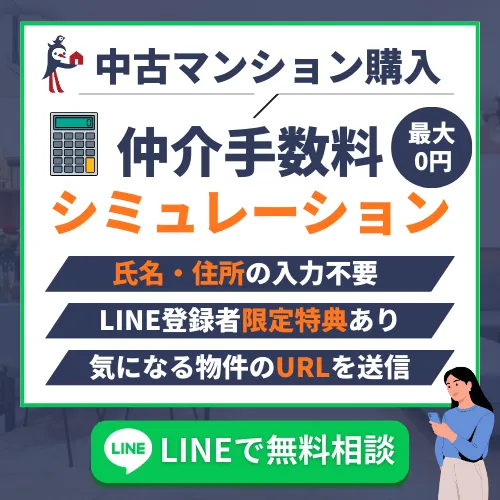
\エリア・物件選びの無料相談も可能/
▶スマトリ公式LINEで無料相談する
部屋で騒音を感じる原因
快適な住まいを求めていても、思ったより音が気になると感じるケースも多いです。
不動産のセカンドオピニオンサイト「住まいサーフィン」のマンションを購入して後悔をしたポイントのアンケートでは、騒音トラブルは2位にランクインしています。
参考:マンション購入で 後悔した理由 ランキング TOP 5(住まいサーフィン)
特にマンションでは、構造や立地、周囲の環境によって、日常的にさまざまな騒音を感じるでしょう。
ここでは、部屋で騒音を感じる主な原因について解説します。
上の階の足音が聞こえてくる
マンションで最もよく挙げられる騒音トラブルの一つが、上階からの足音や物音です。
これは「重量衝撃音」と呼ばれ、子どもが走り回る音や椅子を引く音、物を落とす音などが該当します。
こうした音は、建物の床スラブの厚みや遮音材の有無によって大きく影響されます。
特に築年数の古い物件や軽量鉄骨造の建物などでは、十分な対策が取られていないケースが多いので、購入時には注意が必要でしょう。
隣室の話し声やテレビの音が聞こえる
隣室からの話し声やテレビの音が壁越しに聞こえてくる騒音トラブルも多く見られます。
これは「空気伝播音」と呼ばれるもので、音が空気中を伝わり、壁や天井を振動させて室内に届く仕組みです。
特に、壁が薄い、コンクリートの内部に断熱材や吸音材が入っていない場合は、音がダイレクトに伝わりやすく、騒音トラブルの原因になります。
さらに、配管まわりやコンセントボックスの隙間など、わずかな空洞部分も音が漏れやすい経路となるため、施工のちょっとした違いが騒音の感じ方に影響することもあります。
外の騒音(車・電車・工事音など)が聞こえる
立地環境によっては、外からの騒音が室内に入り込むケースもあります。
たとえば、幹線道路沿いの車の音、線路近くを走る電車の音、周辺での工事などが外の騒音の主な原因です。
このような屋外の騒音も空気伝播音ですが、窓や換気口などを通じて音が伝わります。
特にアルミサッシの一重窓などは、遮音性能が低く、音が伝わりやすいので、より騒音を感じるでしょう。
近年では、複層ガラス(二重サッシ)や防音サッシを取り入れることで、ある程度の外部騒音は軽減できるようになっていますが、物件によっては導入されていないことも多いため、内見時の確認が重要です。
入居者ができる具体的な騒音対策
マンションでは、建物構造や周辺環境に起因する騒音を完全に防ぐことは難しいです。
騒音を防ぐためには、入居者自身が工夫をして騒音対策をする必要があります。
ここでは、日常生活の中で取り入れやすい具体的な騒音対策を紹介します。
床に防音カーペット・マットを敷く
床を伝ってくる重量衝撃音を抑えるには、防音カーペット・マットの設置が有効です。
特に小さな子どもがいる家庭やフローリングの床で物音が響きやすいマンションでは、階下に音が伝わって騒音トラブルになりやすいので、防音カーペット・マットを敷いておくと騒音が軽減されます。
防音カーペット・マットは、柔らかく厚みのある素材を使うことで、足音や物を落とした際の音を和らげられます。
また、防音マットを下地に敷き、その上にラグやカーペットを重ねる「二重構造」にすると、より高い防音効果が期待できます。
厚手のカーテンや吸音パネルを設置する
外からの騒音や反響音を抑えるには、厚手の遮音カーテンが効果的です。
厚手のカーテンや吸音パネルを設置することで、窓まわりの隙間から入ってくる車や電車、工事の音を減少させられます。
また、室内の壁に吸音パネルやフェルトボードなどを貼ると、音の反響を抑え、室内外への音の漏れを軽減する効果もあります。
吸音パネルやフェルトボードは、見た目もインテリアとして楽しめる製品が多く、手軽に取り入れやすいので有効に活用しましょう。
壁際に本棚など大型家具を配置する
隣室からの音が気になる場合は、壁際に本棚や収納棚などの大型家具を配置するのも有効な手段です。
家具自体が壁の代わりとなって、音を遮る役割を果たし、壁から伝わる音を軽減してくれます。
また、本や衣類など中身が詰まっている家具ほど遮音性が高くなるため、実用性と防音性を兼ね備えた対策と言えるでしょう。
窓やドアのすき間にパッキンを貼る
空気伝搬音は、わずかなすき間からでも入り込んできます。
窓やドアのすき間に防音パッキンや隙間テープを貼ることで、空気伝播音の侵入を防ぐ効果的な方法です。
特に古い物件や建具に劣化が見られる住まいでは、気密性が低下している場合が多いので、隙間ができていないかを確認する必要があります。
100円ショップなどで手に入る簡易な素材で対策を講じるだけでも、外から入っている騒音を大幅に軽減できます。
耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを使用する
外部からの騒音がどうしても気になる場合には、耳栓やノイズキャンセリング機能付きのイヤホンを使うのもひとつの方法です。
特に勉強や仕事など集中したい場面や夜間の安眠を妨げる騒音に悩んでいる方には有効な手段と言えます。
ただし、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンは、一時的な対処にしかなりません。
騒音の原因を突き止めて、厚手のカーテンや吸音パネルを設置や防音パッキンや隙間テープを貼るなど、有効な騒音対策を実施しましょう。
\LINE登録者限定無料特典あり/
今すぐ無料特典を受け取る
防音性の高いSRC造物件を選ぶチェックポイント
SRC造は、鉄骨の強度とコンクリートの遮音性を兼ね備えた防音性の高い構造です。
ただし、すべてのSRC造物件が同じ遮音性能を持つわけではありません。
同じSRC構造でも、築年数や床のスラブ厚、使用しているサッシなどによって、防音性能は大きく異なります。
ここでは、より防音性の高いSRC造物件を選ぶための具体的なチェックポイントを紹介します。
築年数が新しい物件
SRC造の性能を最大限に活かすには、築年数が比較的新しい物件を選ぶのがポイントです。
近年の建築基準や技術は進化しており、遮音性に配慮した設計や高性能な建材が使われていることが多いため、防音性の高いマンションが増えています。
一方で、築年数が古い物件では、コンクリートの劣化や隙間の多い設計により、音が漏れやすいケースもあるため注意しましょう。
スラブ厚が200mm以上
床スラブ(コンクリート床)の厚みは遮音性に大きく影響します。
180mm以上あれば有効とされていますが、防音性の高さを求めるなら、目安としては200mm(20cm)以上の厚さが必要です。
ただし、マンションの設計図書や設計図面がないとスラブ厚が確認できないケースもあります。
物件の詳細資料や不動産会社に確認すれば、スラブ厚の情報を得られることもあるので、静かな住環境を求めるなら必ず確認しましょう。
角部屋や最上階
角部屋や最上階は、隣接する住戸が少なくなるため、生活音の影響を受けにくいのがメリットです。
特に角部屋は、隣室が片側しかない場合が多く、壁越しに伝わる空気伝播音を抑えられます。
最上階であれば、上階からの足音などもないため、遮音性の面では最も効果が高い位置と言えます。
ただし、角部屋や最上階は、人気が高いので、物件価格が他の部屋よりも高くなっていることが多いです。
どうしても防音性を重視したい人は、予算と相談しながら決めましょう。
複層ガラスや防音サッシがある
外部からの騒音対策として大事なのが窓まわりの仕様です。
一般的に使用されているアルミサッシの一重窓などは、遮音性能が低く、騒音を感じやすいので、音に敏感な人は、遮音性の高い複層ガラス(二重ガラス)や防音サッシは重要な設備と言えます。
複層ガラス(二重ガラス)や防音サッシが採用されている物件は、道路や鉄道、近隣の音を大幅に軽減できます。
特に防音サッシには、音の周波数をカットする構造が取り入れられており、交通量の多いエリアや幹線道路沿いの物件では必須の設備です。
近年では、国土交通省が子育てグリーン住宅支援事業で既存窓を使って複層ガラスへの交換をするのに補助金を出すなど、築年数の古いマンションでも導入されているケースが増えています。
参考:開口部の断熱改修【リフォーム】 – 子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)
商業施設や幹線道路の有無
商業施設や幹線道路と隣接しているマンションは、どれだけ建物の防音性能が高くても、周辺環境からの騒音は避けられません。
駅近マンション周辺は、商業施設や幹線道路が多いので、物件選びの際には特に注意が必要です。
物件周辺に商業施設や幹線道路、線路、学校、工事エリアなどがある場合は、窓や壁を通じて音が入り込む可能性があるため、ベランダの向きや使用されているサッシの確認も忘れずにチェックしましょう。
内覧時に、昼夜の騒音レベルや交通量などを確認しておくと、入居後のトラブルを防ぐことができます。
【無料】住まい購入の相談はスマトリがおすすめ!

・仲介手数料最大無料
・氏名や住所の入力不要
・電話やメールの営業なし
スマトリのLINE相談では、AIではなく経験豊富な担当者が対応してくれるので、不動産の購入が初めての人でも安心して利用できます。
気になる物件が既にある方は、仲介手数料無料かどうかをお気軽に判定可能です。
「仲介手数料無料って本当?」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、まずはスマトリのLINE相談を活用してみてください。
SRC造は、質量・剛性・気密性の点で優れており、RC造や鉄骨造と比較すると遮音性能と防音性能の高い構造です。
しかし、SRC造でも、築年数やスラブ床や壁の厚み、使用されているサッシなどによって、遮音性能と防音性能に差があります。
内覧時には、実際に壁や床を叩いた際の音の響き方や複層ガラスや防音サッシが使われているかなどをチェックしましょう。
また、商業施設や幹線道路などの周辺環境も騒音においては重要なポイントです。
実際に現地に行かなくても、地図アプリなどを使って、周辺の状況を確認することもできるので、内覧前にチェックしましょう。
これからSRC造のマンションの購入を検討している人は、今回の記事を参考に、防音性の高い物件を選んでいただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。












