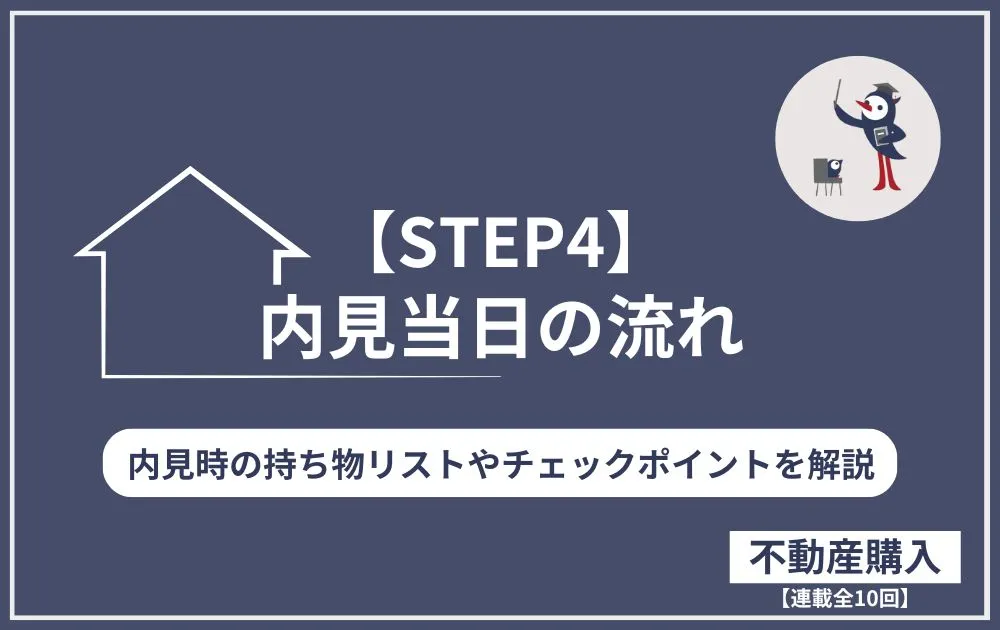マンションで住んではいけない階はある?階層別の特徴や注意点を解説
「自分にとって住み心地のよい階は何階だろう」「マンションでやめておいたほうがいい階や住んではいけない階ってある?」
などマンションの購入を検討している方にとって、住む階数が生活環境にどう影響するのか不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
低層階や中層階、高層階とそれぞれの階で日当たりや風通し、防犯面、災害時の不安などにおいて違いがあります。
この記事では、マンションの階層の違いによって変わってくる住みやすさや特徴について解説します。
目次
マンションで住んではいけない階はないが、各階に特徴がある
マンションは、階によって住み心地や環境が異なります。
住んではいけない階の明確な定義はありませんが、住む人の家族構成や条件によって住むべきではない階数もあるといえるでしょう。
各階の特徴をよく理解し、自分や家族にとって快適に過ごせる階を把握しておくことが大切です。
マンションの階数が住みやすさに与える影響
住む階数によって、住みやすさはどう変わってくるのでしょうか。
自分がどういった点を優先させるかによって選ぶべき階は絞られてきます。
この項では、階によって異なる住み心地や環境について解説します。
騒音や生活音の問題
階層によって、生活音や様々な騒音の問題は異なります。
低層階では通りを歩く人や車の音、緊急車両のサイレンなどが聞こえたり、共用部分の音が聞こえやすかったりします。
一方で、高層階では周辺に音を遮るものがないため、遠くの雑音が低層階以上に聞こえてしまう場合があります。
同じ敷地でも、地上に近い低層階と高層階では聞こえる騒音が異なるのです。
また、2階以上の住戸では足音などの騒音トラブルが発生する可能性があるため、生活音への配慮が求められるでしょう。
日当たりの良さと室温の変化
マンションの階層によって、日当たりの良さや室温の上がり方に違いがみられます。
高層階は日当たりが良く、部屋の向きにもよりますが日中は電気を付けなくても明るく過ごせます。
差し込む日差しによって、冬でも気温がひどく低くなることはないでしょう。
ただし、夏場は室温が上がりやすくなるので注意が必要です。
低層階は他の建物によって日陰になりやすく、暑い時期でも比較的涼しく過ごせますが、冬場は地面が近いこともあって下からの冷気で寒くなる傾向にあります。
防犯面のリスクとプライバシーの問題
マンションの住む階によって、防犯面のリスクやプライバシーの確保といった点で違いがでてきます。
低層階は、高層階と比べて空き巣などの侵入リスクが高くなります。
特に1階で囲いなどの目隠しが不十分なマンションの場合、外から部屋の中を確認しやすいため留守を狙われる可能性もあるでしょう。
窓用補助鍵を設置する、外出の際にはしっかり鍵をかけるなど防犯対策を意識する必要があります。
高層階の場合は不審者が侵入する可能性が低いため、防犯のリスクは少ないといえるでしょう。
また、高層階は外部からの視線が届きにくいため、プライバシーの確保という面でもメリットがあります。
ただし、災害時にエレベーターが使えなくなった場合など、高層階は避難が困難になる可能性があります。
長い階段をひたすら下りなければならないので、高齢者や小さな子どもにとっては大きな負担となってしまいます。
低層階の特徴と選び方
低層階を選ぶ際に最も大きなポイントは、エレベーターの待ち時間が少ない、もしくは利用しなくても生活できるという点です。
外出、帰宅のたびにエレベーターを待つ必要があると、外出が面倒になってしまうケースもあります。
低層階ならば、階段で上り下りしても負担が少ないでしょう。
この項では、低層階の特徴や低層階が向いている人の特徴について解説します。
アクセスの良さと防災の安心感
低層階には、外出に際してのアクセスのよさ、防災の面で安心感があるといった利点があります。
低階層であれば、階段を利用できるため、エレベーターが混み合う通勤や通学の時間でもエレベーターを待つ必要がありません。
エレベーターに乗らなくても外出や帰宅ができるので、急いでいる場合でもストレスを感じることはないでしょう。
また、災害時の停電などでエレベーターが使えなくなってしまうと、階段を利用するしかないため、高層階では負担が大きくなります。
低層階ならば、災害時の避難の他、買い出しなど頻繁な外出でも困難を感じることはありません。
虫の侵入や防犯リスク
低層階は地面が近いことで、虫の侵入リスクが上がります。
特に周囲に緑豊かで土がある場所や、ゴミ置き場などといった箇所から発生した虫が侵入しやすくなります。
また、低層階は侵入されやすいといった防犯面でのリスクが高い傾向にあります。
窓やベランダが手に届きやすい所にあったり、足場になるような植栽などが伸びていたりすると特に危険です。
人感センサーによるライトの設置、窓に防犯フィルムを貼るなどして対策をするようにしましょう。
低層階が向いている人の特徴
低層階であれば、エレベーター待ちで悩む必要がほとんどありません。
子育て中の家庭や、頻繁に外出する方、エレベーターの使用を避けたいと考えている方に向いているといえるでしょう。
他にも以下のような人が低層階に向いています。
・住宅ローンの費用を抑えたい
・日当たりや眺望をそれほど重視しない
・災害時に避難がしやすい
・外に出るのが面倒にならない高さの部屋がいい
・高い所が苦手
マンションは低層階ほど購入価格が安くなる傾向があります。
子どもが多い家庭や、進学を控えている子どもがいる家庭など、住宅ローンを少しでも抑えたいと考えている人には向いているでしょう。
また、日当たりや眺望を重視しないのであれば、外出時の手間、災害時の避難の心配がないという点で低層階がおすすめです。
中層階の住みやすさと注意点
マンションの中層階は、低層階と高層階の両方の特徴を程よく含むので、住み心地のバランスが良い階といえます。
この項では中層階の特徴や、ライフスタイルにより中階層が向いている人について解説します。
外部からの視線が気になりづらい
中層階は低層階の住戸と比べると外からの視線が届きにくいため、プライバシーが守られやすいといった特徴があります。
道路を歩いている人の気配や視線も気になりません。
中層階は、落ち着いて過ごせる環境であるといえるでしょう。
ただし、同じように高い建物が近くにある場合には窓の高さも似たような位置になるため、視線が合うことがあります。
騒音やプライバシーの問題
上下階や隣の部屋からの音が気になりやすい場合があり、防音対策が必要なケースもあります。
自分たちの部屋から声や音が他の部屋に伝わるという場合もあるでしょう。
個人のプライバシーの権利が侵害されるといったプライバシーリスクにも注意が必要です。
中層階が適しているライフスタイル
低層階と高層階のメリットとデメリットを少しずつ合わせ持つ中階層は、バランスの取れた住宅を手に入れたい方に向いています。
中階層は、室内の気温の変化が穏やかです。冬は低階層よりも暖かく、夏は高階層よりも涼しく過ごせます。
エレベーターを使わない生活は難しいですが、エレベーターが停電や故障で利用できなくなった場合でも、階段で対応しきれない高さではありません。
他にも中階層には以下のような特徴があります。
・日当たりと風通しが良好
・防犯面でのリスクが低い
・洪水時など、床上浸水する可能性が低い
・高階層よりも価格が低め
日当たりと風通しが比較的良好で、価格もある程度抑えたいと考えている人は中階層が向いているといえるでしょう。
また、部屋の位置が高いことから空き巣などの被害に遭うリスクや、洪水時に浸水する可能性が少なくなります。
防犯面、価格、住み心地などのメリットをバランスよく得たい人には中階層がおすすめです。
高層階の魅力とリスク
高層階は眺望や日当たりがよく、人気があります。
防犯性が高いといった点でも魅力のある階でしょう。
一方で、災害時の影響をうけやすいといったデメリットも存在します。
この項では、高層階の魅力と気をつけておきたいデメリットを解説します。
眺望の良さと優れた防犯性
高層階は、開放的な眺望と防犯面での安心感を兼ね備えています。
周囲に高い建物がなく、視界を遮るものがなければ開放的な眺望が楽しめます。
採光に不満を持つこともないでしょう。
また、低階層、中階層に比べて外からの侵入がされにくいのもメリットのひとつです。
ただし、高層階でも屋上からベランダに侵入したり、高い木や電柱などを利用したりして侵入される可能性もあります。
どの階であっても、防犯対策は日頃から心がけておくことが大切です。
災害時の影響を受けやすい
マンションの高層階は、地震の揺れが低階層よりも大きく揺れる傾向にあります。
また、停電時のエレベーター停止などにより、災害時の影響を受けやすいことが特徴としてあります。
高層階では、防災対策が欠かせないといえるでしょう。
次項で、高層階に住む際に必要な防災対策をご紹介します。
高層階に住む際の防災対策
高層階に住む場合、大きな揺れによる被害や停電などにより避難できず、生活に大きな支障をきたすケースがでてきます。
以下は、災害時に備えてとっておくべき防災対策です。
・転倒防止器具などを大型の家具に設置し、転倒を防ぐ
・ガラスに飛散防止フィルムを貼る
・最低3日以上、できれば一週間以上の食料や飲料水を備蓄する
・日用品も備蓄しておく
・枕元に靴を用意しておく
まずは家具の転倒やガラスの飛散を防止し、身を守る対策をとっておきましょう。
階段を利用しての外出も困難となるので、備蓄品もしっかり準備しておくことが大切です。
また、枕元には必ず靴を用意しておきましょう。
地震の際はガラスや食器などが割れ、破片が床に散らばっていることが多くあります。
破片で足を怪我してしまい、避難や移動が困難とならないように靴を準備しておくことが重要です。
そのほか避難手順の確認や、家族とはぐれてしまった場合の集合場所なども話し合っておくとよいでしょう。
階数選びで失敗しないためのポイント
階層選びで失敗しないためには、階層の特徴を把握し、自分のライフスタイルにあった環境を選ぶことが大切です。
この項では、階数を選ぶ際のポイントを解説します。
ライフスタイルに合った階数を選ぶ
家族の状況や、ライフスタイルに合わせて適切な階数を選ぶことが大切です。
低層階は、外出時に労力や時間がかからないため、小さな子供や高齢者がいる家庭におすすめです。
一方で、高層階は静かな環境を望む単身者の方や、在宅時間が長い方に向いています。
日当たりや眺望、騒音問題も少ないため快適に過ごせるでしょう。
また、階数を選ぶときは、購入時の状況だけでなく、将来のライフスタイルの変化も見据えておくことが大切
です。
今後生活に変化があっても、階層の特徴にメリットを感じ、快適に過ごせるか検討しておくことが重要でしょう。
共用施設と部屋の距離を確認する
ジムやゴミ置き場、エレベーターなどマンションの住人が共同で使う共用施設と部屋の距離を確認しておきましょう。
静かさを重視するならば、他の住人も利用する共用施設からは遠い部屋を選ぶことが大切です。
また、ジムを頻繁に使用する場合はジムが近い部屋を、ゴミ捨てを楽にしたいならばゴミ置き場が近くにある部屋を、というように選択するのもおすすめです。
利便性と静かさのバランスを考慮して、自分に合った階や部屋を選ぶようにしましょう。
避難経路や防災設備を確認する
災害時の避難ルートや防災設備の確認をしっかりしておきましょう。
マンションは建築基準法により2ヵ所以上の避難経路を用意しなければならないと定められています。
普段利用する入り口とは別に非常口と階段があったり、バルコニーに避難ハッチが備わっていたりします。
避難時に不安がある高層階では特にしっかりと避難経路や防災設備を確認し、安心して暮らせる環境かどうか見極めることが必要です。
周辺環境と騒音レベルを確認する
にぎやかな繁華街が近くにあったり、交通量の多い道路が目の前にあったりすると騒音に悩まされる可能性があります。
階数だけでなく、周囲の騒音や環境が住み心地に大きく影響するので事前に確認しておくことが重要でしょう。
また、玄関やエントランスに設置されている掲示板などに、騒音に関する貼り紙がないかどうかも確認しておく必要があります。
貼り紙がある場合は、現在、マンションで騒音問題が起きている可能性があります。
将来の資産価値や売却時の需要を考える
購入時だけでなく、将来の売却を見据えた階数選びも重要です。
近い将来に売却の予定がなかったとしても、資産価値の下がりにくいマンションを選ぶようにしましょう。
購入したものを再販売するときの価値であるリセールバリュー(※)にも関わってくるため、人気が高い階数や、需要が見込まれるエリアの選定が重要です。
最上階は資産価値が高いので、将来的に売却を検討している人には向いている階です。
また、駅までのアクセス、利便性、周辺環境、立地などに優れたマンションも資産価値が高い傾向にあります。
ただし、リセールバリューが高い物件は価格も高くなる傾向にあります。
マンション選びでは「家族で快適に生活すること」が最優先となるので、予算や環境の面で家族が望む条件と異なっている場合は、他の選択を検討するのもひとつの方法です。
※リセールバリュー:築10年前後のマンションの資産価値を示すひとつの指標。
まとめ
この記事では、マンションの階層によって異なる特徴や、階層選びで失敗しないためのポイントを解説しました。
階層によって、環境や住み心地に違いがあります。
「住んではいけない階」というのはありませんが、自分や家族の価値観、生活スタイルによって最適な階を選ぶことが大切です。
また、マンションを選ぶ際には内見もしっかりしておきましょう。
日当たり、風通し、電波の入り具合などを実際に確認しておくことが重要です。
日当たりなどは時間帯によって印象が変わるので、内見はできれば時間を変えて2回おこなうことをおすすめします。
周辺環境や騒音などのチェックも忘れずにしておきましょう。
内見時に必要な持ち物や確認しておきたいチェックリストの記事もオススメです。
この記事を参考に、自分が快適に過ごせるマンションの階層を検討してみてください。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。