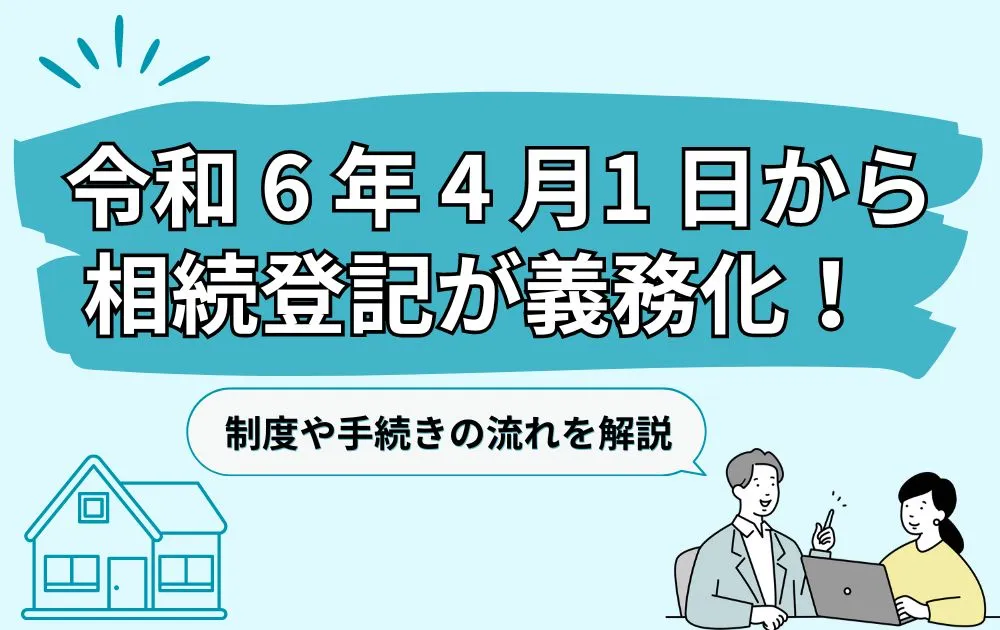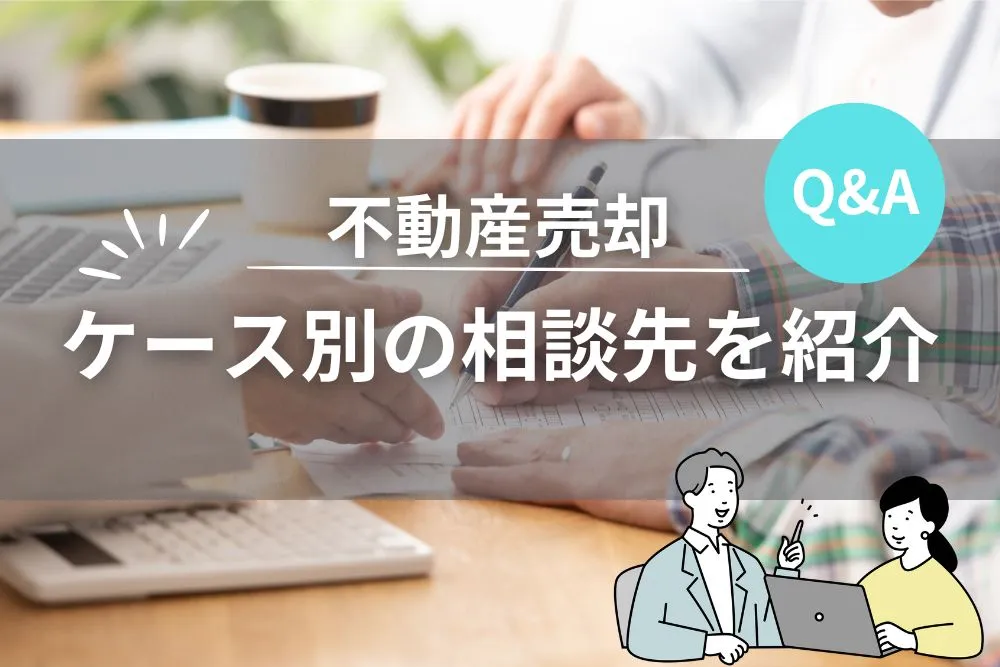空き家を放置するリスクとは?発生するリスクと活用方法を詳しく解説
「実家を相続したけれど、遠方なので空き家のまま放置している」「空き家を持っているが税金が高くなると聞いて不安になっている」など、相続で空き家を取得したが活用方法がわからずに困っているといった人も多いでしょう。
2023年時点で日本全国の空き家は900万戸にのぼり、2018年から51万戸の増加、空き家率も13.8%と過去最高を記録しました。
人口減少や高齢化による過疎化が進んだことも空き家が増加した大きな要因ですが、相続した後も自宅で生活していることから活用せずに放置している方もおられるでしょう。
空き家を放置することで発生するリスクは非常に多いです。
税金の支払いや修繕、維持に費用がかかるといったコスト面だけでなく、地震や台風による倒壊リスク、不審者が侵入するといった防犯上のリスクをすべて所有者が負う必要があります。
空き家は放置するとリスクが多いので、活用または売却して処分するなど対策が必要です。
今回は、空き家を放置することで発生するリスクと活用方法について詳しく解説します。
現在空き家に悩んでいる、地方にいる親の物件を相続する予定があるといった人は最後まで読んでいただければと思います。
参考:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果 (総務省)
日本全国の空き家は2023年時点で900万戸にのぼる
ここでは、空き家の問題点と空き家対策特別措置法の内容について詳しく解説します。
空き家は固定資産税と都市計画税を支払う必要がある
不動産を所有していると不動産のあるエリアの自治体から固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。
これは空き家であっても同じです。
空き家を所有するデメリットのひとつが固定資産税と都市計画税といったランニングコストと言えます。
固定資産税と都市計画税は課税標準額に税率を乗じて計算されます。
固定資産税の計算方法
課税標準額(固定資産税評価額) × 1.4%(標準税率)
都市計画税の計算方法
課税標準額(固定資産税評価額) × 最高0.3%(制限税率)
固定資産税評価額は、自治体の長が不動産の価値を評価し算定した価額です。
基本的に固定資産税評価額と課税標準額は同じですが、土地については、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などにより調整されるので異なることがあります。
深刻化する空き家問題を解決するための国の制度がある
空き家問題は年々深刻化しており、国としても国土交通省が2015年5月に空き家対策特別措置法を施行するなど対策を実施しています。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されて以降も空き家は増えており、更なる対策として2023年に改正空き家対策特別措置法が施行されました。
改正空き家対策特別措置法では、放置することで公的に不利益がある空き家について、自治体が管理不全空き家、特定空き家と認定し、改善勧告、最終的には解体といった公権力の介入が可能です。
参考:空家等対策特別措置法とは(NPO法人 空家・空地管理センター)
管理不全空き家と特定空き家は指導・勧告の対象
自治体から管理不全空き家または特定空き家に指定されると指導・勧告の対象です。
空き家対策特別措置法では、特定空き家のみでしたが改正空き家対策特別措置法で新たに管理不全空き家という区分が追加されました。
管理不全空き家と特定空き家の定義は以下のとおりです。
【管理不全空き家】
1年以上誰も住んでおらず、管理が不十分な家で今後もそのままの状態だと特定空き家に指定される恐れのある空き家
【特定空き家】
1年以上誰も住んでおらず、管理が不十分な家で今後もそのままの状態の空き家
特定空き家に指定するには、自治体もかなりの労力がいることもあり、早い段階で行政が加入しやすいように管理不全空き家を定義したというわけです。
特定空き家は以下の要因にあてはまる場合に指定される可能性があります。
・そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となる状態
・著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
管理不全空き家や特定空き家に指定されると自治体より助言、指導、勧告、命令の順番で行政指導が行われます。
| 助言 | 自治体より適正管理を行うための助言を行う。 法的効力はない。 |
| 指導 | 助言によって改善されない場合に助言よりも強く適正管理を促す。早急な管理状況の改善が必要。 |
| 勧告 | 指導でも改善されない場合は指導よりも強い勧告が行われます。 固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、従来の土地の税金6倍を支払う必要があります。 |
| 命令 | 勧告によって改善されない場合、最終段階として命令が行われます。 命令は行政処分にあたり、空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金です。 |
勧告を受けた空き家を放置すると固定資産税の優遇措置が適応されなくなるので、従来の土地の固定資産税の6倍の金額を払う必要があります。
更に重い命令の場合は、対応しないと50万円以下の罰金です。
また、空き家を放置することで建物が倒壊、外壁落下、火災などによって、ケガや周辺の住宅に損害を与えて場合は損害賠償などの費用が発生する恐れもあります。
空き家対策は早めに行うことが重要になります。
倒壊の恐れなど管理不全空き家や特定空き家に指定される可能性がある場合は、修繕または解体を行う、売却や賃貸するなどの対策が必要です。
何から行うべきか迷う場合は、国土交通省が提供している「空家リスクチェックリスト」を活用するとよいでしょう。
空き家を放置することで発生するリスク
空き家を放置することでさまざまなリスクが発生します。
自身の負担が増えるだけでなく、景観の悪化や倒壊によるケガなど周囲への影響には特に注意が必要です。
どういったリスクがあるかを把握し、トラブルを防ぐためにも早めに対策しましょう。
ここでは空き家を放置することで発生する7つのリスクについて解説します。
周囲環境の景観が悪化する
空き家を放置することで、建物や植栽などの管理を怠ると周囲環境の景観の悪化が進みます。
建物は人が住んでいないと通風などが行われないので傷みが早く、外壁の剥がれや屋根の瓦が落ちるなど見た目も悪くなります。
庭付きの空き家だと植栽があることが多く、放置すると無造作に草木が伸び、最悪の場合は周辺の家に越境して迷惑をかけます。
また、老朽化した空き家を放置するとゴミの廃棄場所になってしまうケースも多いです。
空き家を維持するには、定期的に訪問して通風を行う、植栽の手入れをする必要があります。
税金の特例が適用されない場合がある
管理不全空き家または特定空き家に指定されると土地の税金の特例が適用されない場合があります。
空き家のある自治体は、倒壊の恐れなど一定の条件を満たす空き家に対して管理不全空き家と特定空き家に指定することで行政指導を行います。
行政より勧告を受けると固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、従来の土地の税金6倍を支払う必要があります。
勧告を受けても改善せず、さらに命令を受けても改善しない場合は、50万円以下の罰金です。
管理不全空き家または特定空き家に指定された場合は、早急に管理の改善、解体や売却などの対策を取る必要があります。
地震や台風で倒壊する可能性がある
空き家を放置すると地震や台風で倒壊する可能性があります。
空き家は老朽化していることが多く、地震や台風が起こると建物の損壊や倒壊する可能性が高いです。
倒壊によって通行者にケガをさせる、隣家に被害を与えると損害賠償を請求される恐れもあります。
空き家を維持するためには、地震対策や台風対策を事前に行っておく必要があります。
不審者が侵入して治安が悪化する
空き家に不審者が侵入することで治安が悪化してしまうこともあります。
不審者たちが空き家を利用し、薬物などの違法な商品の受け渡しなど犯罪に悪用されるケースが増えています。
また、不審者が空き家に住み続けることで火災の原因になることも考えられます。
不審者は老朽化した人の出入りの空き家を狙うことが多いです。
空き家を維持するためには、自分または隣人に定期的に室内を確認できる環境を整える必要があります。
近隣住民との間にトラブルが起きる
空き家を放置すると近隣住民との間にトラブルが起こる可能性が高まります。
景観の悪化、建物の倒壊や植栽の越境など、空き家は管理していないと多くのトラブルの元です
トラブルが起こってしまうと対応に時間を取られて仕事どころではありません。
親から空き家を相続した場合は、自身が住んでいたり、定期的に子供を連れて里帰りしたりと近隣住民と面識があると思いますので、何かあった場合は連絡してもらえるような関係性を築いておくと良いでしょう。
空き家の修繕や維持のコストがかかる
空き家の修繕や維持にはコストがかかります。
自宅のローンや管理費・修繕積立金の支払いがある場合は、追加で空き家の費用も捻出する必要があるので大変です。
空き家の修繕や維持にかかるコストには以下のようなものがあります。
・固定資産税・都市計画税
・外壁や屋根などの修繕費用
・地代(借地の場合)
・水道光熱費
・定期的な管理に通うための往復交通費
・火災保険料など
・剪定や除草・除雪等の費用
・町内会費
ただ持っているだけでもこれだけの費用が掛かります。
空き家については、利用する予定がない場合は維持するのか、解体または売却するのかを早めに決める必要があります。
修繕や維持の後に解体するなど、二度手間にならないように対応することが大切です。
害虫が発生して不衛生になる
空き家を放置すると害虫が発生して不衛生になる点にも注意が必要です。
人が住まないとねずみやゴキブリが増えたり、草木が伸びることで蜂や蟻などの害虫を呼び寄せたりします。
大きなハチの巣が出来たりすると行政に駆除をお願いするなど手間もかかります。
また、建物に関しては、建物に最も被害を与えるシロアリが発生する可能性も高いです。
建物がシロアリの被害を受けると売却の際に対処する必要があるので費用もかかります。
害虫が発生しないように管理を行うのは大変です。
害虫が発生する前に空き家対策をしないと空き家の維持は難しいでしょう。
空き家を放置せずに活用する4つの方法
空き家を放置するリスクは多く、管理不全空き家または特定空き家に指定されないためにも早期に対応することが重要です。
しかし、実際にはどのように対応すればよいかがわからないという人も多いと思います。
ここでは空き家を放置せずに活用する4つの方法について詳しく解説します。
空き家の管理を継続する
空き家の管理を自身で継続して行う方法です。
管理の内容としては、建物の維持と植栽の剪定などがあります。
建物が傷んでいる場合は、改修工事(リフォーム)が必要になります。
また、築年数が古い物件などは維持費が高額になりやすいことにも注意しましょう。
空き家を解体して更地にする
建物の倒壊など周囲に迷惑をかける可能性がある場合は、空き家を解体して更地にするのもひとつの方法です。
リスクとなる建物を無くせばリスクそのものを排除できます。
ただし、建物を解体して更地にすると建物の固定資産税はなくなりますが、土地にかかる税金の特例がなくなる点には注意しましょう。
建物を残した方が税制上は有利な場合もあるため、更地にする場合は事前に税金のことを確認しておくことが重要です。
空き家を中古物件として売却・貸出する
空き家の状態が良ければ、中古物件として売却、貸出する方法もあります。
売却する方法には、建物を解体して更地として売却する、古家付き土地で売却するといった方法が一般的です。
建物の状態が良い場合は、中古戸建てとして売り出せば、土地で売却するよりも高値で売却できます。
また、貸出する場合は、事前に改修を行うなど借り手が付くように準備する必要があります。
空き家の事業やサービスを利用する
地方自治体が行う事業やサービスを活用することも選択肢の一つです。
それぞれの地方自治体において、遠隔地在住の方々への相談方法拡充や空き家バンクの設置などの空き家対策の事業やサービスが展開されています。
地自法自治体の空き家の事業やサービスについては、国土交通省の住宅市場を活用した空き家対策モデル事業で確認できます。
最後に
今回は、空き家の現状とリスクや活用方法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
人口減少と高齢化により、国内の空き家の数は年々増加しており、これから親から空き家を相続する予定がある人も多いはずです。
空き家を放置するリスクは高く、早急に活用方法を検討する必要があります。
空き家については、管理不全空き家または特定空き家に指定される前に対策することが重要です。
対策方法としては、空き家の管理を維持することは難しいと思うので、不動産会社に相談または地方自治体の空き家事業やサービスを利用して売却するのが良いでしょう。
現在も空き家問題を抱えている人、これから空き家を相続する可能性がある人は、今回の記事を参考に早めに空き家対策をしていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。