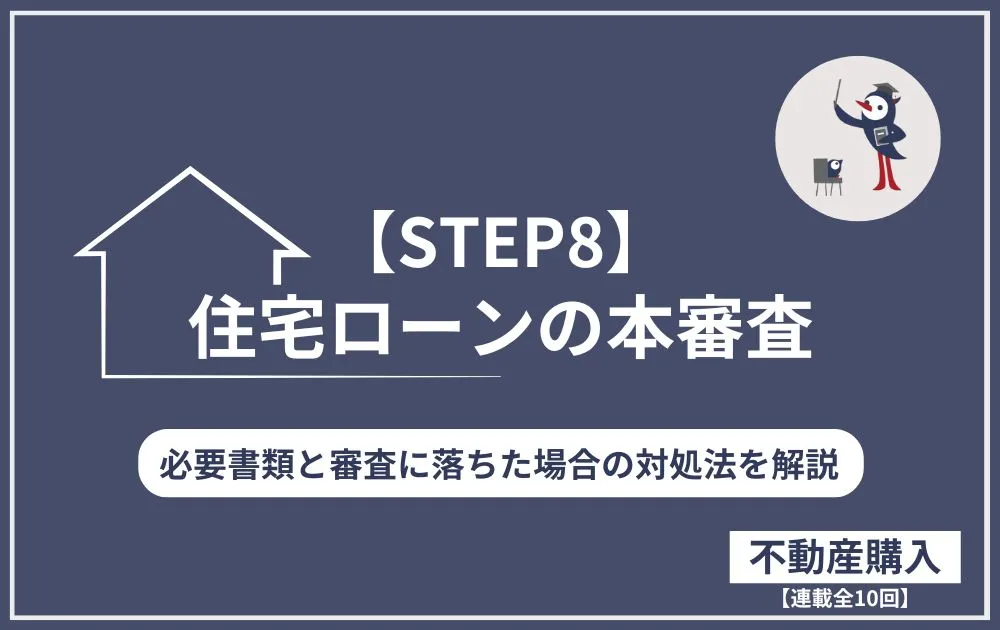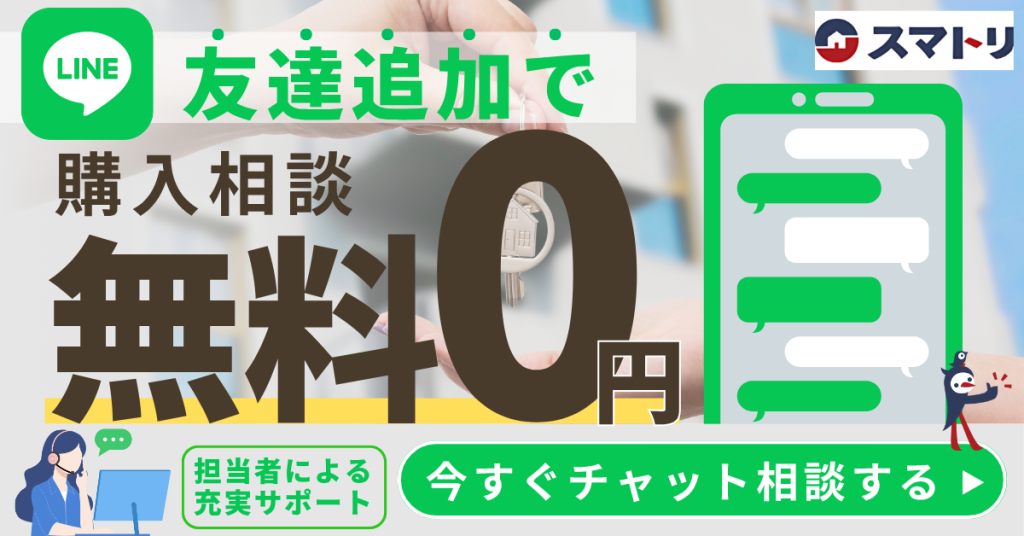築30年の中古マンションは固定資産税がいくら必要?計算方法を解説
「中古マンションは築30年を越えると固定資産税は安くなる?」「固定資産税って控除できるの?」など、中古マンションの売買において固定資産税について知ることは重要なポイントのひとつと言えるでしょう。
固定資産税が高いと生活への影響も大きいので気になる人も多いかと思います。
マンションや戸建てなどの不動産を所有していると、固定資産税を毎年支払う必要があります。
固定資産税は所有している不動産が位置する市町村に納める地方税です。
中古マンションの固定資産税額は、築年数や建物の再建築価格などを元に計算されます。
また、固定資産税は条件を満たすと特例措置を受けられるケースもあるので、土地の購入やリフォームをする場合は事前に確認しておく必要があります。
今回の記事では、中古マンションの固定資産税の基礎知識や特別措置について詳しく解説します。
所有している不動産の固定資産税が気になる、これから中古マンションの購入を検討している方は最後まで読んでいただければと思います。
目次
中古マンションの所有者は毎年固定資産税を支払う必要がある
中古マンションの所有者は毎年固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産の所有者に課せられる税金です。
その年の1月1日の固定資産の所有者が納税対象者となり、固定資産のある市区町村に納めます。
固定資産は以下のとおりです。
| 固定資産の種類 | 例 |
| 土地 | 田んぼ、畑、住宅地、池や沼、山林、牧場、原野などの土地 |
| 家屋 | 住宅(戸建やマンション)、店舗、工場、倉庫などの建物 |
| 償却資産 | 会社等が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具、備品(パソコンや工具)など |
固定資産税の支払いは毎年4月以降に送付される固定資産税納税通知書に基づいて行います。
納税通知書には固定資産税額を決めるための基準となる課税標準額が記載されていますが、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村の長が評価して決定しています。
課税標準額は3年に一度の見直しを行っており、次の見直しは令和6年です。
中古マンションの固定資産税額を決定する主な3つの要素
中古マンションの固定資産税額を決定する主な要素は中古マンションの築年数、土地の固定資産税評価額、建物の再建築価格の3つです。
対象となる中古マンションを3つの要素で評価し、土地、建物のそれぞれの固定資産税評価額を算出します。
固定資産税評価額は不動産取得税や登録免許税の税額の基準になる重要な指標です。
ここでは、中古マンションの固定井資産税額を決定する3つの要素について解説します。
中古マンションの築年数
中古マンションの評価額は築年数が経過するごとに減額されますが、その割合が減価補正率といいます。
減額補正率は、鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの建物の構造によって異なります。
築年数が経過するほど減額されますが、減額補正率の下限は建物の再建築価格の20%が目安です。
中古マンションの場合は築45年で下限に到達します。
土地の固定資産税評価額
土地の固定資産税は、土地の固定資産税評価額(課税標準額)を元に計算します。
計算方法は以下のとおりです。
土地の固定資産税額=土地の固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税額)
土地の固定資産税評価額は、国が発表している地価公示価格の70%が目安です。
地価公示価格は、全国約26,000の地点の1月1日時点の価格を不動産鑑定士が評価したもので、毎年3月に発表されます。
およその金額を知りたい場合は、近隣の公示価格を確認して上記の目安で計算するとよいでしょう。
固定資産税の評価額の算出基準や方法については、固定資産税評価額の調べ方は?計算方法や見方を分かりやすく解説をご確認ください。
建物の再建築価格
中古マンションにおける建物の固定資産税評価額は、建物の再建築価格を基準に算出します。
建物の再建築価格とは、その建物を新築する場合に必要な建築費用のことです。
実勢の価格とは異なる点には注意しましょう。
固定資産税評価額の目安は、新築時には家屋の建築費の50%~60%程度ですが、その後は経年に応じて経年減価補正率を乗じて算出します。
築30年中古マンションの固定資産税額のシミュレーション
実際に築30年の中古マンションの固定資産税額をシミュレーションしてみましょう。
シミュレーションの条件は以下のとおりです。
・中古マンション
・築年数:30年
・専有面積:75㎡
・土地の固定資産税評価額:950万円
・建物の再建築価格:2,700万円
土地については上記で説明した計算式で算出します。
です。
土地の固定資産税額=950万円×1/6×1.4%(標準税額)=22,166円
建物の固定資産税額は、建物の固定資産税評価額に経年減価補正率、標準税額(1.4%)を乗じて計算します。
建物の固定資産税額=2,700万円×0.3059(経年減価補正率)×1.4%=115,630円
固定資産税額の合計:137,000円(100円未満切捨)
経年減価補正率については、法務局の経年減価補正率で確認ができます。
築30年の中古マンションが売れづらい5つの理由
中古マンションを売却する際には築年数は重要なポイントです。
築年数が古いほど中古マンションの売却は難しくなります。
特に、築年数が30年を過ぎた中古マンションの場合は、建物設備の劣化具合や建物の耐震性能について気になる人も多いでしょう
ここでは、築30年の中古マンションが売れづらい5つの理由について解説します。
建物の設備が経年劣化している可能性が高いから
築30年の中古マンションは、建物の設備が経年劣化している可能性が高いです。
建物設備が経年劣化していると建物設備の交換や修繕が必要になります。
建物設備の交換や修繕が行われていないと、将来的に管理費や修繕積立金が値上がりする可能性もあり、築30年のマンションは売れづらいというわけです。
中古マンションについては、一般的に12年~15年程度の周期で大規模修繕工事を行います。
管理のよいマンションであれば大規模修繕工事の際に設備の交換や修理を行っているケースが多いです。
築年数の古いマンションを購入する際には、売却も見据えて定期的に大規模修繕を行っているかを確認しておく必要があります。
大規模修繕工事の履歴については、マンションの管理組合または管理会社が発行してくれる重要事項調査報告書で確認が可能です。
販売先の不動産会社が取得していることが多いので購入前には必ず入手しましょう。
住宅ローンの審査に通りづらいケースがあるから
築30年のマンションの場合、住宅ローンの審査に通りづらいケースも多いです。
住宅ローンの審査では、個人の属性の他に建物の担保価値も確認します。
中古マンションの場合は、築年数の制限を設けていない金融機関がほとんどですが、一部の金融機関では築年数が古いと住宅ローンの返済期間や借入金額の制限を受ける場合があります。
住宅ローンの審査が通りづらいのは、あくまで一部の金融機関なので制限のない金融機関を探すとよいでしょう。
メンテナンス費用がかかることが予想されるから
築30年のマンションの場合、室内の設備などメンテナンス費用がかかることが予想されます。
室内の設備については、築10年を過ぎると故障が増えます。
そのため、中古マンションの場合は住んでから15年程度で設備の入れ替えなどのリフォームが必要です。
しかし、キッチンやお風呂などの水回り関連は交換に費用がかかるので、修理をするなどして購入時のままで使っているケースも多々あります。
やはり、購入してからメンテナンス費用がかかる物件は売れづらいです。
メンテナンス費用がかかる物件を売却する際は、リフォームをするか、価格を低めに設定する必要があります。
建物の耐震性能に不安を感じる場合があるから
築30年のマンションの場合、建物が現在の耐震基準を満たしておらず、建物の耐震性能に不安を感じる人も多いです。
中古マンションの場合、建物の耐震性には新耐震基準と旧耐震基準があります。
旧耐震基準は、建築確認日が昭和56年5月31日以前に建てられたマンションに採用されている基準です。
震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準に設定されています。
一方で、新耐震基準は昭和56年6月1日以降に建てられたマンションに採用されている基準です。
新震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しない基準に設定されており、旧耐震基準よりも高い耐震性能になっています。
築30年を過ぎた中古マンションには旧耐震基準が採用されている物件も多く、住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合は、住宅金融支援機構が定めた耐震基準(新耐震基準に準ずる)を満たす必要があります。
築30年のマンションを購入する際には新耐震基準または耐震基準適合証明書を取得している物件を選びましょう。
外観や建物内部のデザインが古い印象を与えるから
築30年のマンションの場合、外観や建物内部のデザインが古い印象のする物件も多いです。
外観の色や質感が古臭さを感じる、エントランス部分にオートロックが無いなど、最近建築されたマンションとではデザインや設備面でどうしても劣ります。
しかし、定期的に大規模修繕を行っている物件であれば、外観のイメージが良く、エントランス部分にオートロックを採用しているなど、デザインや設備面で印象の良いマンションもあります。
また、築30年のマンションでも室内については、リフォームやリノベーションを行った上で売却している物件も多いです。
リフォームやリノベーション物件であれば新築と変わらないクオリティで住むことができます。
ただし、室内がきれいでも建物全体の管理が行き届いていないマンションは売れづらいです。
中古マンションは管理が命と言えますので、購入時には管理状態を必ずチェックしましょう。
固定資産税が控除される対象になる特例措置
固定資産税については、条件を満たすと控除対象になる特例措置が適用されます。
特例措置は、住宅用地や省エネ・バリアフリーなどの改修工事などが対象ですが、条件が細かく設定されているケースも多いので使用の際には注意が必要です。
ここでは固定資産税が控除される対象になる5つの特例措置について解説します。
住宅用地の特例措置
マンションや戸建てといった居住用の建物の敷地を住宅用地と言います。
居住用ということで住宅用地については、税負担を減らす必要があるということでその面積に応じて特例措置の対象です。
住宅用地の所有者であれば誰でも特例措置を受けることができます。
住宅用地が200㎡以下の場合は、課税標準額が価格の6分の1、200㎡を超える場合は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1です。
参考:固定資産税(総務省)
省エネ改修工事の特例措置
省エネ改修工事の特別控除は、住宅特定改修特別税額控除のひとつです。
既存住宅に対して特定の改修工事をした場合に所得税額の特別控除で、住宅ローン控除とは別に受けることができます。
マイホームについて一般省エネ改修工事を行った人が対象です。
省エネ改修に関する特例措置を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【適用条件】
・自己所有の家屋に対して省エネ改修工事を行い、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供していること。
・工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
・控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を自己の居住用に供していること。
・工事費用が50万円を超えること。
・工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること
省エネ改修の対象となる工事は以下のとおりです。
・窓の断熱改修工事(必須)
・床の断熱工事
・天井の断熱工事
・壁の断熱工事
・一定の太陽光発電装置設置工事
窓の断熱改修工事は必須となっているので注意しましょう。
省エネ改修工事の控除対象限度額は250万円ですが、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円です。
控除額の計算方法については、国税庁:No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)に詳しく記載されているので確認してください。
バリアフリー改修に関する特例措置
バリアフリー改修工事を実施した場合も固定資産税の特例処置を受けられます。
マイホームについてバリアフリー工事を行った人が対象です。
年齢等の条件があるので以下の点に注意しましょう。
バリアフリー改修工事を行う人が、次の(1)から(4)のいずれかに該当する特定個人である必要があります。
(1)50歳以上の人
(2)介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている人
(3)所得税法上の障害者である人
(4)高齢者等(65歳以上の方または上記(2)もしくは(3)に該当する方をいいます。)である親族と同居を常況としている人
バリアフリー改修に関する特例措置を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【適用条件】
・自己所有の家屋に対してバリアフリー改修工事を行い、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供していること。
・工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
・控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を自己の居住用に供していること。
・工事費用が50万円を超えること。
・工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること
バリアフリー改修の対象となる工事は以下のとおりです。
・バリアフリーのために通路または出入口の幅を拡張する工事
・バリアフリーのために階段の設置または勾配を緩和する工事
・バリアフリーのために浴槽の取替え、便器を座便式に取り換える工事等
・便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関等に手すりを取り付ける工事
・便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関等に床の段差を解消する工事
・出入り口の開戸を引戸、折戸等に取り替える工事等
・便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関等に床の材料を滑りにくいものに取り換える工事
バリアフリー改修工事の控除限度額は200万です。
控除額の計算方法については、国税庁:No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)に詳しく記載されているので確認してください。
バリアフリー改修工事は、介護保険や自治体からの補助金が利用できる場合も多いので合わせて活用しましょう。
耐震改修に関する特例措置
耐震改修工事を実施した場合も固定資産税の特例処置を受けられます。
マイホームについて耐震工事を行った人が対象です。
耐震改修に関する特例措置を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【適用条件】
・自己所有の家屋に対して耐震工事を行い、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供していること。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
・耐震改修をした家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
耐震工事の控除限度額は250万です。
耐震工事に関する特例措置を受けるためには、耐震改修した家屋が現行の耐震基準に適合するものであることを証明する必要があります。
証明書は、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人に申請を行い、「増改築等工事証明書」を発行してもらう、または地方公共団体の長に申請を行って「住宅耐震改修証明書」が発行してもらうことで取得できます。
控除額の計算方法については、国税庁:No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)に詳しく記載されているので確認してください。
長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
長期優良住宅化リフォームをした場合も固定資産税の特例措置を受けられます。
子育て世帯等(令和6年12月31日時点で、「19歳未満の扶養親族を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)で、令和6年1月1日~令和6年12月31日に居住を開始した人が対象です。
長期優良住宅化リフォームに関する特例措置を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【適用条件】
・自己所有の家屋に対して長期優良住宅化リフォームを行い、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供していること。
・工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
・控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
・工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上を自己の居住用に供していること。
・借入金の償還期間が10年以上あること。
長期優良住宅化リフォームの対象となる工事では以下を満たす必要があります。
・省エネ性
・耐震性
・バリアフリー性
・劣化対策
・災害配慮
・可変性
・維持管理・更新の容易性
・居住環境
・住戸面積
・維持保全計画
長期優良住宅化リフォームの補助率は工事費用の3分の1が限度で控除限度額は210万です。
特例措置を受けるためには長期優良住宅認定通知書を取得する必要があります。
所管の行政庁に対して、工事着工前に認定申請を行い、認定申請が通れば長期優良住宅認定通知書を発行してもらえます。
詳細については、認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省)でご確認ください。
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
最後に
今回は、固定資産税の基礎知識、税額を決定する要素や特例措置について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
固定資産税は、中古マンションなどの不動産を所有している人が支払う必要のある税金です。
最終的な金額は各市町村の長が決めますが、基礎的な計算方法を知っておくことで固定資産税額の正当性を確認できます。
また、固定資産税は、居住用の土地や耐震、バリアフリーなどの改修工事を行うことで特例措置を受けられる点も重要なポイントです。
中古マンションの固定資産税は築年数の経過によって下がっていきますが、築30年を超えるとメンテナンス費用や耐震性といった面で売却がしづらくなります。
中古マンションを購入する際には、将来の売却も見据え、建物全体の維持、管理の状態や耐震性などチェックしましょう。
この記事を読んで中古マンションの固定資産税の基礎知識を身につけていただき、物件の購入や売却の際に生かしていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。