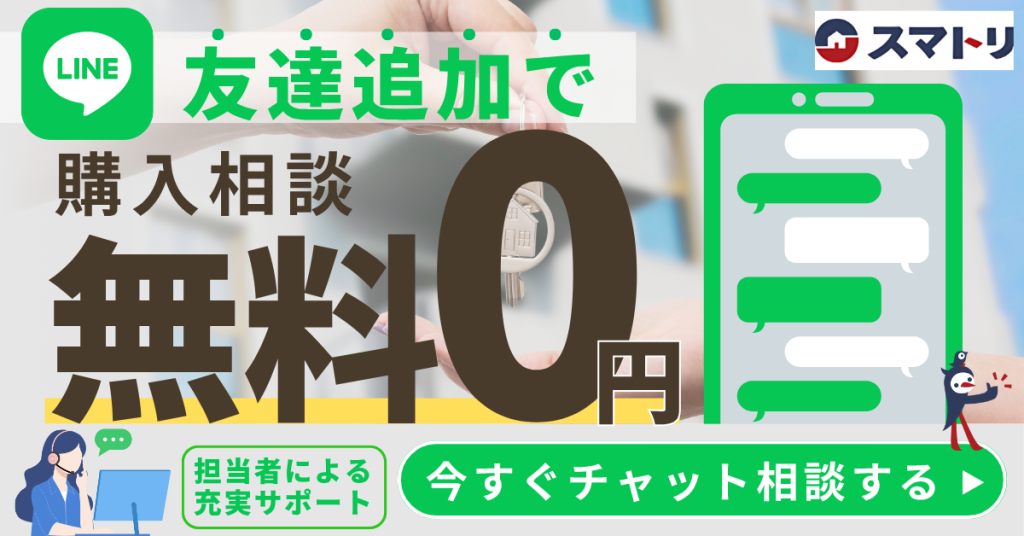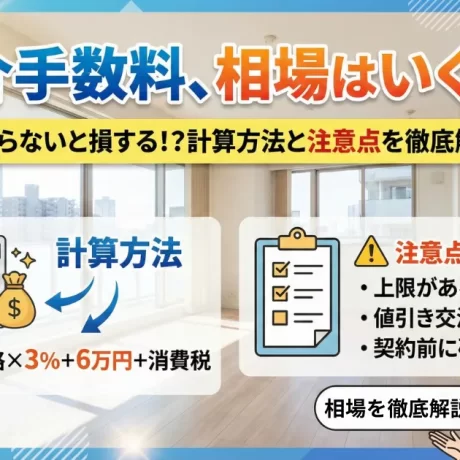家を買うタイミングはいつがベスト?年齢や年収など適切な購入時期を解説
「家を買うタイミングはいつがベストなのか?」
この疑問に明確な答えを出すのは簡単ではありません。
年齢や年収、家族構成、住宅ローンの返済計画、社会の動きなど、さまざまな要素が影響するからです。また、人生の節目ごとに住まいに求める条件も変わるため、正しいタイミングは人それぞれ異なります。
本記事では、家を買う時期を判断するために押さえておきたいポイントを、データや制度、実生活に即した視点からわかりやすく解説します。
この記事を通して、自分たちにとって無理のない、納得のいくマイホーム購入の時期を見つけるヒントになれば幸いです。
目次
家を買うベストタイミング
「そろそろマイホームを…」と考え始めたとき、誰もが気になるのが“いつ買うのがベストか”という問題です。住宅は高額な買い物だからこそ、勢いや感覚だけで決めてしまうのは危険です。
家を買うタイミングを判断するには、年齢や年収などのライフステージに関わる要素はもちろん、住宅ローンの借入条件や社会の動きといった外部要因も重要になります。
株式会社AlbaLink(本社:東京都江東区、代表取締役:河田 憲二)は、家の購入経験がある500人を対象に「家を買ったタイミングに関する意識調査」によると、第1位は「妊娠・出産」2位以下は「子どもの入園・入学」「結婚・婚約」という結果になりました。
実際に家を購入した人の意見を参考にして、ご自身のベストタイミングを選択することが大切です。
ここでは、家を買うベストなタイミングを見極めるための3つの視点「年齢」「年収」「社会状況」から、それぞれの傾向や考え方を解説していきます。
年齢
住宅の購入タイミングとして多いのは、30代です。国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査」によると、はじめてマイホームを購入した世帯主の平均年齢は、新築住宅で38.8歳、中古住宅で43.6歳となっています。
新築と中古それぞれの購入時の平均年齢をまとめた表は以下のとおりです。
【新築住宅】
・注文住宅:40.1歳
・分譲戸建住宅:36.6歳
・分譲マンション:39.9歳
※新築住宅全体の平均:38.8歳
【中古住宅】
・戸建住宅:43.6歳
・分譲マンション:43.7歳
※中古住宅全体の平均:43.6歳
とくに分譲戸建は36.6歳、注文住宅は40.1歳と、同じ新築でも購入時期にばらつきがあるのが特徴です。
このように、購入年齢は物件の種類によっても異なります。
中古住宅のほうが平均年齢が高めなのは、価格が比較的抑えられている分、ライフスタイルが落ち着いた世代が選びやすい傾向があるためです。
一方、新築は長期ローンを組むことを前提に、少しでも若いうちに購入したいと考える人が多いといえます。
30代は結婚や出産、子どもの進学など人生の大きな節目が重なるタイミングでもあり、家を買う判断をする人が多くなります。
ライフプランを見据えたうえで、住宅ローンの返済計画や働き方、家族構成とのバランスをどう取るかが重要なポイントになります。
年収
住宅を購入する世帯の年収は、選ぶ物件の種類によって大きく異なります。
国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査」によると、住宅を初めて購入した世帯の平均年収は新築で789万円、中古で659万円でした。
新築と中古それぞれの購入時の平均年収をまとめた表は以下のとおりです。
【新築住宅】
・注文住宅:808万円
└ 三大都市圏のみ:924万円
・分譲戸建住宅:721万円
・分譲マンション:840万円
※新築住宅全体の平均:789万円
【中古住宅】
・中古戸建住宅:650万円
・中古分譲マンション:668万円
※中古住宅全体の平均:659万円
特に高年収層が多いのは新築マンションで、平均年収は840万円に達しています。駅近や都市部の利便性を重視した住宅を選ぶ傾向が強く、共働き世帯や子育て世代に人気です。
また、注文住宅の購入者の平均年収は808万円と、新築分譲戸建(721万円)よりもやや高め。ただし、東京・大阪・名古屋の三大都市圏では924万円とさらに高くなっており、土地代の高さが影響していると考えられます。
中古住宅は、新築に比べて購入時の年収が低めの傾向があります。分譲マンションでは668万円、戸建では650万円が平均値です。中古物件は購入価格が比較的抑えられているため、幅広い年収層の世帯に選ばれていることがうかがえます。
年収によって購入できる物件の選択肢は変わりますが、大切なのは無理のない返済計画を立てること。住宅ローンの審査では「年収に対する借入額の割合(返済負担率)」も重要視されるため、年収だけで判断せず、資金計画全体を見据えた検討が必要です。
社会状況
家を買うタイミングは、世帯の年齢や年収だけでなく、社会全体の動きにも大きく影響されます。たとえば、昨今では物価上昇や住宅価格の高騰、建築資材の値上がりといった要因から、「早めに買っておいたほうが良いのでは」と考える人が増えています。
また、日銀による長期金利の引き上げの可能性など、住宅ローンの金利にも注目が集まっており、これまでの超低金利時代から徐々に変化が起きつつあります。金利が1%違うだけでも、30〜35年ローンでは数百万円単位で総返済額に差が出るため、金利動向は慎重に見極める必要があります。
さらに、テレワークの定着や働き方の多様化により、「都心に住む必要がない」として郊外や地方に目を向ける人も増加傾向にあります。住宅選びにおいても、利便性だけでなく住環境や広さを重視するケースが目立つようになりました。
このように、経済情勢や社会の価値観の変化によって、住宅購入の考え方も変わりつつあります。住宅市場を取り巻く流れを理解しながら、自分にとって無理のないタイミングを見極めることが、後悔しない家づくりにつながります。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
ライフステージの変化
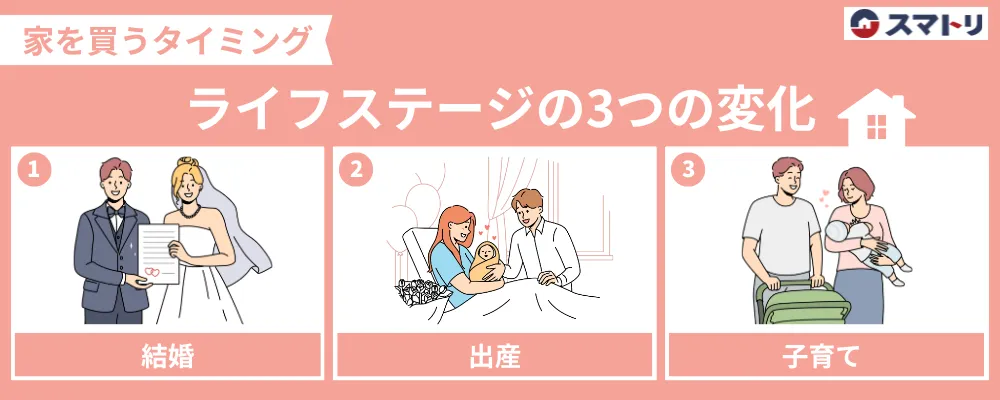
家を買うタイミングは人それぞれですが、ライフステージの変化がきっかけになるケースは多く見られます。特に結婚や出産、子育てといった人生の節目は、住まいに対する価値観や優先順位が大きく変わるタイミングです。
ここでは、それぞれの場面で「なぜ今、家を買おうと思うのか?」という背景やメリットを紹介します。
結婚
結婚を機に、賃貸ではなく「ふたりの新しい住まい」としてマイホーム購入を検討する人は少なくありません。
これまで別々に暮らしていた2人が一緒に生活を始めることで、住環境に対する希望や将来設計が明確になるからです。
新婚当初は夫婦共働きでローン返済に余裕があり、頭金も用意しやすいため、住宅購入を前向きに考えるにはよいタイミングともいえます。
出産
子どもが生まれるタイミングは、家に求める条件が大きく変わる時期です。
たとえば、階段のない間取り、保育園の近さ、車での移動を前提とした駐車場付きなど、生活動線や安全性を意識した家選びが必要になります。
また、家族が増えることで部屋数や収納スペースの必要性も高まり、今の住まいでは手狭だと感じることもあるでしょう。
出産前後は新生活への備えとして、マイホーム購入を本格的に検討する人が増える傾向にあります。
子育て
子どもが成長するにつれ、教育環境や住環境を重視した家選びが求められるようになります。
たとえば、通学しやすい学区や公園・病院の近さ、広めのリビングなどがその一例です。
子育てをきっかけに、より落ち着いた地域や自然が豊かな場所への引っ越しを考える家庭も少なくありません。
長期的な視点での家づくりが必要になるため、教育費や住宅ローンなど、家計全体を見渡して購入時期を検討することが大切です。
住宅ローン
家を買う際、多くの人が利用する住宅ローン。
物件価格や自己資金だけでなく、「いつ買うか」にも影響を与える大きな判断材料です。完済年齢や返済期間、金利タイプなどは、家計やライフプランと密接に関わってきます。
ここでは、タイミングを考えるうえで押さえておきたい3つの住宅ローンの基本ポイントを解説します。
完済時の年齢
住宅ローンを組むとき、重要になるのが「完済時の年齢」です。
多くの金融機関では完済年齢の上限が75〜80歳に設定されているため、35年ローンを利用する場合、45歳前後がひとつの目安となります。
できるだけ若いうちに購入した方が、定年までにローンを完済できる可能性が高く、将来の家計負担を軽減しやすくなります。
そのため、完済時期を逆算して購入時期を検討することが重要です。
返済期間
住宅ローンの返済期間は、最長で35年が一般的です。
期間が長ければ毎月の返済額は抑えられますが、そのぶん利息が増えるというデメリットも。
逆に、返済期間を短くすれば総支払額を減らせますが、月々の負担は重くなります。無理のない返済計画を立てるには、将来の収入見通しやライフイベント(教育資金・老後資金など)を踏まえたバランスの良い期間設定がポイントです。
金利タイプ
住宅ローンの金利タイプには「固定金利」「変動金利」「固定期間選択型」があります。
固定金利は返済額が一定で将来の家計設計が立てやすい一方、金利はやや高めです。
変動金利は低金利の恩恵を受けやすい反面、将来的な金利上昇リスクがあります。
どのタイプを選ぶかによって、支払い総額や安心感が大きく変わるため、金利の動向やリスク許容度に応じた選択が必要です。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
家を買ってはいけないタイミング
マイホーム購入は人生でも大きな決断のひとつですが、どんな状況でも「買えば正解」とは限りません。
むしろ、タイミングを誤ると後悔や家計の圧迫につながるケースもあるでしょう。
ここでは、家を買うのをいったん待つべきタイミングについて解説します。購入の勢いに流されず、立ち止まって考える材料としてご活用ください。
ローン返済の見通しが立たないとき
毎月のローン返済に無理がある状態では、購入を急ぐべきではありません。
収入が不安定だったり、将来の支出計画が不透明なまま住宅ローンを組むと、返済が家計を圧迫する恐れがあります。
特に、ボーナス頼みの返済プランや貯金を全て頭金に回すような状況は注意が必要です。
「借りられる額」ではなく、「無理なく返せる額」で計画を立てられる時期が、購入の目安となります。
転勤や転職の可能性が高いとき
今後、勤務地の変更や転職の予定がある場合は、マイホーム購入を慎重に検討すべきです。
勤務先が変われば通勤圏内での住み替えが必要になり、せっかく買った家に住み続けられなくなる可能性もあります。
また、転職によって収入が変わると、住宅ローンの審査や返済計画にも影響が出ることがあります。ライフスタイルが安定するまでのあいだは、賃貸で柔軟に対応できるほうが安心です。
住宅購入以外の出費が多いとき
子どもの進学、車の買い替え、結婚式、介護など、大きな出費が重なっているタイミングでの住宅購入は避けたほうが無難です。
住宅ローン以外にも登記費用や引っ越し代、家具・家電など、購入時にはさまざまな初期費用が発生します。
手元資金に余裕がないまま無理に購入を進めてしまうと、思わぬ資金不足に陥る可能性も。家計の見通しが立つまで、購入は待つ判断も必要です。
家を買うタイミングで利用できる制度
住宅購入は大きな支出を伴いますが、タイミング次第で国や自治体の支援を受けられることもあります。
とくに税制優遇や補助金制度は、利用できるかどうかで家計への影響が大きく変わる場合もあるでしょう。
ここでは、家を買うときにぜひ知っておきたい2つの代表的な支援制度をご紹介します。
住宅ローン控除の減税制度
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、一定の要件を満たした住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、所得税や住民税が控除される制度です。
年末時点のローン残高の0.7%が13年間にわたり控除される仕組みとなっており、最大で数百万円単位の減税効果があります。
住宅の種類や省エネ性能、取得時期によって適用条件や控除額が異なるため、事前の確認が重要です。
購入タイミングによって制度の内容が変わる場合もあるため、最新情報のチェックは欠かせません。
住宅ローン減税の詳細については、国税庁のHP:住宅ローン減税をご確認ください。
各自治体の補助金制度
各自治体では、子育て世帯や若年層、移住者向けに住宅購入を支援する補助金や助成金制度を設けている場合があります。
たとえば、一定の地域に住宅を建てることで数十万円の補助が受けられる制度や、リフォーム・省エネ設備の導入に対する助成が用意されているケースもあるでしょう。
対象者の条件や申請時期、予算の上限などは自治体によって異なるため、購入予定の地域の行政窓口や公式サイトで確認しておく必要があります。
タイミングによっては、支援を受けられないこともあるので注意が必要です。
東京都が行う住宅購入の助成金制度は以下のとおりです。他にも、ご自身がお住まいの地域に合わせた助成金制度を調べてみることをおすすめします。
知ってお得な助成制度とは?:東京都
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
まとめ
家を買うタイミングに「正解」はありませんが、年齢・年収・ライフステージ・住宅ローン・社会情勢など、複数の視点から冷静に判断することが大切です。
特に結婚や出産、子育てといったライフイベントの前後は、住まいへのニーズが大きく変化するタイミングでもあります。
また、住宅ローンの完済年齢や返済計画、金利の選び方によって、家計への影響も大きく左右されます。勢いだけで購入を進めるのではなく、将来の見通しや他の支出とのバランスも見据えたうえで判断しましょう。
一方で、住宅購入には住宅ローン控除や自治体の補助金といった公的な支援制度を活用できる場合があります。これらの制度を上手に使えば、経済的な負担を軽減しながら賢くマイホームを手に入れることも可能です。
「いつ買うか」を考えることは、「どう暮らしたいか」を考えることでもあります。焦らず、自分たちにとって最適なタイミングを見極めて、後悔のない住まい選びを目指しましょう。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。