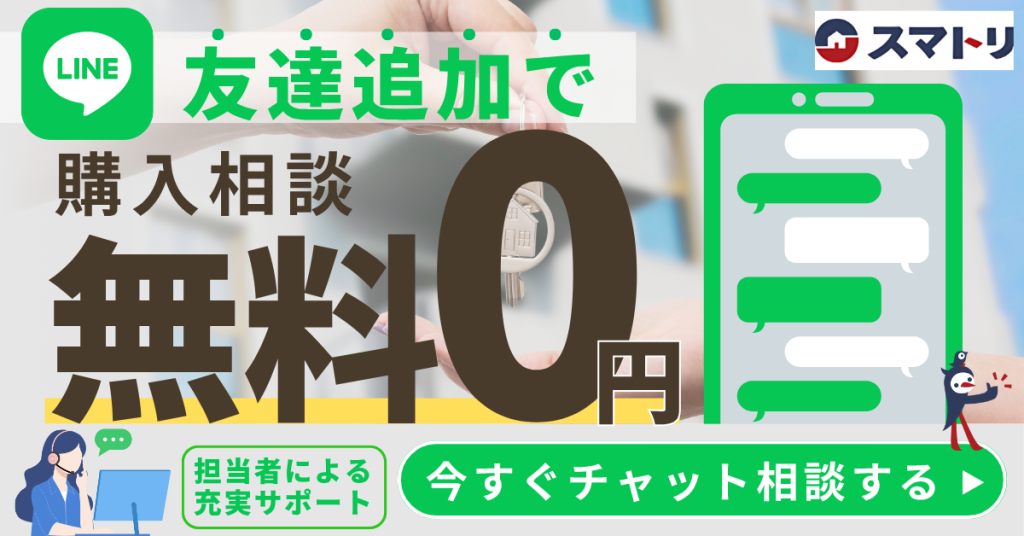理想のマンションの買い替え時期はいつ?手順や税金を徹底解説
本記事にはプロモーションが含まれています。
「マンションの買い替えを検討しているが良いタイミングがわからない」「マンション買い替えの資金計画や税金について知りたい」など、マンションの買い替えの際の手順や資金計画などについて知りたいという方も多いでしょう。
「売却を先にすればよいのか」「新居を決めてから売却を進めたほうかよいのか」など、マンションを買い替える手順に悩む方もおられるかと思います。
マンションの買い替えを成功させるためには、手順や資金計画、税金について理解を深めることが重要です。
マンションの買い替えの手順は、売り先行、買い先行によって大きく異なるので、それぞれのメリット・デメリットを理解して買い替えを進める必要があります。
売却時の築年数を確認する、周辺地域の売却相場を調べておくといったこともマンションの買い替えを成功される上で大切なポイントです。
国土交通省住宅局の令和4年度住宅市場動向調査報告書によると、新築の集合住宅(マンション)の一次取得者は30歳代が45.2%に対して、二次取得者(マンションを買い替える世帯)は50歳以上が72.3%と非常に多くなっています。
これからマンションの買い替えを検討されている人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
目次
マンションの買い替えを行う3つのタイミング
【マンションを買い替える主な3つのタイミング】
・ライフステージ
・年齢
・築年数
今の住まいに不満があるわけではないけれど、「このまま住み続けていいのか」と悩む方も多いですよね。
マンションの買い替えは、生活の変化や将来の見通しによってベストなタイミングが異なります。
売却や購入にかかるコストや市場動向も踏まえる必要があるため、判断は簡単ではありません。
ここでは、ライフステージや年齢・築年数といった視点から、買い替えを検討すべきタイミングをわかりやすく解説します。
ライフステージ
結婚、出産、子どもの進学、独立、そして定年後の生活と人生は続いていきます。
ライフステージが変われば、理想の住まいのかたちも変化するものです。
たとえば、子育て期には広さや学校区、利便性が重視され、老後は段差の少ないバリアフリー住宅や静かな環境が求められることが増えます。
今のマンションが、これからの暮らしに合っているかを見直すことが、買い替えを考える大きなきっかけになります。
変化に応じた住まい選びが、快適な暮らしに直結するでしょう。
マンションの買い替えをするタイミングは人それぞれですが、ライフステージの変化する時期に行うことが多いです。
ライフステージの変化する時期には、以下のようなタイミングが挙げられます。
・結婚や出産、進学といった家族構成の変化する時期
・仕事の転勤や転職の時期
・親の介護を行う時期
特に、家族構成の変化する時期は、住んでいるマンションが手狭になる、子供の学校区を考えての引っ越しなどマンションの住み替えのきっかけとなるできごとが多いです。
ほかにも、建物自体が古くなる時期、マンションの大規模修繕が終わった時期、高齢のために暮らしやすい施設への移動を考える時期などもマンションの買い替えを検討する時期と言えます。
年齢
マンションの買い替えには、住宅ローンの借入れや返済計画が大きく関わってきます。
20代〜50代であれば、まだローン審査に通りやすく、買い替え後も十分に返済期間を確保できますが、60代以降になると借入が難しくなり、現金や自己資金での対応が求められることもあるでしょう。
年齢が上がるほど、住み替えの選択肢が限られてくるため、資金面の余裕があるうちに検討するのが理想です。
「動けるうちに動く」ことが後悔のない判断につながります。
築年数
築年数が経過するほど、マンションの資産価値は徐々に下がっていきます。
一般的に築20年を超えると売却価格が大きく落ち込む傾向があり、リフォームや修繕の負担も増えていくでしょう。
そのため、築15〜20年をひとつの目安として「売るなら今かもしれない」と考えるのも一つの判断基準です。
また、古くなった設備や断熱性能に不満が出てくる時期でもあるため、生活の快適さと資産価値の両面から、築年数に応じた見直しを行いましょう。
売却と購入の手順
マンションの買い替えの手順は、売却と購入のタイミングで決まります。
売り出しを先に進めてから購入物件を探す場合を売り先行、購入物件を決めてから売却を進める場合が買い先行です。
どちらもメリット、デメリットがあるので、自身の状況に応じて売り先行、買い先行を選びましょう。
売り先行の流れ
マンションの買い替えを行う場合は、一般的には売り先行を選ぶ人が多いです。
売り先行では、マンションに居住しながら売却を行い、売買契約が決まった段階で新居探しを始めるので、2重ローンが発生することがなく、安く売り急ぐ心配がありません。
また、住宅ローンなどの資金計画が立てやすい点もメリットと言えます。
一方で、万が一新居が決まるまでにマンションが売れた場合には引渡し時期によっては仮住まいをする必要があるので、余分な費用が発生する可能性がある点や居住中なので内覧のたびに掃除や片づけなどの手間がかかるといった点がデメリットです。
売り先行の場合は、売買契約時に新居探しの期間として引渡しまで3か月程度の猶予をもらえることが多いので、引渡しについては不動産会社と相談すると良いでしょう。
買い先行の流れ
買い先行は、新居の購入を決めてから居住中のマンションの売出しを開始する方法です。
メリットは、新居に引越しが済めば空室で販売できる点です。
居住中だと内覧者は住んでいる人の部屋の状態や臭いといった生活感が気になるので購入にいたらないことが多いですが、空室であれば生活感もなく、ハウスクリーニングをすれば印象も大きく変えられるので売却がしやすくなります。
不動産会社に鍵を預けておけば、内覧の調整も必要ありません。
また、引っ越しが先になるので仮住まいをしなくてもよい点やあわてて物件を探す必要がないので購入に時間をかけて気に入った物件を購入することができる点もメリットと言えます。
買い先行のデメリットは、新居と現在のマンションの2重ローンが発生する可能性があるので、資金的に余裕がないと取り組みが難しい点です。
売却が長期化するとローンや管理費、修繕積立期などの負担が大きくなり、価格を下げて早めに処分する必要があるなど希望の価格で売れないケースもあります。
そのため、売却金額が確定しないので資金計画が立てにくいといった点もデメリットと言えます。
物件価格以外に税金と諸費用がかかる
マンションの買い替え時には、物件価格以外に税金と諸費用がかかります。
予算を検討する際には、税金や諸経費も含めて検討する必要があります。
マンションの売却時と購入時でそれぞれにかかる税金や諸費用が異なる点にも注意しましょう。
売却時にかかる税金
マンションの売却時にかかる税金は、印紙税、譲渡所得税があります。
印紙税は、売買契約書などの課税文書にかかる税金です。
課税文書には、領収書や契約書、借用書や手形、株券、債券などが含まれます。
売買契約書にかかる印紙税は売買金額によって税額が異なり、令和9年3月31日までの間に作成する売買契約書については軽減税率が適用されています。
売買契約書にかかる印紙税の税額については以下のとおりです。
【売買契約書にかかる印紙税】
| 金額 | 税率 | 軽減税率 |
| 1万円以下のもの | 非課税 | 非課税 |
| 1万円を超え10万円以下のもの | 200円 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの 2,000円 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
次に、売却時に利益が出る場合は、譲渡所得税(所得税+住民税)を支払う必要があります。
売却時に損失がでる場合は、譲渡所得税を払う必要はありません。
譲渡所得税は、譲渡所得に所得税率を乗じて計算しますが、所得税率は、マンションの所有期間によって税率が異なります。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得といって税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)、所有期間が5年以上場合は長期譲渡所得といって税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。
長期譲渡の場合の5年以上というのは、1月1日を5回以上越える必要がありますので間違えないように注意しましょう。
譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却価格 -(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税=譲渡所×所得税率
取得費は主に売却した不動産の購入費ですが、購入時に不動産会社へ支払った仲介手数料や印紙税などの税金、司法書士に支払った登記費用、リフォーム費用など購入時にかかった費用を含むことができます。
マンションの購入費のうち建物については、取得した年月日によって減価償却費を計算する必要があります。
譲渡費用は、売却時に不動産会社に支払った仲介手数料、売買契約書の印紙代や売却時にかかった費用です。
参考:譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(国税庁)
参考:建物の取得費の計算(国税庁)
購入時にかかる税金
マンションの購入時にかかる税金には、印紙税、登録免許税、不動産取得税があります。
売却時と同様に購入時にも売買契約書には印紙税が必要です。
詳細については売却時の説明をご参照ください。
登録免許税は、マンションなど購入して土地や建物の所有権や抵当権の登記をする際に必要な税金です。
土地の所有権の移転、建物の登記など種類によって税率は異なります。
土地の所有権の移転登記にかかる税率は以下のとおりです。
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
| 売買 | 不動産の価額 | 2.0% | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1.5% |
| 相続、法人の合併また共有物の分割 | 不動産の価額 | 0.4% | |
| その他(贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 2.0% |
建物の登記にかかる税率は以下のとおりです。
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率,br>(措法72の2~措法75) |
| 所有権の保存 | 不動産の価額 | 0.4% | 個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については軽減税率が適用されます。 |
| 売買または競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 2.0% | 同上 |
| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 4.0% | |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 2.0% |
不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です。
また、個人が建物の登記において住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については軽減税率が適用されます。
国税庁の「No.7191 登録免許税の税額表の住宅用家屋の軽減税率」をご参照ください。
不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に課税される税金です。
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税されますが、相続による取得など一部の取得については課税されません。
不動産取得税の計算方法は以下のとおりです。
不動産取得税=不動産の価額×標準税率(4%)
不動産の価格は、登録免許税と同様に原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です。
不動産取得税の税率は、土地、建物はいずれも4%となっています。
令和9年 3月31日までは、居住用の住宅を建てるための宅地は価格は2分の1、住居用の土地や建物の場合は3%の軽減税率が適用できます。
上記以外にも翌年には固定資産税がかかります。
購入した年の固定資産税については、1月1日を起算日として購入日の前日までを売主、購入日以降を買主が負担するのが一般的です。
関西だと4月1日を起算日とするケースもあるので契約時に確認しましょう。
買い替え時に必要な諸費用
マンションの買い替え時に必要な諸経費には、仲介手数料や登記費用などがあります。
売却時と購入時で諸経費は異なります。
マンションの売却時にかかる諸費用は以下のとおりです。
売却時に必要な諸費用
・売却の際に利用した不動産会社に支払う仲介手数料
・登記費用
購入時にかかる諸経費は以下のとおりです。
購入時に必要な諸経費
・購入の際に利用した不動産会社に支払う仲介手数料
・登記費用
売却する家を購入した際の諸経費と売却時にかかった諸経費については、取得費に含むことで譲渡所得を減らすことができます。
また、売却時の登記費用は数万円で済みますが、購入時には登録免許税が数十万円かかる点には注意が必要です。
居住用財産の買い替え時に適用できる減税措置
近年は購入時よりもマンション価格が上昇しており、売却すると譲渡所得税が発生するケースが多いです。
居住用マンションの買い替え時には適用できる減税措置がいくつかあります。
特別控除や軽減税率を活用して上手に節税しましょう。
譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、居住用として利用していたマンションなどの財産を譲渡(売却)した場合に譲渡所得額から最高3,000万円を控除できる制度です。
住まなくなってから一定期間が経ったマンションでもこの制度を利用できます。
この制度が利用できる条件は以下のとおりです。
・自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地や借地権の売却であること。
・居住用家屋等を売却した年の前年または前々年にこの特例を利用していないこと。
・個人の配偶者および直系血族など特別の関係にある者に対する譲渡ではないこと。
・居住用財産を譲渡した前年、前々年にすでに適用を受けていないこと、併用できない他の特例をつかっていないこと。
・居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
建物を取り壊して売却する場合など、詳細については国税庁の「No.3302 マイホームを売ったときの特例」をご参照ください。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と併用できる特例には10年超所有軽減税率の特例があります。
10年超所有軽減税率の特例については後ほど詳しく解説します。
また、住宅ローンとは併用できない点には注意が必要です。
買い替える不動産で住宅ローンを使いたい場合はどちらか得かを考えて利用するようにしましょう。
特定の居住用財産の買い替えの特例
特定の居住用財産の買い替えの特例とは、居住用のマンションなどの財産を令和5年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件を満たすと譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。
例えば、2,000万円で購入したマンションを3,000万円で売却し、5,000万円のマンションに買い換えた場合、本来は1,000万円の譲渡益が課税対象ですが、買い換えたマンションを売却するまで譲渡益への課税が繰延べされます。
特定の居住用財産の買い替えの特例が利用できる主な条件は以下のとおりです。
・自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地や借地権の売却であること。
・居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
・マンションを売却した年、その前年および前々年に3,000万円の特別控除の特例または居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例もしくは居住用材サインを買い換えた場合の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。
・売却価格が1億円以下であること。
詳細については国税庁の「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」をご参照ください。
特定の居住用財産の買い替えの特例は、併用できない特例が多いので利用する際には注意が必要です。
また、売却価格が1億円以下であることが条件になるため、首都圏のタワーマンションなどでは活用が難しいでしょう。
参考:特定のマイホームを買い換えたときの特例(国税庁)
特定のマイホームを買い換えたときの特例(国税庁)
売却した場合の軽減税率の特例
居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例では、居住用マンションなどの財産を売った場合、一定の要件を満たすと長期譲渡所得の税額を低い税率で計算する軽減税率の特例が利用できます。
長期譲渡の場合の税額は、通常は税率20.315%です。
軽減税率が適用されると課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、課税長期譲渡所得金額×10%、6,000万円を超える部分については(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円です。
居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例が利用できる主な条件は以下のとおりです。
・自己が居住している家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売却すること。
・売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること
・マンションを売却した年、その前年および前々年に3,000万円の特別控除の特例または居住用財産を売却したバイの軽減税率の特例もしくは居住用材サインを買い換えた場合の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
・売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
・個人の配偶者および直系血族など特別の関係にある者に対する譲渡ではないこと。
詳細については国税庁の「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」をご参照ください。
居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例を利用するにあたっては、居住用のマンションを取得してから所有期間が10年を越えているかがポイントです。
他の特例や軽減措置との併用が難しいので利用する際には注意しましょう。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
居住用のマンションを買い替えで売却する場合、一定の要件を満たしていれば譲渡損失が出ると損益通算及び繰越控除の特例が利用できます。
損益通算では、給与所得や事業所得などの他の所得からの控除が可能です。
譲渡損失が控除しきれなかった場合は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除できます。
居住用財産を買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が利用できる条件は以下のとおりです。
・自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地や借地権の売却であること。
・居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
・譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える財産で日本国内にあるものの譲渡であること。
・譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある財産で家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
・買い替えの財産を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供することまたは供する見込みであり、取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
詳細については国税庁の「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」をご参照ください。
買い替えの特例なので、新居を取得または取得予定があれば利用できますが賃貸に引っ越す場合などには使えません。
他の特例に比べると部屋の広さなど細かい条件があるので利用する場合は注意しましょう。
また、繰り越しについては、その年の12月31日の住宅ローンの償還期間が10年以上ある、その年の合計所得が3,000万円以上ある、旧居の敷地面積が500㎡を超える場合は超えた部分については繰越控除不可です。
参考:マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)(国税庁)
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
買い替えを成功させる4つのポイント
買い先行したら旧宅がなかなか売れなかったなど、マンションの買い替えで失敗したという話をよく耳にします。
では、実際にマンションの買い替えを成功させるためにはどういった点に気を付ければいいのでしょうか。
ここでは、マンションの買い替えを成功させるための4つのポイントについて解説します。
売却時の築年数を確認する
マンションの成約率は築年数によって大きく変わるので、マンションの売却時の築年数を確認することは非常に重要です。
マンションの場合は、立地によっては購入時よりも高くなるケースもありますが、一般的には築年数が経つごとに物件の価格は下落します。
国土交通省の「中古住宅流通、リフォーム市場の現状(ヘドニック法)」によるとマンションの価格は築5年で約84%、築10年で約75%、築20年で約58%となっています。
マンションの買い替えを検討する場合は、少しでも早く売却するほうが売却はしやすくなります。
売却相場を調べておく
周辺地域の売却相場を調べていなかったばかりに、不動産会社に言われとおりに売出しをして相場よりも安い価格で売ってしまったという話をよく耳にします。
そのため、マンションの売却で損をしないためにも周辺地域の売却相場を調べておくことは重要です。
周辺地域の売却相場を調べておくと、自分のマンションが最低でもどのくらいであれば売ってもよいかという基準を作ることができるので不動産会社との交渉もしやすくなります。
資金の余裕を持って計画を立てる
マンションの買い替えは、時間と資金の余裕を持って計画を立てたほうがトラブルなく進むケースが多いです。
たとえば、売り先行の場合は資金計画については余裕を持てますが、売買契約後の住み替えのタイミングを誤ると仮住まいに移動しないといけません。
そのため、売買契約が決まりそうなタイミングで次に引っ越したい物件の目星をつけておくと引渡しと引っ越しのタイミングを合わせることができるのでロスなく売却できます。
買い先行の場合は、購入はすでに決まっているので仮住まいをする必要もなく時間的な余裕はあります。
しかし、資金面では一時的にダブルローンになる可能性もあるので手元資金に余裕を持っておくほうが良いでしょう。
複数の不動産会社を要検討する
マンションの買い替えを成功させるためには依頼する不動産会社選びは大切なポイントです。
例えば、売り先行で進める場合は少しでも高く売れると買い替え先の選択しも広がります。
マンションの買い替えを成功させるには、売却実績や営業力のある不動産会社を選ぶ必要がります、
信頼できる不動産会社を見つけるには、一社だけではなく、複数社に査定を依頼することが重要です。
複数の不動産会社に会うことで、提案力や営業力などを比較し、その中から自分の考えに合った不動産会社を選びましょう。
また、不動産会社は一度決めるとなかなか変えることができないという人も多いと思います。
なかなか売却が進まない場合は不動産会社を変えるのもひとつの方法です。
実際に不動産会社を変えただけですぐに売却が決まったというケースも多々あります。
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
買い替え時の資金計画を立てる上で利用できる制度
マンションの買い替え時に重要になるのが資金計画を事前に立てておくことです。
ご自身が購入したいと思えるマンションがあっても、資金の目途が立たないと購入できません。
つなぎ融資や住み替えローンをなどマンションの買い替え時に資金計画を立てる上で利用できる制度を上手に活用しましょう。
一時的に費用を借り入れる「つなぎ融資」
つなぎ融資は、マンションの買い替え時に買い先行や売り先行でも引渡し前に引っ越し先が決まった場合、一時的に新居の支払い代金などの費用を借り入れできる制度です。
不動産会社に依頼すればつなぎ融資してくれる金融機関を紹介してもらえます。
引渡しまではダブルローンにはなりますが、売却するマンションの売買代金で返済できるので短期間の借入で済みます。
ただし、
短期間のローンになるので金利が高くなる点、売却するマンションの売却価格が新居よりも高い場合はつなぎ融資を使っても手出しが必要になる点には注意が必要です。
新居のローンに上乗せする住み替えローン
住み替えローンは、売却するマンションを売却しても住宅ローンが残る場合、ローンの残債を新しい家の住宅ローンに上乗せして1つの住宅ローンとして融資を組んでもらえる制度です。
自己資金が足りなくても家を購入できる、二重ローンを組まなくてよいといったメリットがあります。
通常よりも多くの住宅ローンを借り入れることになるので、自身の与信が低いと組めない、返済金額が増える、通常の住宅ローンよりも金利が高いといった点には注意が必要です。
また、住み替えローンを組むためには、売却するマンションと新居の購入を同日で行う必要があり、タイミングを合わせるのが難しく、売却するマンションが売れないと新居が購入できないといったケースもあります。
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
最後に
今回は、マンションの買い替え時の手順、かかる税金や費用、適用できる減税措置などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
マンションの買い替えでは、買い先行や売り先行といった手順や実際にかかる税金、費用などの資金計画を把握しておくことが重要です。
特に買い先行で進める場合には先に新居を購入することになるので、資金計画は重要です。
自己資金が少ない場合には、売り先行で進めるか、つなぎ融資や住み替えローンを活用しましょう。
マンションを売却して利益が出る場合は、居住用のマンションについては3,000万円控除や買い替え特例、軽減措置が使うことで減税が可能です。
減税措置を上手に活用すれば手元資金を多く残すことができます、
この記事を参考に、マンションの買い替えの手順や資金計画を理解し、成功するためのポイントを確認しながら実践してみてください。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。