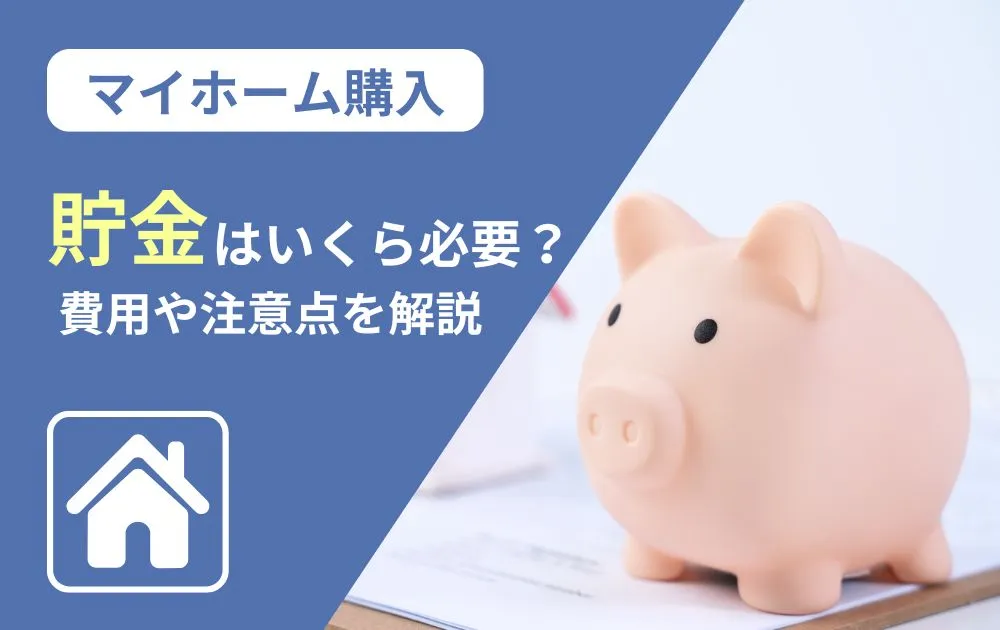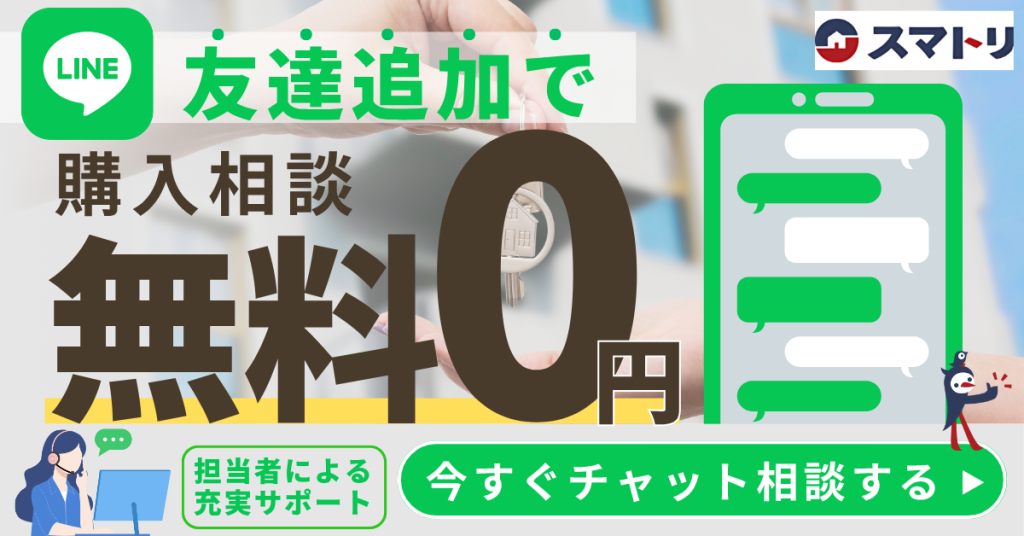家を買うために年収はいくら必要?予算の立て方や計算方法を解説
「家を買いたいけれど、自分の年収で買えるのはどんな家だろう?」
「ローン返済で家計が苦しくならないか心配」
これから家の購入を考えている場合、こういった不安や疑問をかかえている方も多いでしょう。
住宅ローン返済は長期に及ぶので、年収とのバランスを考え無理のない資金計画を立てることが必要となってきます。家族構成やライフスタイルの変化によって、将来的に必要なお金も変わってくるので、その変化を踏まえ予定外の出費があっても、対応していけるように計画を立てることが重要と言えるでしょう。
株式会社リクルートが実施した2023年首都圏新築マンション契約者動向調査によると、世帯総年収は全体平均で1057万円で、2008年以降で最も高い結果になりました。
不動産価格が上昇傾向にある近年、年収がどれくらいあれば家が購入できるのか気になる方も多いかと思います。
この記事では、年収に応じてどんな家が買えるのか、購入金額の目安や年収をもとに考える住宅ローン返済額の計算方法について解説していきます。今後家の購入を考えている方は、是非ご自身の年収や今後の年収見込みについて考えながら最後までお読みください。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
目次
家の購入額は年収の5~6倍
家の購入額は年収の5~6倍が目安といわれています。購入額と年収の比率をあらわす「年収倍率」も、予算を考える際に参考にされる指標の一つです。
過去3年分(2020年~2022年)の全国における年収倍率をみてみましょう。
| 世帯年収 | 建設費 | 年収倍率 | |
| 2022 | 623.7万円 | 3715.2万円 | 約5.96倍 |
| 2021 | 602.2万円 | 3569.7万円 | 約5.92倍 |
| 2020 | 594.2万円 | 3533.6万円 | 約5.95倍 |
上記によると、家の購入額は年収の6倍程度になっていることがわかります。
また、2021年4月~2022年3月の国土交通省「令和4年度住宅市場動向調査」 (mlit.go.jp)によると、注文住宅を購入した世帯年収は全国平均で801万円、三大都市圏では896万円でした。
割合としては年収600万~800万の世帯が25.7%で最も多くを占めていました。年収400万~600万22.0%とあわせると約半数に及びます。
家を購入しているのは、年収400万円~800万円の世帯が多いことがわかります。
家を買うには頭金やローンを考えて計算する必要がある
家を買うためには、頭金をどの程度準備しておくとよいか、住宅ローンの返済はどの程度なら苦しくなく返済していけるのか、を考えて計算しておく必要があります。
マイホーム購入となると、つい理想やこだわりが強くなって予算もオーバーしてしまいがちです。無理なく返済できる額を考えて、住宅ローンを組む必要があります。頭金も準備し、返済の負担を少しでも軽くしておくようにしましょう。
今後の年収やライフスタイルの変化を考えて家の購入を検討する
家族の人数やライフスタイルの変化によって、お金の使い方や必要な貯蓄額が異なってきます。
今後どのようにライフスタイルが変化していくか、ある程度考えて家の購入を検討する必要があります。
住宅ローン完済までは数十年間あるケースが多いでしょう。その期間、何度か大きな出費が発生する可能性が考えられるので、その出費に備えられるようローンを組んでおくことが必要です。
例えばお子さんがいる場合、教育資金を考慮しておかなければなりません。子育て費用の家計負担は子どもの年齢とともに増加していき、大学在学時は一番負担が大きくなります。大学進学に向けての資金も考慮しておかなければなりません。
また、車や家電製品の買い替え、維持費なども大きな出費です。ローン完済の年までに起こりそうなライフイベントと必要な費用を書き出し、確認しておくことをおすすめします。
加えてケガや病気、転職など予期せぬトラブルで収入が減るリスクもあります。家計が苦しくならないよう、不測の事態に備えて半年分程度の生活費資金を確保しておくと安心です。
参考:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果を公表します」
家の購入予算は「自己資金」+「住宅ローン」で考える
家の購入予算は、住宅ローンのみに頼るのではなく「自己資金」と「住宅ローン」セットで考える必要があります。
自己資金は住宅購入価格の2割と、諸費用(不動産会社の仲介手数料や土地や建物の登記費用、住宅ローンの手数料など)を合わせて3割を目安に用意しておきましょう。
自己資金のうち、頭金次第で住宅ローンの優遇条件を受けることができる場合もあります。そのため、住宅ローンだけでなく、自己資金も予算に入れておくことが重要といえるでしょう。
この項では「自己資金」とは具体的にどういったものなのか、自己資金を用意するメリットとともに解説していきます。
また住宅ローンを組むにあたって実際にいくら借りればいいのか、年収をもとにしたローン返済額の計算方法もご紹介していきます。
自己資金とは何か
自己資金とは、住宅購入の際に、住宅ローンで準備する資金とは別に用意しておく現金のことです。
一般的に、住宅を購入する場合、住宅購入代金をすべてローンで払うのではなく、一部を現金で支払うケースが多いといえます。この現金支払いが頭金であり、諸費用と合わせたお金を「自己資金」と呼びます。「自己資金」は「頭金」+「諸費用」で算出することが可能です。
頭金は住宅ローンの借り入れ前に現金で支払いますが、住宅価格の一部として支払うため住宅ローンの借入金を減らせる、といったメリットにつながります。
頭金を支払うことにより「毎月の返済額が抑えられること」と「想定していた返済額を変えずに借入期間を短くできる」といった効果が得られます。
自己資金のうち、頭金を必要とせずに住宅価格の全額を借入できる金融機関もありますが、あまりおすすめはできません。
頭金を用意するメリット大きいため、全てを借り入れるのではなく頭金を用意しておいたほうがよいでしょう。
頭金を用意するメリットとして、ほかに以下の2点があげられます。
・頭金の準備により月々の返済負担が減り、支払能力が高まると判断され住宅ローン審査に通りやすくなる
・金融機関によっては適用金利が下がる可能性がある
スムーズに返済していくために、住宅ローンを組む際はある程度の頭金を用意しておくことをおすすめします。
住宅ローンは返済できる額で設定する
住宅ローンは借入可能額ではなく、返済できる額の設定をすることが必要です。
無理のない返済計画を立てるために、まずは毎月の住宅ローン返済額と年収の関係を確認しておきましょう。
年収に占める年間ローン返済額の割合のことを「返済負担率」といいます。返済負担率が小さいほうが余裕を持って返済することが可能です。理想的な返済負担率は20~25%以下といわれています。
返済負担率は、金融機関が住宅ローン審査を行う際の指標としても使われます。返済負担率は金融機関よって異なりますが「30%~40%以下」であることが推奨されています。
しかし将来的に子供の教育費などで家計が圧迫されると、毎月の返済が苦しくなる可能性もあるので、返済負担率は25%以下にすることが望ましいでしょう。
注文住宅:21.9%
土地付注文住宅:25.6%
建売住宅:23.9%
マンション:22.1%
中古戸建:20.4%
中古マンション:19.7%
住宅の種類によって差はありますが、返済負担率は20%~25%程度であることがわかります。
参考:「住宅ローンの返済比率の目安は?上限割合や計算方法、注意点」
住宅金融支援機構の2022年度の調査データ(2022年度 フラット35利用者調査)では、住宅の種類と返済負担率の平均は以下のようになっています。
お家の購入でこんなお悩みありませんか?
◆ お金に関すること全般が不安
◆ 不動産業者がなんだか怖い
\LINEで担当者にチャット相談/
無料の購入相談を始める
年収をもとに考える住宅ローン返済額の計算方法
年収をもとにして住宅ローン返済額の参考となる計算方法をご紹介します。
返済負担率(%)=年間返済額÷年収×100
たとえば、年収400万円で、月々の返済額が7万円、年間返済額が84万円の場合、【21=84÷400万×100】となり、返済負担率は21%です。
借入可能額を計算する場合、先に返済負担率を決めてから式に入れることでその目安を把握できます。
ちなみに、無理のない返済プランを立てるには、年収は「税込(額面)年収」よりも「手取り年収」での返済負担率を考慮したほうがよいでしょう。額面年収から2割を引くと、手取り収入の目安が計算できます。
住宅ローン審査では税込の年収が用いられます。しかし住宅ローンの返済期間は長いため、予想外のトラブルにも対応できるよう考慮しておくことが必要です。住宅ローン返済額の計算は、生活の実態に合った手取り年収のほうで計算するようにしましょう。
[年収別]家を買う際の金額目安
家を購入する際、年収によっていくらの家が買えるのか、年収別に金額の目安をみていきます。
月々の返済額がいくらになるのか把握し、家計が苦しくなる可能性はないか確認しておきましょう。
ご自分の年収と購入する家の価格の目安として、【年収400万未満の場合】【年収500~800万の場合】【年収1000万以上の場合】の3パターンで見ていきます。
仮に固定金利1.4%で、35年間にわたってローンを返済した場合の借入可能額の目安を例にあげます。(毎月の返済額が一定となる元利均等返済を選択)
返済負担率は25%とします。住宅ローン返済のイメージをつかんでみてください。
【年収400万未満の場合】
年収300万円で、月々の返済額が7.5万円の場合、借入可能額は金利1.0%だと2479万円。金利1.5%だと2286円になります。
【年収500~800万の場合】
年収600万円で、月々の返済額が15万円の場合、借入可能額は金利1.0%だと5314万円。金利1.5%だと4899円になります。
【年収1000万以上の場合】
年収1000万円で、月々の返済額が25万円の場合、借入可能額は金利1.0%だと8856万円。金利1.5%だと8165円になります。
年収が多いほど借入可能額が増えていきます。年収が多くなくても、頭金を多めに用意するなどしておくと、買いたい家を手に入れられる可能性は上がります。
また年収が同じであれば月々の返済額は変わりませんが、金利が低いほうが借入金額を増やすことが可能です。
【無料】不動産購入の悩みをLINEで解決!
・LINE登録後の電話営業は一切ありません
・面倒な個人情報の入力は不要です
・AIではなく、経験豊富なスタッフが対応します
将来の暮らしやお金のことまで考えると、簡単には決められない「住まい」の選択。スマトリのLINE相談では、無理に購入を勧めるのではなく、あなたの状況に合ったベストな選択肢を一緒に考えます。
「親や知人には相談しづらい」「ネットの情報が多すぎて正解が分からない」などお悩みを抱えている方は、不動産のプロにLINEで直接相談してみてください。
\電話営業は一切ナシ!まずは気軽にチャット/
スマトリ公式LINEで無料相談する
さいごに
この記事では、住宅を購入する際に、年収を目安とした家の購入可能金額について解説しました。
さいごに「返済負担率を20%にした場合、返済額がどの程度変わるか」といったことも確認しておきましょう。前述したように、家を購入しているのは、年収400万円~800万円の世帯が多いので年収600万円の場合で比較してみます。
年収600万円で返済負担率を20%にした場合、借入可能額は4140万円から3310万円に、月々の支払い額は約12万4700円から約9万9700円に変わります。返済負担率が5%下がるだけで、借り入れ可能額、月々の支払額に大きな差が生じます。
同じ年収の世帯でも、子どもの養育費や親の介護、車のローンがある場合などそれぞれのケースで状況は異なってくるでしょう。ご紹介した返済可能額の計算方法や、返済負担率を参考に各家庭に沿った資金計画を立てることが必要です。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。